sein はリアルな述語ではない [ノート]
気が付いてみれば、もう半年も更新していなかった。が、これといって書きたいこともない。で、ここは、嘗て翻訳してみようとして中途で放り出してしまった「神の存在のオントロジカルな証明の不可能性について〔Von der Unmöglichkeit eines ontlogischen Beweises vom Dasein Gottes〕」というカントの『純粋理性批判』の一節のその訳文に手を加え披露して、ひとまずお茶を濁すことにしたい。
ここまでからして、次のことは容易に判る: 絶対必然的存在者という概念〔der Begriff eines absolut notwendigen Wesens〕は純粋な理性概念つまり単なるアイディア〔Idee〕であり、そのオブジェクティヴ・リアリティ〔objektive Realität〕は理性がそれを必要としていることによって証明されているなどという訳には到底いかず、また、このアイディアは到達不能にもかかわらず確とした完璧さをただ当てにさせるばかりであって、実のところ、悟性を新たな対象〔Gegenstände〕へと拡張することよりは、限定することに役立つ。ところが、ここに、およそ所与の存在〔Dasein〕から何か只管必然的な存在への推論が緊要で当を得ているように見えるにもかかわらず、そのような必然性の概念を懐くための悟性の条件の総てに我々は全く悖叛しているという訝しくも馬鹿げた事態が見出される。
ひとはいつの時代にも絶対必然的存在者について語って来たが、その種のものをそもそも考えることができるのかどうか、それに如何にして、ということを理解することよりは、むしろ、その存在を証明することに骨を折って来た。ところで、それはつまりその非在〔Nichtsein〕が不可能であるような何かであるといったような、この概念の名目的説明はいかにも非常に手軽ではあるものの、しかし、それでは、ものの非在を全然思考不能と看做すのを不可能にする条件を顧慮するに、我々はちっとも悧巧にならない。我々が知りたいのは実にそうした条件、つまりは件の概念によって我々はそもそも何かを考えているのか否かということなのにだ。私にとって、無条件という言葉をもちだして、悟性が何かを必然的と看做すのに常に必要とする条件の総てを放棄することは、では無条件に必然的という概念によって私はまだ何かを考えているのか、あるいはひょっとしてもう何も考えてなどいないのか、ということを到底はっきりさせはしないのだ。
そればかりか、ひとはおまけにこの単に出たとこ勝負で賭けられ結局すっかり周知となった概念を大量の例でもって説明することに信を置いたため、それを明瞭にするためのどんな問いももう全く無用に見えるのだった。例えば三角形は三つの角をもつといったような幾何学の命題は何れも只管必然的だ。そして、ひとは我々の悟性の領域の全く外に位置する対象について、まるで自分が件の概念でもってそれについて何を云おうとしているのかを十全に理解しているかのごとく、語るのだった。
これまでに呈示されている例の総ては例外なくもっぱら判断に関して採られており、ものとその存在に関してではない。判断の無条件の必然性は、だが、事態の絶対的必然性ではない。判断の無条件の必然性は事態の、もしくは当の判断における述語の条件附き必然性に過ぎないのだ。先の命題は、三つの角が全然必然的だということではなく、何らかの三角形がそこにある〔da ist〕(所与である)という条件のもとでは、三つの角もまたそこに(その三角形の中に)必然的にあるということを述べているのだった。それにもかかわらず、この論理的必然性は大変な幻惑力を発揮したのであって、ひとは、ものというアプリオリな概念〔einen Begriff a priori von einem Dinge〕を懐きつつ、自らの見解のままに、存在なるもの〔das Dasein〕をもこの概念の範囲において把握することとなったあげくに、次のように確と推論し得ると思い込むのだった: この概念のオブジェクト〔Objekt〕には存在が必然的に当てはまる訳だから、つまり、私がこのものを所与(存在するもの〔existierend〕)として立てるという条件のもとでは、それの存在もまた(同一律によって)必然的に立てられることになるから、この存在者〔Wesen〕それ自体が、したがって、全然必然的である――というのは、それの存在は随意に想定される概念において、その対象を私が立てるという条件のもとでは、一緒に考えられることになる訳だから。
私が或る同一性判断における述語を破棄し主語を保持すれば、矛盾が生じ、そこで、私は云う: この述語はこの主語に必然的に当てはまる。だが、主語を述語もろともに破棄すれば、矛盾は生じない。矛盾を来たし得るものなどもはや何もないからだ。或る三角形を立てることとなおかつその三つの角を破棄することは矛盾するが、しかし、その三つの角もろとも当の三角形を破棄することは矛盾ではない。絶対必然的存在者という概念についても、ことはまさに同様だ。それの存在を破棄するとき、君等はそのものそれ自体をそれの述語の総てとともに破棄するのであり、すると矛盾はいったい何処からやって来るというのか? 当のものは外的に必然的である訳がないから、外的には矛盾を来たすものなど何もないし、また、そのものそれ自体の破棄によって、君等はその内部の総てを同時に破棄したのだから、内的にも何もない。神は全能であるというのは必然的判断だ。神というようなものつまり無限の存在者を君等が立てるとき、無限の存在者という概念と全能という概念は一致するから、全能は破棄され得ない。君等が、しかし、神はあらぬ〔Got ist nicht〕と云うとき、全能も他のどんな神の述語も呈されてはない。そうした述語は主語もろとも総て破棄されているからであり、そして、この思考にはほんの僅かの矛盾さえ姿を現わしてはいない。
sein 〔英語ならば be、フランス語ならば être〕は、明らかに、リアルな述語つまりものの概念に加わり得るような何かのその概念ではない〔Sein ist offenbar kein reales Prädikat, d. i. ein Begriff von irgend etwas, was zu dem Begriffe eines Dinges hinzukommen könne〕。それは単にものの、もしくは或る種の規定そのものの措定だ。論理的使用においては、それは判断のコプラに過ぎない。Gott ist allmächtig 〔神は全能である〕という命題は神および全能というオブジェクトをもつふたつの概念を含んでおり、ist という一語はもうひとつの述語ではなく、ただ述語を主語との関係において立てるだけのものだ。私がいまこの主語(Gott)をそれの述語の総て――そこには全能も含まれる訳だが――とともにひとまとめにし、そして、Gott ist 〔神はある〕あるいは es ist ein Gott 〔神がある〕と云えば、私は何の新たな述語も神という概念へと立ててはおらず、ただ主語そのものを、詳しく云えば我が概念に相関する対象を、その述語の総てとともに立てているだけだ。両者は正確に同じものを含んでいるはずであり、したがって、私がそれの対象を(er ist 〔それはある〕という表現によって)只管所与として考えるということに係って、単に可能性を表現しているだけの件の概念に、さらに何かが加わることなどあり得ない。そういう訳で、現実のものは単に可能なものが含んでいる以上の何も含んではいない。・・・
ちなみに、俺が『純粋理性批判』の特にこの一節に興味を覚えたのは、木田元の『ハイデガーの思想』(岩波新書)を読んだせいなのだった。その「カントの存在概念」という節によれば、上の文中に見られる「sein はリアルな述語ではない」というテーゼにおける「real」(ドイツ語風に云えばレアール)という語は、ラテン語の「res(物)」に由来し、カントの時代には「物の事象内容を示す」というような意味で使われていて、今日におけるような実在的という意味はもたなかったのだそうで、そのことはハイデガーが『現象学の根本問題』という講義で「明快に説き明かして」いるのだそうな。で、木田は云うのだ。「これだけでも驚くべき発見であった」と。
ほう、そうかね、てな訳で、ろくすっぽ読んだことがなかった手もちの河出書房新社版『純粋理性批判』(高峯一愚訳)を覘いてみると、だが、どうも様子が違うのだった。木田は「real」を実在的という意味に解してしまうと件のテーゼは「まったく意味がわからなくなる」と云うのだが、しかし、「リアルな述語」(河出版では「実在的述語」)は、上の通り、その都度ちゃんと「ものの規定」、「ものの概念に加わり得るような何かのその概念」と云い替えられている訳で、何が問題になっているのか、明確にとはいかないにしても、一応は理解することができるではないか。ハイデガーがどんなふうに論じているのかは知らないが、木田の言は勇み足というものだろう。(むしろ判らないのはオブジェクティヴ・リアリティという概念の方だが、それはさておき、そもそもそうして間を置かずに出て来る「リアルな述語」が二度とも律儀に云い替えられているのは、カントの時代にも、やっぱり誤解される可能性が十分あったからなのではなかろうか? )
ともあれ、そうして当たってみた河出版『純粋理性批判』の訳文というのがどうもいまひとつ要領を得ないしろもので、で、それがきっかけとなって、件の節を自分で翻訳してみようという気を止しゃあいいのに俺は起こしてしまったのだった。が、いざ手をつけてみると、カントの文章は何やら破格で、しかもごたごたしていて判りにくく、おまけに日本語にうつすのが難しくて、あれこれ苦心して訳文をひねるのがすぐに阿呆らしくなって、で、さっさと放り出してしまった、という次第なのだ。
その名残をここにこうして収めて、俺にも『純粋理性批判』をまっとうに読もうとしたことがあったのだという紀念としておく。
☆ ☆ ☆
ここまでからして、次のことは容易に判る: 絶対必然的存在者という概念〔der Begriff eines absolut notwendigen Wesens〕は純粋な理性概念つまり単なるアイディア〔Idee〕であり、そのオブジェクティヴ・リアリティ〔objektive Realität〕は理性がそれを必要としていることによって証明されているなどという訳には到底いかず、また、このアイディアは到達不能にもかかわらず確とした完璧さをただ当てにさせるばかりであって、実のところ、悟性を新たな対象〔Gegenstände〕へと拡張することよりは、限定することに役立つ。ところが、ここに、およそ所与の存在〔Dasein〕から何か只管必然的な存在への推論が緊要で当を得ているように見えるにもかかわらず、そのような必然性の概念を懐くための悟性の条件の総てに我々は全く悖叛しているという訝しくも馬鹿げた事態が見出される。
ひとはいつの時代にも絶対必然的存在者について語って来たが、その種のものをそもそも考えることができるのかどうか、それに如何にして、ということを理解することよりは、むしろ、その存在を証明することに骨を折って来た。ところで、それはつまりその非在〔Nichtsein〕が不可能であるような何かであるといったような、この概念の名目的説明はいかにも非常に手軽ではあるものの、しかし、それでは、ものの非在を全然思考不能と看做すのを不可能にする条件を顧慮するに、我々はちっとも悧巧にならない。我々が知りたいのは実にそうした条件、つまりは件の概念によって我々はそもそも何かを考えているのか否かということなのにだ。私にとって、無条件という言葉をもちだして、悟性が何かを必然的と看做すのに常に必要とする条件の総てを放棄することは、では無条件に必然的という概念によって私はまだ何かを考えているのか、あるいはひょっとしてもう何も考えてなどいないのか、ということを到底はっきりさせはしないのだ。
そればかりか、ひとはおまけにこの単に出たとこ勝負で賭けられ結局すっかり周知となった概念を大量の例でもって説明することに信を置いたため、それを明瞭にするためのどんな問いももう全く無用に見えるのだった。例えば三角形は三つの角をもつといったような幾何学の命題は何れも只管必然的だ。そして、ひとは我々の悟性の領域の全く外に位置する対象について、まるで自分が件の概念でもってそれについて何を云おうとしているのかを十全に理解しているかのごとく、語るのだった。
これまでに呈示されている例の総ては例外なくもっぱら判断に関して採られており、ものとその存在に関してではない。判断の無条件の必然性は、だが、事態の絶対的必然性ではない。判断の無条件の必然性は事態の、もしくは当の判断における述語の条件附き必然性に過ぎないのだ。先の命題は、三つの角が全然必然的だということではなく、何らかの三角形がそこにある〔da ist〕(所与である)という条件のもとでは、三つの角もまたそこに(その三角形の中に)必然的にあるということを述べているのだった。それにもかかわらず、この論理的必然性は大変な幻惑力を発揮したのであって、ひとは、ものというアプリオリな概念〔einen Begriff a priori von einem Dinge〕を懐きつつ、自らの見解のままに、存在なるもの〔das Dasein〕をもこの概念の範囲において把握することとなったあげくに、次のように確と推論し得ると思い込むのだった: この概念のオブジェクト〔Objekt〕には存在が必然的に当てはまる訳だから、つまり、私がこのものを所与(存在するもの〔existierend〕)として立てるという条件のもとでは、それの存在もまた(同一律によって)必然的に立てられることになるから、この存在者〔Wesen〕それ自体が、したがって、全然必然的である――というのは、それの存在は随意に想定される概念において、その対象を私が立てるという条件のもとでは、一緒に考えられることになる訳だから。
私が或る同一性判断における述語を破棄し主語を保持すれば、矛盾が生じ、そこで、私は云う: この述語はこの主語に必然的に当てはまる。だが、主語を述語もろともに破棄すれば、矛盾は生じない。矛盾を来たし得るものなどもはや何もないからだ。或る三角形を立てることとなおかつその三つの角を破棄することは矛盾するが、しかし、その三つの角もろとも当の三角形を破棄することは矛盾ではない。絶対必然的存在者という概念についても、ことはまさに同様だ。それの存在を破棄するとき、君等はそのものそれ自体をそれの述語の総てとともに破棄するのであり、すると矛盾はいったい何処からやって来るというのか? 当のものは外的に必然的である訳がないから、外的には矛盾を来たすものなど何もないし、また、そのものそれ自体の破棄によって、君等はその内部の総てを同時に破棄したのだから、内的にも何もない。神は全能であるというのは必然的判断だ。神というようなものつまり無限の存在者を君等が立てるとき、無限の存在者という概念と全能という概念は一致するから、全能は破棄され得ない。君等が、しかし、神はあらぬ〔Got ist nicht〕と云うとき、全能も他のどんな神の述語も呈されてはない。そうした述語は主語もろとも総て破棄されているからであり、そして、この思考にはほんの僅かの矛盾さえ姿を現わしてはいない。
・・・・・・・
論理的述語とリアルな述語(つまりものの規定〔der Bestimmung eines Dinges〕)の混同による幻惑がおおよそどんな諭しもうけつけないことを見出していなかったら、私はこんなくよくよとした論証など、エグジステンス〔Existenz〕という概念の厳密な規定でもって、何の躊躇もなく水の泡にしてしまうことをきっと望んでいるだろう。何であれひとが欲せば論理的述語として用いられ得るのであり、あまつさえ主語はそれ自体によって賓述され得る。論理はあらゆる内容を度外視するからだ。だが、規定は主語をなす概念の上に到来しそれを拡大する述語だ。したがって、それが以前からそこに含まれているはずはない。sein 〔英語ならば be、フランス語ならば être〕は、明らかに、リアルな述語つまりものの概念に加わり得るような何かのその概念ではない〔Sein ist offenbar kein reales Prädikat, d. i. ein Begriff von irgend etwas, was zu dem Begriffe eines Dinges hinzukommen könne〕。それは単にものの、もしくは或る種の規定そのものの措定だ。論理的使用においては、それは判断のコプラに過ぎない。Gott ist allmächtig 〔神は全能である〕という命題は神および全能というオブジェクトをもつふたつの概念を含んでおり、ist という一語はもうひとつの述語ではなく、ただ述語を主語との関係において立てるだけのものだ。私がいまこの主語(Gott)をそれの述語の総て――そこには全能も含まれる訳だが――とともにひとまとめにし、そして、Gott ist 〔神はある〕あるいは es ist ein Gott 〔神がある〕と云えば、私は何の新たな述語も神という概念へと立ててはおらず、ただ主語そのものを、詳しく云えば我が概念に相関する対象を、その述語の総てとともに立てているだけだ。両者は正確に同じものを含んでいるはずであり、したがって、私がそれの対象を(er ist 〔それはある〕という表現によって)只管所与として考えるということに係って、単に可能性を表現しているだけの件の概念に、さらに何かが加わることなどあり得ない。そういう訳で、現実のものは単に可能なものが含んでいる以上の何も含んではいない。・・・
☆ ☆ ☆
ちなみに、俺が『純粋理性批判』の特にこの一節に興味を覚えたのは、木田元の『ハイデガーの思想』(岩波新書)を読んだせいなのだった。その「カントの存在概念」という節によれば、上の文中に見られる「sein はリアルな述語ではない」というテーゼにおける「real」(ドイツ語風に云えばレアール)という語は、ラテン語の「res(物)」に由来し、カントの時代には「物の事象内容を示す」というような意味で使われていて、今日におけるような実在的という意味はもたなかったのだそうで、そのことはハイデガーが『現象学の根本問題』という講義で「明快に説き明かして」いるのだそうな。で、木田は云うのだ。「これだけでも驚くべき発見であった」と。
ほう、そうかね、てな訳で、ろくすっぽ読んだことがなかった手もちの河出書房新社版『純粋理性批判』(高峯一愚訳)を覘いてみると、だが、どうも様子が違うのだった。木田は「real」を実在的という意味に解してしまうと件のテーゼは「まったく意味がわからなくなる」と云うのだが、しかし、「リアルな述語」(河出版では「実在的述語」)は、上の通り、その都度ちゃんと「ものの規定」、「ものの概念に加わり得るような何かのその概念」と云い替えられている訳で、何が問題になっているのか、明確にとはいかないにしても、一応は理解することができるではないか。ハイデガーがどんなふうに論じているのかは知らないが、木田の言は勇み足というものだろう。(むしろ判らないのはオブジェクティヴ・リアリティという概念の方だが、それはさておき、そもそもそうして間を置かずに出て来る「リアルな述語」が二度とも律儀に云い替えられているのは、カントの時代にも、やっぱり誤解される可能性が十分あったからなのではなかろうか? )
ともあれ、そうして当たってみた河出版『純粋理性批判』の訳文というのがどうもいまひとつ要領を得ないしろもので、で、それがきっかけとなって、件の節を自分で翻訳してみようという気を止しゃあいいのに俺は起こしてしまったのだった。が、いざ手をつけてみると、カントの文章は何やら破格で、しかもごたごたしていて判りにくく、おまけに日本語にうつすのが難しくて、あれこれ苦心して訳文をひねるのがすぐに阿呆らしくなって、で、さっさと放り出してしまった、という次第なのだ。
その名残をここにこうして収めて、俺にも『純粋理性批判』をまっとうに読もうとしたことがあったのだという紀念としておく。
2011-07-23 14:06
コメント(0)
Existenz は概念の属性である(?) [ノート]
前回はカントの『純粋理性批判』から「sein はリアルな述語ではない」というテーゼが登場する辺りを引いたが、そうしたら、今度は「「存在する」は二階の述語である」というゴットロープ・フレーゲに由来するらしいテーゼが気になりだした。で、そもそもフレーゲは何処でその類のことを云っていたのか、という訳で、とりあえず飯田隆の『言語哲学大全 I 』(勁草書房)に当たってみたところ、第一章の註のなかに次のようにあった。
「「存在する」が一階の述語ではなく、二階の述語であることを示すフレーゲの議論は、『算術の基礎』に初めて接する人々の多くが大きな感銘を受けるものであると言う。(筆者も幸いにしてその例外ではなかった。)だが、残念ながら、ここでその議論を扱うことはできない。」
そこで、その『Die Grundlagen der Arithmetik』を拾い読みしだしてみたところ、前にも同じようなコースをたどって、同じようにそれを拾い読みしたことがあったのを思いだした。しかも、その折には、飯田が「フレーゲの議論」と呼んでいるものと思しき辺りを翻訳までしていたのだった。二度あることは三度あるという。またすっかり忘れて同じことを繰返すはめにならないともかぎらないので――まあ、それもわるくはないのだが――その訳文に手を加えて、ここに収めておくことにする。
§45. これまでに確かめられたことがらおよび答のないままに留まった問をここで概観しておこう。
数というもの〔die Zahl〕は、色や重さ、硬さなどと同様の仕方で、ものから抽象されてある訳ではない。そうした意味でのものの属性ではない。残ったのは、数の述定〔eine Zahlangabe〕によって何ごとかが叙述されるのは何についてなのか、という問だった。
数は物理的な何かではないが、しかし、また、主観的な何かでもない。表象〔Vorstellung〕というようなものではない。
数はものをものに付加することで生じるのではない。それに、そうした付加の都度の命名がその点に関して何かを変えることもない。
「Vielheit」、「Menge」、「Mehrheit」といった表現〔何れも多いことを意味する〕は、その不定性の故に、数の説明に用いられるには不適格だ。
一〔Eins〕と単位〔Einheit〕に関しては、一つのものと多くのものとの区別をことごとくぼやけさせるように見える解釈の専横を如何に制限すべきか、という問が残るのだった。
被劃定性、不可分性、分解不能性等は、我々が「Ein〔一つのもの〕」という語によって表現していることがらのために利用可能なメルクマール〔Merkmale〕ではない。
数えられ得るものを単位と呼ぶのであれば、単位はみな等しいという無条件の主張は誤っている。そうしたものは或る点においてはみな等しい、ということは確かに正しいが、しかし、無価値だ。数えられ得るものどもの相違は、それどころか、当の数が 1 より大きくなろうものなら、必須でさえある。
そういう訳で、我々は相等性および区別可能性という二つの矛盾する属性を単位どもに付与せざるを得ないように見えるのだった。
一と単位は区別されねばならない。「Eins 〔一〕」という語は、数学研究における或る一つの対象の固有名としては、複数形をとり得ない。したがって、Einsen 〔Eins の複数形〕の統括によって数を生じさせるというのは無意味だ。1 + 1 = 2 におけるプラス記号がそうした統括を表わすことなどあり得ない。
§46. ことを明らかにするためには、数をその元来の用法が際立つような判断のコンテクストにおいて考察するのがいいだろう。私が同一の外的現象を顧慮し同一の真理性を伴って「dies ist eine Baumgruppe 〔これは一つの木叢である〕」および「dies sind fünf Bäume 〔これは五本の木である〕」と、あるいは、「hier sind vier Compagnien 〔ここには四つの中隊が留まっている〕」および「hier sind 500 Mann 〔ここには500人いる〕」と云い得るとすれば、その際に変化するのは、個々のものでもなければ、その全体、集まりといったものでもなく、私の名指しだ。これは、だが、単に或る概念の別の概念による置換のしるしに過ぎない。そこで、前節の最初の問への答として、数の述定は何らかの概念についての何らかの叙述を含む、ということがすぐに思い浮かぶ。それが最も明瞭なのは数 0 の場合だろう。私が「die Venus hat 0 Mond 〔金星は0箇の衛星をもつ〕」と云うとき、それについて何ごとかが叙述され得るような衛星や衛星の集まりなどそこには全然ない。ところが、それによって「Venusmond 〔金星の衛星〕」という概念には一つの属性が付与される。何も包摂しないという属性が、だ。「der Wagen des Kaisers wird von vier Pferden gezogen 〔皇帝の車は四頭の馬によって牽かれる〕」と云うとき、私は「Pferd, das den Wagen des Kaisers zieht 〔皇帝の車を牽く馬〕」という概念に四という数を付与している。
ひとは反論するかも知れない。数の述定が概念について何かそうしたことを叙述するのだとすれば、例えば「ドイツ帝国の成員」というような概念は、そのメルクマールは変わらないにもかかわらず、年々変化する属性をもつことになるだろう、と。それに対してひとは、対象はその属性を変えるが、そのことはそれを同一であると認めることを妨げるものではない、と押し返すことができる。しかも、この場合、その理由はさらに詳しく述べられ得る。「ドイツ帝国の成員」という概念は時を可変的成分として含んでいる。つまり、数学的に表現させてもらうならば、それは時の関数なのだ。ひとは「a はドイツ帝国の成員である」に代えて「a はドイツ帝国に属している」と云うことができるが、これは今現在の時点に係っている。したがって、当の概念そのものに既に流動的なところがある訳だ。一方、「ベルリン時1883年初頭におけるドイツ帝国の成員」という概念には永久不変に同一の数が与えられる。
§47. 数の述定が我々の解釈には依存しない実際のことがらを表現するということを驚異と受けとるのは、概念を表象と同様の主観的なものと看做す者だけだ。しかし、そうした見解は誤っている。例えば、物体という概念を重さをもつものという概念の下位に置くなり、鯨という概念を哺乳動物という概念の下位に置くなりするとき、我々はそれによって客観的なことがらを主張している。ところが、もし概念が主観的だとしたら、或る概念が別の概念の下位に位置することもまた、それらの間の関係として、表象間の関係と同様、主観的なものだということになるだろう。たしかに、
§48. 同一のものにまちまちの数が与えられるようだという、上の幾つかの例に生じた見かけは、その際に対象が数の担い手として仮定された、ということで説明がつく。我々がその真の担い手、概念を正当な地位に就けるや否や、数はその勢力範囲において色と同様の排他性を顕わにする。
ここで、また、何故にひとが数をものからの抽象によって獲得しようとするに到るのかも判る。ひとが抽象によって獲るのは概念であり、そのときそこにひとは数を見出す。そうして、抽象は実際にしばしば数の判断の形成に先行する。その取り違えは、板壁と藁葺屋根を伴う木骨造りでもって洩れやすい煙出しをもつ家屋を建てることで、引火しやすさという概念が獲られる、と云い張る場合に同断だ。
概念の結集力は総合的統覚の統合力をはるかに超えている。統覚によってはドイツ帝国の成員達をひとつの全体へと束ねることなど可能ではないだろうが、しかし、ひとは彼等を「ドイツ帝国の成員」という概念のもとに置き、数えることができる。
ここで、また、数の広範な適用可能性も説明がつくことになる。実際、外的現象とともに内的現象について、空間的かつ時間的な現象とともに非空間的かつ非時間的な現象について、どうして同じことが叙述され得るのかは不可解だ。ところが、数の述定においてはそうしたことは全然おこなわれはしないのだ。数は、ただ、外的現象と内的現象が、空間的現象と時間的現象が、非空間的現象と非時間的現象がそのもとに置かれている概念に付与されるに過ぎない。
§49. 我々の見解への裏書の一つは、スピノザのもとに見出される。彼は次のように云う。「ものは単にその存在〔Existenz〕への顧慮によって一つのとか唯一のとかと云われるのであって、その本質〔Essenz〕への顧慮によってではない、と私は答えよう。我々がものどもを数のもとに表象するのは、もっぱらそれらが何らかの共通の尺度を宛がわれた後においてだからだ。例えば、一箇のセステルティウスと一箇のインペリアルを手に持っている者は、そのセステルティウスとインペリアルのそれぞれに硬貨もしくはコインという同じ名称を負わせることができなければ、箇数二〔die Zweizahl〕を思ったりはしないだろう。それができれば、彼は自分が二つの硬貨もしくはコインをもっていることを肯定し得る。彼はそのセステルティウスばかりでなくそのインペリアルをもまたコインという名称によって表示する訳だから。」ところが、「このことからして、ものが一つのとか唯一のとかと云われるのは、もっぱらそれに(既述のとおり)合致する何か別のものが表象された後においてであることは明らかだ」と続けるとき、そして、我々は神の本質について何の抽象的概念も形成し得ないのだから、本来の意味においては神を一つのとか唯一のとか云うことはできない、と云うとき、概念は多くの対象からの直接の抽象によってしか獲得され得ないと考える点において、彼は間違っている。ひとはメルクマールから概念へと達することもできるのであって、しかも、そのとき当の概念に帰属するものは何も無いということも可能なのだ。もし、そうしたことが生じないとしたら、ひとは決して存在なるものを否定し得ないだろうし、それとともに存在の肯定もまたその内容を失うことだろう。
§50. E. シュレーダーは、一つのものの頻出〔Häufigkeit〕が語られ得るのであれば、そうしたものの名称は常にクラス名〔ein Gattungsname〕、一般概念語〔ein allgemeines BegriffsWort〕(notio communis)でなければならない、ということを強調している。「つまり、ひとがひとつの対象を完全に――その総ての属性および関係とともに――捕捉するや否や、それは世界に唯一の身となり、もはや同類をもたないだろう。また、その対象の名称は固有名(nomen proprium)の性格を帯びるだろうし、当の対象は繰り返し出現するものとは考えられ得ない。このことは、だが、単に具体的な対象にばかりでなく、そもそもあらゆるものについて成り立つ。たとえそれの表象が抽象によって成ろうとも、ただその表象だけが当のものを完全に特定されたものとするに十分であるようなエレメントを包含している限りは、だ。 ・ ・ ・ 後者」(数えのオブジェクトとなること)「は何らかのものにおいて、そして、そのものがそれらによって自余の総てのものと区別されるようなそれに固有のメルクマールや関係の幾つかをひとが考慮の外におくなり度外視するなりする限りにおいて、初めて可能となる。それによって、そのとき初めて、ものの名称は多くのものに適用可能な概念となる。」
§51. この説明における真実は胡乱で紛らわしい云い回しで表現されているため、整理と吟味が必要だ。まず、一般概念語をものの名称と呼ぶのは不適切だ。それによって、まるで数がものの属性であるかのような見かけが生じる。一般概念語はまさに概念を表示するのだ。それは、ただ定冠詞もしくは指示代名詞を伴ってのみ、ものの固有名として通用するが、ただし、それとともに概念語として通用することをやめる。ものの名称は固有名だ。一つの対象が繰り返し出現するのではなく、多くの対象が一つの概念に帰属する。概念はただそれに帰属するものどもからの抽象によってのみ獲得される訳ではないということは、既にスピノザに反対して述べた。ここで私は、概念はただ一つのものしかそれに帰属しない――したがって、そのものは当の概念によって完全に特定されている――ことで概念であることをやめたりはしない、ということを付け加えよう。そうした概念(例えば、地球の衛星〔Begleiter der Erde〕)にまさに与えられるのが、2 や 3 と同じ意味において数である数 1 だ。概念の場合、それに何かが帰属するのか否か、そして何がそれに帰属するのかが常に問われる。固有名の場合、そうした問は無意味だ。言語が例えば「Mond 〔月〕」という固有名を概念語として〔衛星という意味で〕用い、その逆もあるということに、ひとは欺かれぬようにせねばならない。区別はそれでもやはり存続するのだ。不定冠詞を伴って、もしくは冠詞なしに複数形で使われるや否や、語は概念語となる。
§52. 数は概念に付与されるという見解へのもう一つの裏書は、ひとが zehn Mann 〔十人〕とか、vier Mark 〔四マルク〕、drei Fass 〔三ファス、三樽〕と云う場合のドイツ語の用語法〔何れにおいても名詞が単数形で単位として用いられている〕に見出され得る。単数形はここではものではなく概念が考えられていることを暗示しているのかも知れない。この表現法の長所は数 0 において殊に際立つ。こうしたケースを除けば、いかにも言語は概念ではなく対象に数を付与する。ひとは、「Gewicht der Ballen 〔梱どもの重さ〕」と云うのと同様に、「Zahl der Ballen 〔梱どもの数〕」と云うのだ。そうして、ひとは本当は概念について何かを叙述するつもりが、外見上は対象について語っている。こうした用語法はことを紛糾させる。「vier edle Rosse 〔四頭の純血種の乗用馬〕」という表現は、「edel 〔純血種の〕」が「Ross 〔乗用馬〕」を規定するのと同様に、「vier 〔四〕」が「edles Ross 〔純血種の乗用馬〕」をさらに規定するかのような見かけを呼び起こす。しかし、「edel」だけがそうしたメルクマールなのであって、「vier」という語によって、我々は概念について何ごとかを叙述している。
§53. 概念について叙述される属性とは、もちろん、当の概念を構成するメルクマールのことではない、と私は解する。メルクマールは当の概念に帰属するものの属性であって、その概念の、ではない。例えば、「直角〔rechtwinklig〕」は「直角三角形〔rechtwinkliges Dreieck〕」という概念の属性ではない。一方、直角正等辺三角形は存在しない〔es kein rechtwinkliges, geradliniges, gleichseitiges Dreieck gebe〕という命題は「直角正等辺三角形」という概念の一属性を述べており、この概念には箇数零〔die Nullzahl〕が付与される。
この点で存在なるもの〔die Existenz〕は数に似ている。存在の肯定は箇数零の否定に他ならないのだ。存在は概念の属性であるが故に、神の存在のオントロジカルな証明〔der ontologische Beweis von der Existenz Gottes〕はその目的を果たさない。存在と同じく唯一性もまた「神」という概念のメルクマールではない。唯一性がこの概念の定義に使われ得ないことは、ひとが家屋の建築に際してその丈夫さとか広さ、快適さを石材やモルタルや角材と諸共に用いることなどできないのと同断だ。しかしながら、何かが或る概念の属性であるということから、それが当の概念から、つまりはそのメルクマールから推論されることはあり得ないと結論することは、一般に許されない。場合によっては、それは可能だ。ひとが建築用石材の種類から建物の耐久性について間々結論をくだし得るのと同様に、だ。したがって、概念のメルクマールから唯一性なり存在なりが結論されることは決してあり得ない、とするのは云い過ぎというものだろう。ただ、それは、ひとが概念のメルクマールを当の概念に帰属する対象に属性として付与するようには、そう直接には、為され得ないのだ。
存在と唯一性がいつか概念のメルクマールとなり得る、ということを否認するのもまた誤りだろう。それらは、単に、ひとが言語に則してそれらをそのメルクマールと看做そうとするような、そうした概念の当のメルクマールなどではないまでだ。例えば、ただ一つの対象だけがそれに帰属するような概念の総てをひとつの概念のもとに集めれば、唯一性はこの概念のメルクマールだ。この概念には例えば「地球の衛星〔Erdmond〕」という概念が帰属することになるのであって、そう呼ばれる天体が、ではない。そうして、ひとは概念を高次の〔höhern〕、謂わば第二次の〔zweiter Ordnung〕概念に帰属させ得る。ただし、この関係を従属関係と混同してはならない。
§54. いまや単位を満足のいくように説明することが可能だろう。E. シュレーダーは先の教科書の7ページで「そうしたクラス名あるいは概念は既述の方法で形成された数の呼称と呼ばれ、その単位の本質を成す」と云っている。
実際、或る概念を、それに与えられる箇数〔Anzahl〕との係りで、単位と呼ぶのは、極めて適切なことではなかろうか。そのとき、それは周囲から分離されていて分割不能である、という単位についての叙述に我々は意味を見出すことができる。数を付与される当の概念は一般にそれに帰属するものを明確な仕方で劃すからだ。「Buchstabe des Wortes Zahl 〔Zahl という語を成す文字〕」という概念は Z を a から劃し、a を h から劃し、等々。「Silbe des Wortes Zahl 〔Zahl という語のもつシラブル〕」という概念は当の語をひとつの全体として、そして、そのどんな部分ももはや「Silbe des Wortes Zahl」という概念には帰属しないという意味で、分割不能なものとして、際立たせる。総ての概念がそのようである訳ではない。我々は、例えば、赤という概念に帰属するものを様々な仕方で分割することができる。分割された部分が当の概念に帰属しなくなることなしに、だ。そうした概念にはどんな有限数も与えられることはない。そこで、単位の被劃定性と分割不能性についての命題というものが、次のように述べられ得る。
それに帰属するものを明確に劃し、どんな恣意的な分割も許さないような概念だけが、有限の箇数に係る単位であり得る。
分割不能性はここで特別の意義〔Bedeutung〕をもっていることが判るだろう。
いまや、どうして相等性は単位の区別可能性によって邪魔され得ないのか、という問に答えるのは簡単だ。「単位〔Einheit〕」という語はここで二重の意味で用いられている。単位どもは、上で説明されたこの語の意義において、等しい。「Jupiter hat vier Monde 〔木星は四つの衛星をもつ〕」という命題においては、単位は「Jupitersmond 〔木星の衛星〕」だ。第一衛星と同様、第二衛星も、第三衛星も、第四衛星も、この概念に帰属する。したがって、ひとは次のように云うことができる。第一衛星が関聯づけられる単位は第二衛星が関聯づけられる単位に等しい云々。その点で、我々は相等性を手にしている。一方、単位どもの区別可能性を主張するとき、ひとはそれによって数えられるものどもの区別可能性を考えているのだ。
フレーゲは、この『算術の基礎』(1884年)に先立つ『概念記法』(1879年)において、ファンクションとアーギュメントという道具立てでもって文を分析する方法を呈示し、いわゆる量化理論を展開することで、論理学を新たな段階へと齎したのだった。そこで定式化された論理のエッセンスは、今日では「古典論理」と呼ばれ、スタンダードとなっている訳だが、その古典論理においては、あらゆるものはかくかくである――今日一般的な論理記号を使って書けば、∀x(x はかくかくである)――ということと、かくかくでないものは存在しない――¬∃x¬(x はかくかくである)――ということは同等であり、また、あらゆるものがかくかくでない訳ではない――¬∀x¬(x はかくかくである)――ということと、かくかくであるものが存在する――∃x(x はかくかくである)――ということも同等だ。したがって、古典論理の体系を考える場合、「あらゆる」に関わる普遍量化か「存在」に関わる存在量化かのどちらか一方を採れば、他方は無しに済ますことが可能であり、実際、フレーゲの概念記法体系には、いわゆる存在量化子に相当するものは具わっていない。その点からすれば、「存在の肯定は箇数零の否定に他ならない」という彼の言葉は、「かくかくであるものが存在する」を、かくかくであるものの箇数は零でない、ということによってあらためて定義しているものと解釈され得る。
ところで、フレーゲが唯一性について云っていることを存在について当てはめてみれば、次のようになる: それに帰属する対象の箇数が零でない概念の総てをひとつの概念のもとに集めれば、存在はこの概念のメルクマールである。この云い回しは、「存在は概念の属性である」という云いぐさともども、いかにも胡乱というものだが、それはさておき、このアイディアは、1891年の『関数と概念』を経て、1893年の『算術の基本法則』第一巻において、その体系に即して具体化されることとなる。そこでは、今日一般的な記号法で書けば、「∀xΦx」という形をした、いわゆる自由変数を含まない表現は、「Φ」によって表わされる一変数の関数――対象を真理値(真か偽)に対応づける関数――を真理値に対応づける或る第二水準の関数(Funktion zweiter Stufe)の値を表わすものとされ、また、「¬∀x¬Φx」というような表現は、「Φ」によって表わされる一変数関数と「¬」によって表わされている真理値を反転する関数との合成関数 ¬Φ についての件の第二水準の関数の値(真か偽)が関数 ¬ によって反転された値を表わすものとされる。(「∀xΦx」によって表わされる真理値は、あらゆる対象について関数 Φ の値が真であれば、真であり、そうでなければ、偽だ。また、「¬∀x¬Φx」によって表わされる真理値は、あらゆる対象について関数 ¬Φ の値が真(つまり Φ の値が偽)であれば、偽であり、そうでなければ、真だ。)そこで、「Φ」という説明の便宜上の不定の表現を今度は空位を示す目印と看做せば、「∀xΦx」および「¬∀x¬Φx」はそれぞれに或る第二水準の関数を表わしているものと解釈され得る。その意味での関数 ¬∀x¬Φx は、それに帰属する対象の箇数が零でない概念の総てを、そしてそれらだけを包摂する概念に相当する、と云えるだろう。実際、フレーゲは第一水準の一変数関数を「第一水準の概念」、第二水準の一変数関数を「第二水準の概念」と呼んでいるのであり、上で彼が「概念」と云っているのも、あるいは、そうした関数に類するもののことなのかも知れない。
ついでに、「「存在する」は二階の述語である」というテーゼについて。この胡乱な云いぐさは、上のような、『算術の基本法則』の体系に即して呈示されたアイディアを、量化理論的語法で補強された自然言語に適用することから捻り出された、と云えるだろう。それを飯田の『言語哲学大全 I 』の第一章に則って見ておこう。
そこでは、「述語」という語は次のような意味で用いられている。
「いくつかの空所をもつ以外は文と同じであり、それらの空所を名前で填めれば文となる形式を「述語」と呼ぶことにしよう。」(ここで「名前」と云われているのは何らかの個体を指す表現のことだと解していいだろう。また、空所はそのような名前によってのみ充填され得るものとしなければならない。それから、「いくつかの空所」とは、単に複数の空所のことではなく、いくつかのグループに分けられた複数の空所のことであり、同じグループの空所は同じ名前によって一斉に充填されるのだと考えるべきだろう。ちなみに、このグループ分けされた空所をもつ形式というアイディアは『概念記法』のファンクションとアーギュメントという道具立てがイントロダクション用に簡便化されたものだと云える。)
例えば――飯田がこうした例を用いている訳ではないが――「ルート2 は分数では表現され得ない数である」という文から「ルート2」という一つの数を指す表現を除外すれば、「・・・は分数では表現され得ない数である」という述語が得られる。(このように、文からその一部を、単なる部分としてではなく、空所をもつ形式として切り出すところが味噌だ。)ところで、「分数では表現され得ない数が存在する」という文は、「ある x について、x は分数では表現され得ない数である」と書き換えられ得る。(ここに量化理論的語法が登場している訳だ。)そこで、そこから件の述語を除外した「ある x について、x ・・・」という形式を考えれば、その空所は、空所を一つもつ(つまり空所のグループを一つだけもつ)あらゆる述語によって、充填され得るものと看做され得る。(この「ある x について、x ・・・」という形式は、それに帰属する対象の箇数が零でない概念の総てを、そしてそれらだけを包摂する概念を表わす、と云えるだろう。)そうした意味で、「ある x について、x ・・・」を「二階の述語」と呼ぶことができるだろうと飯田は云う。そして、さらに、この二階の述語が「存在を表現するものである」と看做され得ることから、ひとつの「教訓」が引き出され得る、と彼は云うのだ。
「すなわち、「存在する」は、述語ではあるが、「ねたむ」や「カラスである」のような、個体について言われる一階の述語ではなく、こうした一階の述語について言われる二階の述語なのである。」(冒頭に引いた註はここに付されている。)
「存在は概念の属性である」と同様、「「存在する」は二階の述語である」という云いぐさもまた、こうしたコンテクストから切り離されれば、混乱の種でしかないだろう。要注意。
さて、カント、フレーゲとくれば、次はクワインの段だろうが、さしあたり俺にはそれに関して書くべきことはない。
「「存在する」が一階の述語ではなく、二階の述語であることを示すフレーゲの議論は、『算術の基礎』に初めて接する人々の多くが大きな感銘を受けるものであると言う。(筆者も幸いにしてその例外ではなかった。)だが、残念ながら、ここでその議論を扱うことはできない。」
そこで、その『Die Grundlagen der Arithmetik』を拾い読みしだしてみたところ、前にも同じようなコースをたどって、同じようにそれを拾い読みしたことがあったのを思いだした。しかも、その折には、飯田が「フレーゲの議論」と呼んでいるものと思しき辺りを翻訳までしていたのだった。二度あることは三度あるという。またすっかり忘れて同じことを繰返すはめにならないともかぎらないので――まあ、それもわるくはないのだが――その訳文に手を加えて、ここに収めておくことにする。
☆ ☆ ☆
§45. これまでに確かめられたことがらおよび答のないままに留まった問をここで概観しておこう。
数というもの〔die Zahl〕は、色や重さ、硬さなどと同様の仕方で、ものから抽象されてある訳ではない。そうした意味でのものの属性ではない。残ったのは、数の述定〔eine Zahlangabe〕によって何ごとかが叙述されるのは何についてなのか、という問だった。
数は物理的な何かではないが、しかし、また、主観的な何かでもない。表象〔Vorstellung〕というようなものではない。
数はものをものに付加することで生じるのではない。それに、そうした付加の都度の命名がその点に関して何かを変えることもない。
「Vielheit」、「Menge」、「Mehrheit」といった表現〔何れも多いことを意味する〕は、その不定性の故に、数の説明に用いられるには不適格だ。
一〔Eins〕と単位〔Einheit〕に関しては、一つのものと多くのものとの区別をことごとくぼやけさせるように見える解釈の専横を如何に制限すべきか、という問が残るのだった。
被劃定性、不可分性、分解不能性等は、我々が「Ein〔一つのもの〕」という語によって表現していることがらのために利用可能なメルクマール〔Merkmale〕ではない。
数えられ得るものを単位と呼ぶのであれば、単位はみな等しいという無条件の主張は誤っている。そうしたものは或る点においてはみな等しい、ということは確かに正しいが、しかし、無価値だ。数えられ得るものどもの相違は、それどころか、当の数が 1 より大きくなろうものなら、必須でさえある。
そういう訳で、我々は相等性および区別可能性という二つの矛盾する属性を単位どもに付与せざるを得ないように見えるのだった。
一と単位は区別されねばならない。「Eins 〔一〕」という語は、数学研究における或る一つの対象の固有名としては、複数形をとり得ない。したがって、Einsen 〔Eins の複数形〕の統括によって数を生じさせるというのは無意味だ。1 + 1 = 2 におけるプラス記号がそうした統括を表わすことなどあり得ない。
§46. ことを明らかにするためには、数をその元来の用法が際立つような判断のコンテクストにおいて考察するのがいいだろう。私が同一の外的現象を顧慮し同一の真理性を伴って「dies ist eine Baumgruppe 〔これは一つの木叢である〕」および「dies sind fünf Bäume 〔これは五本の木である〕」と、あるいは、「hier sind vier Compagnien 〔ここには四つの中隊が留まっている〕」および「hier sind 500 Mann 〔ここには500人いる〕」と云い得るとすれば、その際に変化するのは、個々のものでもなければ、その全体、集まりといったものでもなく、私の名指しだ。これは、だが、単に或る概念の別の概念による置換のしるしに過ぎない。そこで、前節の最初の問への答として、数の述定は何らかの概念についての何らかの叙述を含む、ということがすぐに思い浮かぶ。それが最も明瞭なのは数 0 の場合だろう。私が「die Venus hat 0 Mond 〔金星は0箇の衛星をもつ〕」と云うとき、それについて何ごとかが叙述され得るような衛星や衛星の集まりなどそこには全然ない。ところが、それによって「Venusmond 〔金星の衛星〕」という概念には一つの属性が付与される。何も包摂しないという属性が、だ。「der Wagen des Kaisers wird von vier Pferden gezogen 〔皇帝の車は四頭の馬によって牽かれる〕」と云うとき、私は「Pferd, das den Wagen des Kaisers zieht 〔皇帝の車を牽く馬〕」という概念に四という数を付与している。
ひとは反論するかも知れない。数の述定が概念について何かそうしたことを叙述するのだとすれば、例えば「ドイツ帝国の成員」というような概念は、そのメルクマールは変わらないにもかかわらず、年々変化する属性をもつことになるだろう、と。それに対してひとは、対象はその属性を変えるが、そのことはそれを同一であると認めることを妨げるものではない、と押し返すことができる。しかも、この場合、その理由はさらに詳しく述べられ得る。「ドイツ帝国の成員」という概念は時を可変的成分として含んでいる。つまり、数学的に表現させてもらうならば、それは時の関数なのだ。ひとは「a はドイツ帝国の成員である」に代えて「a はドイツ帝国に属している」と云うことができるが、これは今現在の時点に係っている。したがって、当の概念そのものに既に流動的なところがある訳だ。一方、「ベルリン時1883年初頭におけるドイツ帝国の成員」という概念には永久不変に同一の数が与えられる。
§47. 数の述定が我々の解釈には依存しない実際のことがらを表現するということを驚異と受けとるのは、概念を表象と同様の主観的なものと看做す者だけだ。しかし、そうした見解は誤っている。例えば、物体という概念を重さをもつものという概念の下位に置くなり、鯨という概念を哺乳動物という概念の下位に置くなりするとき、我々はそれによって客観的なことがらを主張している。ところが、もし概念が主観的だとしたら、或る概念が別の概念の下位に位置することもまた、それらの間の関係として、表象間の関係と同様、主観的なものだということになるだろう。たしかに、
「alle Wallfische sind Säugethiere 〔総ての鯨は哺乳動物である〕」
という命題は一見すると概念ではなく動物を扱っているように見えるが、しかし、いったいどの動物が話題になっているのかと問えば、ひとは何かを一つだけ示すことができない。たとえ一頭の鯨が目の前にいたとしても、この命題はその鯨についてはやはり何も主張してはいない。ひとは、そこから、目の前にいるその動物は哺乳動物である、とは推論し得ない。それは一頭の鯨である〔es ein Wallfisch ist〕という、件の命題がそれに関しては何の含みももたない命題を取り入れることなしには、だ。そもそも或る対象について語ることは、それをどうにかして表示するなり名指すなりすることなしには、不可能だ。「Wallfisch 〔鯨〕」という語は、だが、何の個体も名指してはいない。もし、ひとが、話題になっているのは、たしかにひとつの明確な対象ではないが、しかし、或る不定の対象なのだ、と応じるならば、私は云おう。「不定の対象」とは「概念」の別の表現でしかなく、しかも、不都合な、矛盾に充ちたものだ、と。たとえ件の命題がもっぱら個々の動物を観察することによってのみ正当化され得るにしても、そうした正当化は当の命題の内容については何も証しはしない。それは何を扱っているのか、という問に関しては、それが真であるか否かや、どんな根拠から我々はそれを真であると看做すのかはどうでもいいことだ。ところが、概念が客観的であれば、それについての叙述もまた実際のことがらを含み得る。§48. 同一のものにまちまちの数が与えられるようだという、上の幾つかの例に生じた見かけは、その際に対象が数の担い手として仮定された、ということで説明がつく。我々がその真の担い手、概念を正当な地位に就けるや否や、数はその勢力範囲において色と同様の排他性を顕わにする。
ここで、また、何故にひとが数をものからの抽象によって獲得しようとするに到るのかも判る。ひとが抽象によって獲るのは概念であり、そのときそこにひとは数を見出す。そうして、抽象は実際にしばしば数の判断の形成に先行する。その取り違えは、板壁と藁葺屋根を伴う木骨造りでもって洩れやすい煙出しをもつ家屋を建てることで、引火しやすさという概念が獲られる、と云い張る場合に同断だ。
概念の結集力は総合的統覚の統合力をはるかに超えている。統覚によってはドイツ帝国の成員達をひとつの全体へと束ねることなど可能ではないだろうが、しかし、ひとは彼等を「ドイツ帝国の成員」という概念のもとに置き、数えることができる。
ここで、また、数の広範な適用可能性も説明がつくことになる。実際、外的現象とともに内的現象について、空間的かつ時間的な現象とともに非空間的かつ非時間的な現象について、どうして同じことが叙述され得るのかは不可解だ。ところが、数の述定においてはそうしたことは全然おこなわれはしないのだ。数は、ただ、外的現象と内的現象が、空間的現象と時間的現象が、非空間的現象と非時間的現象がそのもとに置かれている概念に付与されるに過ぎない。
§49. 我々の見解への裏書の一つは、スピノザのもとに見出される。彼は次のように云う。「ものは単にその存在〔Existenz〕への顧慮によって一つのとか唯一のとかと云われるのであって、その本質〔Essenz〕への顧慮によってではない、と私は答えよう。我々がものどもを数のもとに表象するのは、もっぱらそれらが何らかの共通の尺度を宛がわれた後においてだからだ。例えば、一箇のセステルティウスと一箇のインペリアルを手に持っている者は、そのセステルティウスとインペリアルのそれぞれに硬貨もしくはコインという同じ名称を負わせることができなければ、箇数二〔die Zweizahl〕を思ったりはしないだろう。それができれば、彼は自分が二つの硬貨もしくはコインをもっていることを肯定し得る。彼はそのセステルティウスばかりでなくそのインペリアルをもまたコインという名称によって表示する訳だから。」ところが、「このことからして、ものが一つのとか唯一のとかと云われるのは、もっぱらそれに(既述のとおり)合致する何か別のものが表象された後においてであることは明らかだ」と続けるとき、そして、我々は神の本質について何の抽象的概念も形成し得ないのだから、本来の意味においては神を一つのとか唯一のとか云うことはできない、と云うとき、概念は多くの対象からの直接の抽象によってしか獲得され得ないと考える点において、彼は間違っている。ひとはメルクマールから概念へと達することもできるのであって、しかも、そのとき当の概念に帰属するものは何も無いということも可能なのだ。もし、そうしたことが生じないとしたら、ひとは決して存在なるものを否定し得ないだろうし、それとともに存在の肯定もまたその内容を失うことだろう。
§50. E. シュレーダーは、一つのものの頻出〔Häufigkeit〕が語られ得るのであれば、そうしたものの名称は常にクラス名〔ein Gattungsname〕、一般概念語〔ein allgemeines BegriffsWort〕(notio communis)でなければならない、ということを強調している。「つまり、ひとがひとつの対象を完全に――その総ての属性および関係とともに――捕捉するや否や、それは世界に唯一の身となり、もはや同類をもたないだろう。また、その対象の名称は固有名(nomen proprium)の性格を帯びるだろうし、当の対象は繰り返し出現するものとは考えられ得ない。このことは、だが、単に具体的な対象にばかりでなく、そもそもあらゆるものについて成り立つ。たとえそれの表象が抽象によって成ろうとも、ただその表象だけが当のものを完全に特定されたものとするに十分であるようなエレメントを包含している限りは、だ。 ・ ・ ・ 後者」(数えのオブジェクトとなること)「は何らかのものにおいて、そして、そのものがそれらによって自余の総てのものと区別されるようなそれに固有のメルクマールや関係の幾つかをひとが考慮の外におくなり度外視するなりする限りにおいて、初めて可能となる。それによって、そのとき初めて、ものの名称は多くのものに適用可能な概念となる。」
§51. この説明における真実は胡乱で紛らわしい云い回しで表現されているため、整理と吟味が必要だ。まず、一般概念語をものの名称と呼ぶのは不適切だ。それによって、まるで数がものの属性であるかのような見かけが生じる。一般概念語はまさに概念を表示するのだ。それは、ただ定冠詞もしくは指示代名詞を伴ってのみ、ものの固有名として通用するが、ただし、それとともに概念語として通用することをやめる。ものの名称は固有名だ。一つの対象が繰り返し出現するのではなく、多くの対象が一つの概念に帰属する。概念はただそれに帰属するものどもからの抽象によってのみ獲得される訳ではないということは、既にスピノザに反対して述べた。ここで私は、概念はただ一つのものしかそれに帰属しない――したがって、そのものは当の概念によって完全に特定されている――ことで概念であることをやめたりはしない、ということを付け加えよう。そうした概念(例えば、地球の衛星〔Begleiter der Erde〕)にまさに与えられるのが、2 や 3 と同じ意味において数である数 1 だ。概念の場合、それに何かが帰属するのか否か、そして何がそれに帰属するのかが常に問われる。固有名の場合、そうした問は無意味だ。言語が例えば「Mond 〔月〕」という固有名を概念語として〔衛星という意味で〕用い、その逆もあるということに、ひとは欺かれぬようにせねばならない。区別はそれでもやはり存続するのだ。不定冠詞を伴って、もしくは冠詞なしに複数形で使われるや否や、語は概念語となる。
§52. 数は概念に付与されるという見解へのもう一つの裏書は、ひとが zehn Mann 〔十人〕とか、vier Mark 〔四マルク〕、drei Fass 〔三ファス、三樽〕と云う場合のドイツ語の用語法〔何れにおいても名詞が単数形で単位として用いられている〕に見出され得る。単数形はここではものではなく概念が考えられていることを暗示しているのかも知れない。この表現法の長所は数 0 において殊に際立つ。こうしたケースを除けば、いかにも言語は概念ではなく対象に数を付与する。ひとは、「Gewicht der Ballen 〔梱どもの重さ〕」と云うのと同様に、「Zahl der Ballen 〔梱どもの数〕」と云うのだ。そうして、ひとは本当は概念について何かを叙述するつもりが、外見上は対象について語っている。こうした用語法はことを紛糾させる。「vier edle Rosse 〔四頭の純血種の乗用馬〕」という表現は、「edel 〔純血種の〕」が「Ross 〔乗用馬〕」を規定するのと同様に、「vier 〔四〕」が「edles Ross 〔純血種の乗用馬〕」をさらに規定するかのような見かけを呼び起こす。しかし、「edel」だけがそうしたメルクマールなのであって、「vier」という語によって、我々は概念について何ごとかを叙述している。
§53. 概念について叙述される属性とは、もちろん、当の概念を構成するメルクマールのことではない、と私は解する。メルクマールは当の概念に帰属するものの属性であって、その概念の、ではない。例えば、「直角〔rechtwinklig〕」は「直角三角形〔rechtwinkliges Dreieck〕」という概念の属性ではない。一方、直角正等辺三角形は存在しない〔es kein rechtwinkliges, geradliniges, gleichseitiges Dreieck gebe〕という命題は「直角正等辺三角形」という概念の一属性を述べており、この概念には箇数零〔die Nullzahl〕が付与される。
この点で存在なるもの〔die Existenz〕は数に似ている。存在の肯定は箇数零の否定に他ならないのだ。存在は概念の属性であるが故に、神の存在のオントロジカルな証明〔der ontologische Beweis von der Existenz Gottes〕はその目的を果たさない。存在と同じく唯一性もまた「神」という概念のメルクマールではない。唯一性がこの概念の定義に使われ得ないことは、ひとが家屋の建築に際してその丈夫さとか広さ、快適さを石材やモルタルや角材と諸共に用いることなどできないのと同断だ。しかしながら、何かが或る概念の属性であるということから、それが当の概念から、つまりはそのメルクマールから推論されることはあり得ないと結論することは、一般に許されない。場合によっては、それは可能だ。ひとが建築用石材の種類から建物の耐久性について間々結論をくだし得るのと同様に、だ。したがって、概念のメルクマールから唯一性なり存在なりが結論されることは決してあり得ない、とするのは云い過ぎというものだろう。ただ、それは、ひとが概念のメルクマールを当の概念に帰属する対象に属性として付与するようには、そう直接には、為され得ないのだ。
存在と唯一性がいつか概念のメルクマールとなり得る、ということを否認するのもまた誤りだろう。それらは、単に、ひとが言語に則してそれらをそのメルクマールと看做そうとするような、そうした概念の当のメルクマールなどではないまでだ。例えば、ただ一つの対象だけがそれに帰属するような概念の総てをひとつの概念のもとに集めれば、唯一性はこの概念のメルクマールだ。この概念には例えば「地球の衛星〔Erdmond〕」という概念が帰属することになるのであって、そう呼ばれる天体が、ではない。そうして、ひとは概念を高次の〔höhern〕、謂わば第二次の〔zweiter Ordnung〕概念に帰属させ得る。ただし、この関係を従属関係と混同してはならない。
§54. いまや単位を満足のいくように説明することが可能だろう。E. シュレーダーは先の教科書の7ページで「そうしたクラス名あるいは概念は既述の方法で形成された数の呼称と呼ばれ、その単位の本質を成す」と云っている。
実際、或る概念を、それに与えられる箇数〔Anzahl〕との係りで、単位と呼ぶのは、極めて適切なことではなかろうか。そのとき、それは周囲から分離されていて分割不能である、という単位についての叙述に我々は意味を見出すことができる。数を付与される当の概念は一般にそれに帰属するものを明確な仕方で劃すからだ。「Buchstabe des Wortes Zahl 〔Zahl という語を成す文字〕」という概念は Z を a から劃し、a を h から劃し、等々。「Silbe des Wortes Zahl 〔Zahl という語のもつシラブル〕」という概念は当の語をひとつの全体として、そして、そのどんな部分ももはや「Silbe des Wortes Zahl」という概念には帰属しないという意味で、分割不能なものとして、際立たせる。総ての概念がそのようである訳ではない。我々は、例えば、赤という概念に帰属するものを様々な仕方で分割することができる。分割された部分が当の概念に帰属しなくなることなしに、だ。そうした概念にはどんな有限数も与えられることはない。そこで、単位の被劃定性と分割不能性についての命題というものが、次のように述べられ得る。
それに帰属するものを明確に劃し、どんな恣意的な分割も許さないような概念だけが、有限の箇数に係る単位であり得る。
分割不能性はここで特別の意義〔Bedeutung〕をもっていることが判るだろう。
いまや、どうして相等性は単位の区別可能性によって邪魔され得ないのか、という問に答えるのは簡単だ。「単位〔Einheit〕」という語はここで二重の意味で用いられている。単位どもは、上で説明されたこの語の意義において、等しい。「Jupiter hat vier Monde 〔木星は四つの衛星をもつ〕」という命題においては、単位は「Jupitersmond 〔木星の衛星〕」だ。第一衛星と同様、第二衛星も、第三衛星も、第四衛星も、この概念に帰属する。したがって、ひとは次のように云うことができる。第一衛星が関聯づけられる単位は第二衛星が関聯づけられる単位に等しい云々。その点で、我々は相等性を手にしている。一方、単位どもの区別可能性を主張するとき、ひとはそれによって数えられるものどもの区別可能性を考えているのだ。
☆ ☆ ☆
フレーゲは、この『算術の基礎』(1884年)に先立つ『概念記法』(1879年)において、ファンクションとアーギュメントという道具立てでもって文を分析する方法を呈示し、いわゆる量化理論を展開することで、論理学を新たな段階へと齎したのだった。そこで定式化された論理のエッセンスは、今日では「古典論理」と呼ばれ、スタンダードとなっている訳だが、その古典論理においては、あらゆるものはかくかくである――今日一般的な論理記号を使って書けば、∀x(x はかくかくである)――ということと、かくかくでないものは存在しない――¬∃x¬(x はかくかくである)――ということは同等であり、また、あらゆるものがかくかくでない訳ではない――¬∀x¬(x はかくかくである)――ということと、かくかくであるものが存在する――∃x(x はかくかくである)――ということも同等だ。したがって、古典論理の体系を考える場合、「あらゆる」に関わる普遍量化か「存在」に関わる存在量化かのどちらか一方を採れば、他方は無しに済ますことが可能であり、実際、フレーゲの概念記法体系には、いわゆる存在量化子に相当するものは具わっていない。その点からすれば、「存在の肯定は箇数零の否定に他ならない」という彼の言葉は、「かくかくであるものが存在する」を、かくかくであるものの箇数は零でない、ということによってあらためて定義しているものと解釈され得る。
ところで、フレーゲが唯一性について云っていることを存在について当てはめてみれば、次のようになる: それに帰属する対象の箇数が零でない概念の総てをひとつの概念のもとに集めれば、存在はこの概念のメルクマールである。この云い回しは、「存在は概念の属性である」という云いぐさともども、いかにも胡乱というものだが、それはさておき、このアイディアは、1891年の『関数と概念』を経て、1893年の『算術の基本法則』第一巻において、その体系に即して具体化されることとなる。そこでは、今日一般的な記号法で書けば、「∀xΦx」という形をした、いわゆる自由変数を含まない表現は、「Φ」によって表わされる一変数の関数――対象を真理値(真か偽)に対応づける関数――を真理値に対応づける或る第二水準の関数(Funktion zweiter Stufe)の値を表わすものとされ、また、「¬∀x¬Φx」というような表現は、「Φ」によって表わされる一変数関数と「¬」によって表わされている真理値を反転する関数との合成関数 ¬Φ についての件の第二水準の関数の値(真か偽)が関数 ¬ によって反転された値を表わすものとされる。(「∀xΦx」によって表わされる真理値は、あらゆる対象について関数 Φ の値が真であれば、真であり、そうでなければ、偽だ。また、「¬∀x¬Φx」によって表わされる真理値は、あらゆる対象について関数 ¬Φ の値が真(つまり Φ の値が偽)であれば、偽であり、そうでなければ、真だ。)そこで、「Φ」という説明の便宜上の不定の表現を今度は空位を示す目印と看做せば、「∀xΦx」および「¬∀x¬Φx」はそれぞれに或る第二水準の関数を表わしているものと解釈され得る。その意味での関数 ¬∀x¬Φx は、それに帰属する対象の箇数が零でない概念の総てを、そしてそれらだけを包摂する概念に相当する、と云えるだろう。実際、フレーゲは第一水準の一変数関数を「第一水準の概念」、第二水準の一変数関数を「第二水準の概念」と呼んでいるのであり、上で彼が「概念」と云っているのも、あるいは、そうした関数に類するもののことなのかも知れない。
ついでに、「「存在する」は二階の述語である」というテーゼについて。この胡乱な云いぐさは、上のような、『算術の基本法則』の体系に即して呈示されたアイディアを、量化理論的語法で補強された自然言語に適用することから捻り出された、と云えるだろう。それを飯田の『言語哲学大全 I 』の第一章に則って見ておこう。
そこでは、「述語」という語は次のような意味で用いられている。
「いくつかの空所をもつ以外は文と同じであり、それらの空所を名前で填めれば文となる形式を「述語」と呼ぶことにしよう。」(ここで「名前」と云われているのは何らかの個体を指す表現のことだと解していいだろう。また、空所はそのような名前によってのみ充填され得るものとしなければならない。それから、「いくつかの空所」とは、単に複数の空所のことではなく、いくつかのグループに分けられた複数の空所のことであり、同じグループの空所は同じ名前によって一斉に充填されるのだと考えるべきだろう。ちなみに、このグループ分けされた空所をもつ形式というアイディアは『概念記法』のファンクションとアーギュメントという道具立てがイントロダクション用に簡便化されたものだと云える。)
例えば――飯田がこうした例を用いている訳ではないが――「ルート2 は分数では表現され得ない数である」という文から「ルート2」という一つの数を指す表現を除外すれば、「・・・は分数では表現され得ない数である」という述語が得られる。(このように、文からその一部を、単なる部分としてではなく、空所をもつ形式として切り出すところが味噌だ。)ところで、「分数では表現され得ない数が存在する」という文は、「ある x について、x は分数では表現され得ない数である」と書き換えられ得る。(ここに量化理論的語法が登場している訳だ。)そこで、そこから件の述語を除外した「ある x について、x ・・・」という形式を考えれば、その空所は、空所を一つもつ(つまり空所のグループを一つだけもつ)あらゆる述語によって、充填され得るものと看做され得る。(この「ある x について、x ・・・」という形式は、それに帰属する対象の箇数が零でない概念の総てを、そしてそれらだけを包摂する概念を表わす、と云えるだろう。)そうした意味で、「ある x について、x ・・・」を「二階の述語」と呼ぶことができるだろうと飯田は云う。そして、さらに、この二階の述語が「存在を表現するものである」と看做され得ることから、ひとつの「教訓」が引き出され得る、と彼は云うのだ。
「すなわち、「存在する」は、述語ではあるが、「ねたむ」や「カラスである」のような、個体について言われる一階の述語ではなく、こうした一階の述語について言われる二階の述語なのである。」(冒頭に引いた註はここに付されている。)
「存在は概念の属性である」と同様、「「存在する」は二階の述語である」という云いぐさもまた、こうしたコンテクストから切り離されれば、混乱の種でしかないだろう。要注意。
さて、カント、フレーゲとくれば、次はクワインの段だろうが、さしあたり俺にはそれに関して書くべきことはない。
2011-09-03 13:16
コメント(0)
続 sein はリアルな述語ではない [ノート]
ずいぶん間があいてしまった。が、あいかわらず、これといって書きたいこともない。で、ここは「sein はリアルな述語ではない」の補足をしてお茶を濁すことにしたい。
ハイデガーはカントの「reales Prädikat」についてどんなことを云っているのか? その『現象学の根本問題』を覘いてみたところ、彼は、ただ、カントにおいては(bei Kant)、「Realität」は現実性や実在性といった意味をもってはおらず、ヴォルフ門下のバウムガルテン――そのテクストをもとにカントは講義をすることが多かったのだとか――を介してスコラ哲学に従うかたちで用いられている、と云っているだけで、別に当時のテクストを博捜してカントの場合だけでなく一般にそうだったということを示してみせている訳ではないのだった。
ともあれ、ハイデガーは、バウムガルテンを引きつつ、次のように云っている。
「バウムガルテンは ens、存在者一般を劃定する節において云っている: Quod aut ponitur esse A, aut ponitur non esse A, determinatur〔A であるとして立てられるか、または A ではないとして立てられるものは限定される〕〔原註: Baumgarten, Metaphysica (1743), §34〕、「A であるとして措定されるか、または非‐A であるとして措定されるものは規定される〔was gesetzt wird als A seiend oder gesetzt wird als nicht‐A seiend, wird bestimmt〕。」そのように措定された A は determinatio だ。カントはものの何〔Was eines Dinges〕に、res に加わる規定について語っている。規定、determinatio は res を規定するもの、リアルな述語〔reales Prädikat〕を意味する。そこで、バウムガルテンは云う: Quae determinando ponuntur in aliquo, (notae et praedicata) sunt determinationes〔限定するかたちで何かについて立てられるもの(メルクマールおよび述語)は限定である〕〔原註: 前掲書、§36〕、「何らかのものについて規定様態において措定されるもの(メルクマールおよび述語)は規定である〔was in der Weise der Bestimmens in irgendeinem Ding gesetzt wird (Merkmale und Prädikate), sind Bestimmungen〕。」したがって、カントが存在〔Dasein〕は規定ではないという表現を用いるとき、この表現は少しも恣意的ではなく、術語的に限定されている。determinatio だ。そうした規定、determinationes は二様であり得る。Altera positiva, et affirmativa, quae si vere sit, est realitas, altera negativa, quae si vere sit, est negatio〔ポジティヴでアファーマティヴな方は、それが正しく立てられているのであれば、リアリティであり、ネガティヴな方は、それが正しく立てられているのであれば、ネゲーションである〕〔原註: 同上〕、「ポジティヴに措定的に、あるいはアファーマティヴに、肯定的に措定する規定項は、その肯定が正当ならば、リアリティであり、他方の否定的な規定は、それが正当ならば、ネゲーションである〔Das Bestimmende, was positiv setzend bzw. affirmativ, bejahend setzt, ist, wenn diese Bejahung rechtmäßig ist, eine Realität, die andere verneinende Bestimmung ist, wenn sie rechtmäßig ist, eine Negation〕。」リアリティは、だから、正当な、当の事物〔Sache〕、res そのものに、その概念に適った、事象内容を含む〔sachhaltige〕、リアルな規定、determinatio だ。リアリティの反対がネゲーションだ。
カントは批判以前の時期ばかりでなく、『純粋理性批判』においても、やはりこうした概念規定に遵っている。例えば、彼はものの概念〔Begriff eines Dinges〕について語り、「リアルなもの〔eines Realen〕」を括弧に括っているが〔原註: 『純粋理性批判』、B286〔つまり第二版、p.286〕〕、これは現実的なもの〔eines Wirklichen〕のことではない。リアリティは肯定的に措定された、事象内容を含む述語を意味するのだから。どんな述語も根本においてはリアルな述語だ。すると、存在〔Sein〕はリアルな述語ではないというカントのテーゼは、存在はそもそも何らかのものの述語などではない、ということを実は述べていることになる。カントはカテゴリー表――そこにはリアリティの他に存在〔Dasein〕、エグジステンスも属す訳だが――を判断表から導出している。判断は、形式的に見れば、主語と述語の結合だ。どんな結合あるいは統合も、その都度、可能なユニティ〔Einheit〕を考慮して為される。それぞれの統合に際して、たとえ主題的に捉えられてはいなくとも、或るユニティのアイディアが心に浮かんでいる。判断において、つまり統合において心に浮かぶユニティの様々な可能な形式、判断的結合のための可能な考慮ないしは考慮内容、それがカテゴリーだ。・・・リアリティも、そしてエグジステンス、存在〔Dasein〕も、そうしたユニティの形式のひとつだ。我々はリアリティと存在という両カテゴリーの差異を、それらがまったく相異なるカテゴリーのクラスに属すことから、はっきりと見てとることができる。・・・リアリティは質のカテゴリーのひとつだ。質でもって、カントは、或る述語が或る主語に付与されるかの否か、それについて肯定されるのか、それとも反措定〔entgegengesetzt〕されるのか、つまり否定されるのかを示す断定のキャラクター〔Charakter der Urteilssetzung〕を表わしている。リアリティは、だから、肯定的な、アファーマティヴな、措定的な、ポジティヴな判断だ。これはまさにバウムガルテンがリアリティに下している定義だ。・・・」(Heidegger, Die Gruntprobleme der phänomenologie, Vittorio Klostermann, S. 46-48)
このあたりを踏まえてのことだろう。木田元は、『ハイデガーの思想』(岩波新書)において、「カントの『純粋理性批判』のように無数の人によって読み継がれ研究しつくされてきた重要な著作の、それも核心部に長いあいだ明確な誤解があったのを、ハイデガーはいかにも快刀乱麻を断つといった感じで訂正してみせるのである」と書いている。リアリティはカテゴリーのひとつとして『純粋理性批判』の核心に位置する概念なのにながいこと実在性という意味に誤解されていたと彼は云うのだ。が、それは荒唐無稽というものだろう。件の概念がスコラ哲学に由来するからには、話は単に、やっぱり哲学書を読むにはそれなりのたしなみが必要なのだ、ということに尽きるだろう。ハイデガーは講壇哲学の常識をいかにも教師然として説いてみせたまでなのではなかろうか。
ついでに書いておけば、バウムガルテンの定義では、或る概念がリアリティであるかネゲーションであるかは個々のケース次第であり、対象に相対的であることになる――例えば、素数という概念は数 7 についてポジティヴに立てられればリアリティであり、6 についてネガティヴに立てられればネゲーションだ――が、カントにおいては、リアリティとネゲーションは概念そのものをその意味内容に即して区別するもののようだ。例えば、無なるものを論じつつ、カントは次のように書いている。
「リアリティは何かであり、ネゲーションは無である、つまり、蔭や冷たさのような、何らかの対象の欠如に関わる概念である(nihil privativum〔欠如的無〕)〔Realität ist Etwas, Negation ist Nichts, nämlich, ein Begriff von dem Mangel eines Gegenstandes, wie der Schatten, die Kälte, (nihil privativum)〕。」(『純粋理性批判』、B347)
いまひとつ要領を得ない文だが、蔭は光の欠如を、冷たさは熱の欠如を意味するのであり、ネゲーションとは、そのような、何かの欠如を意味する概念のことだ、という訳なのだろう。なお、ハイデガーは何故か「non esse A」に「nicht‐A seiend」を当てているが、カントにおいては、A ではないという判断と非‐A であるという判断は否定判断と無限判断として区別される。それに対応して、質として括られるカテゴリーには、リアリティとネゲーションに加えてもうひとつリミテーションなるものがあって、話はさらにややこしくなるのだが、ここらでもうやめにしておこう。
ハイデガーはカントの「reales Prädikat」についてどんなことを云っているのか? その『現象学の根本問題』を覘いてみたところ、彼は、ただ、カントにおいては(bei Kant)、「Realität」は現実性や実在性といった意味をもってはおらず、ヴォルフ門下のバウムガルテン――そのテクストをもとにカントは講義をすることが多かったのだとか――を介してスコラ哲学に従うかたちで用いられている、と云っているだけで、別に当時のテクストを博捜してカントの場合だけでなく一般にそうだったということを示してみせている訳ではないのだった。
ともあれ、ハイデガーは、バウムガルテンを引きつつ、次のように云っている。
「バウムガルテンは ens、存在者一般を劃定する節において云っている: Quod aut ponitur esse A, aut ponitur non esse A, determinatur〔A であるとして立てられるか、または A ではないとして立てられるものは限定される〕〔原註: Baumgarten, Metaphysica (1743), §34〕、「A であるとして措定されるか、または非‐A であるとして措定されるものは規定される〔was gesetzt wird als A seiend oder gesetzt wird als nicht‐A seiend, wird bestimmt〕。」そのように措定された A は determinatio だ。カントはものの何〔Was eines Dinges〕に、res に加わる規定について語っている。規定、determinatio は res を規定するもの、リアルな述語〔reales Prädikat〕を意味する。そこで、バウムガルテンは云う: Quae determinando ponuntur in aliquo, (notae et praedicata) sunt determinationes〔限定するかたちで何かについて立てられるもの(メルクマールおよび述語)は限定である〕〔原註: 前掲書、§36〕、「何らかのものについて規定様態において措定されるもの(メルクマールおよび述語)は規定である〔was in der Weise der Bestimmens in irgendeinem Ding gesetzt wird (Merkmale und Prädikate), sind Bestimmungen〕。」したがって、カントが存在〔Dasein〕は規定ではないという表現を用いるとき、この表現は少しも恣意的ではなく、術語的に限定されている。determinatio だ。そうした規定、determinationes は二様であり得る。Altera positiva, et affirmativa, quae si vere sit, est realitas, altera negativa, quae si vere sit, est negatio〔ポジティヴでアファーマティヴな方は、それが正しく立てられているのであれば、リアリティであり、ネガティヴな方は、それが正しく立てられているのであれば、ネゲーションである〕〔原註: 同上〕、「ポジティヴに措定的に、あるいはアファーマティヴに、肯定的に措定する規定項は、その肯定が正当ならば、リアリティであり、他方の否定的な規定は、それが正当ならば、ネゲーションである〔Das Bestimmende, was positiv setzend bzw. affirmativ, bejahend setzt, ist, wenn diese Bejahung rechtmäßig ist, eine Realität, die andere verneinende Bestimmung ist, wenn sie rechtmäßig ist, eine Negation〕。」リアリティは、だから、正当な、当の事物〔Sache〕、res そのものに、その概念に適った、事象内容を含む〔sachhaltige〕、リアルな規定、determinatio だ。リアリティの反対がネゲーションだ。
カントは批判以前の時期ばかりでなく、『純粋理性批判』においても、やはりこうした概念規定に遵っている。例えば、彼はものの概念〔Begriff eines Dinges〕について語り、「リアルなもの〔eines Realen〕」を括弧に括っているが〔原註: 『純粋理性批判』、B286〔つまり第二版、p.286〕〕、これは現実的なもの〔eines Wirklichen〕のことではない。リアリティは肯定的に措定された、事象内容を含む述語を意味するのだから。どんな述語も根本においてはリアルな述語だ。すると、存在〔Sein〕はリアルな述語ではないというカントのテーゼは、存在はそもそも何らかのものの述語などではない、ということを実は述べていることになる。カントはカテゴリー表――そこにはリアリティの他に存在〔Dasein〕、エグジステンスも属す訳だが――を判断表から導出している。判断は、形式的に見れば、主語と述語の結合だ。どんな結合あるいは統合も、その都度、可能なユニティ〔Einheit〕を考慮して為される。それぞれの統合に際して、たとえ主題的に捉えられてはいなくとも、或るユニティのアイディアが心に浮かんでいる。判断において、つまり統合において心に浮かぶユニティの様々な可能な形式、判断的結合のための可能な考慮ないしは考慮内容、それがカテゴリーだ。・・・リアリティも、そしてエグジステンス、存在〔Dasein〕も、そうしたユニティの形式のひとつだ。我々はリアリティと存在という両カテゴリーの差異を、それらがまったく相異なるカテゴリーのクラスに属すことから、はっきりと見てとることができる。・・・リアリティは質のカテゴリーのひとつだ。質でもって、カントは、或る述語が或る主語に付与されるかの否か、それについて肯定されるのか、それとも反措定〔entgegengesetzt〕されるのか、つまり否定されるのかを示す断定のキャラクター〔Charakter der Urteilssetzung〕を表わしている。リアリティは、だから、肯定的な、アファーマティヴな、措定的な、ポジティヴな判断だ。これはまさにバウムガルテンがリアリティに下している定義だ。・・・」(Heidegger, Die Gruntprobleme der phänomenologie, Vittorio Klostermann, S. 46-48)
このあたりを踏まえてのことだろう。木田元は、『ハイデガーの思想』(岩波新書)において、「カントの『純粋理性批判』のように無数の人によって読み継がれ研究しつくされてきた重要な著作の、それも核心部に長いあいだ明確な誤解があったのを、ハイデガーはいかにも快刀乱麻を断つといった感じで訂正してみせるのである」と書いている。リアリティはカテゴリーのひとつとして『純粋理性批判』の核心に位置する概念なのにながいこと実在性という意味に誤解されていたと彼は云うのだ。が、それは荒唐無稽というものだろう。件の概念がスコラ哲学に由来するからには、話は単に、やっぱり哲学書を読むにはそれなりのたしなみが必要なのだ、ということに尽きるだろう。ハイデガーは講壇哲学の常識をいかにも教師然として説いてみせたまでなのではなかろうか。
ついでに書いておけば、バウムガルテンの定義では、或る概念がリアリティであるかネゲーションであるかは個々のケース次第であり、対象に相対的であることになる――例えば、素数という概念は数 7 についてポジティヴに立てられればリアリティであり、6 についてネガティヴに立てられればネゲーションだ――が、カントにおいては、リアリティとネゲーションは概念そのものをその意味内容に即して区別するもののようだ。例えば、無なるものを論じつつ、カントは次のように書いている。
「リアリティは何かであり、ネゲーションは無である、つまり、蔭や冷たさのような、何らかの対象の欠如に関わる概念である(nihil privativum〔欠如的無〕)〔Realität ist Etwas, Negation ist Nichts, nämlich, ein Begriff von dem Mangel eines Gegenstandes, wie der Schatten, die Kälte, (nihil privativum)〕。」(『純粋理性批判』、B347)
いまひとつ要領を得ない文だが、蔭は光の欠如を、冷たさは熱の欠如を意味するのであり、ネゲーションとは、そのような、何かの欠如を意味する概念のことだ、という訳なのだろう。なお、ハイデガーは何故か「non esse A」に「nicht‐A seiend」を当てているが、カントにおいては、A ではないという判断と非‐A であるという判断は否定判断と無限判断として区別される。それに対応して、質として括られるカテゴリーには、リアリティとネゲーションに加えてもうひとつリミテーションなるものがあって、話はさらにややこしくなるのだが、ここらでもうやめにしておこう。
2012-05-13 21:35
コメント(0)
続続 sein はリアルな述語ではない [ノート]
ハイデガーはカントが「ものの概念〔Begriff eines Dinges〕について語り、「リアルなもの〔eines Realen〕」を括弧に括っている」と云っていた。その云い換えが現われる文脈は次の通り。
「Da sie aber gleichwohl doch immer synthetisch sind, so sind sie es nur subjektiv, d. i. sie fügen zu dem Begriffe eines Dinges, (Realen,) von dem sie sonst nichts sagen, die Erkenntniskraft hinzu...」(Kritik der reinen Vernunft, B286)
これを「(Realen,) 」を無視して訳出してみれば次の通り。
「とはいえ、それら〔可能、現実、必然といういわゆる様相についての原則〕はやはりつねに総合的である訳で、してみれば、それらはただサブジェクティヴに総合的であるに過ぎない、つまり、ものの概念に認識力を付け加えるばかりで、当の概念については何も語らない・・・」
ハイデガーは形容詞「real」が名詞化されたかたちの「Realen」を「Dinges」の云い換えと解している訳だが、コンマに注意してみれば、むしろそれは「realen Begriffe」の略なのではないかと思われる。(ちなみに、第一版では括弧に括られているのは「realen」だ。)つまり、様相の原則はリアルな概念に認識力を付け加えるだけだ、とカントは云っているのではないか。
それはさておき、前回に引いたあたりのあとで、ハイデガーは今度は次のように云っている。
「カントのオブジェクティヴ・リアリティという概念は、リアリティという概念とは区別されねばならず、現実性と同義だ。オブジェクティヴ・リアリティは、それによって考えられている対象に、それのオブジェクトに実現している当の事物性、つまり、現実的なものとして、現に存在するものとして経験されている存在者に顕現している事物性を意味する〔Objektive Realität heißt diejenige Sachheit, die an dem in ihr gedachten Gegenstand, ihrem Objekt, sich erfüllt, d. h. diejenige Sachheit, die sich an erfahrenen Seienden als wirklichem, als daseiendem, ausweist〕。」(Die Gruntprobleme der phänomenologie, S. 49)
これは、だが、的を逸している。カントは、絶対必然的存在者という概念のオブジェクティヴ・リアリティは理性が当の概念を必要としているということによって証明されるようなものではない、と云っていた。また、sein はリアルな述語ではないというテーゼが出て来る少し前の脚註には次のようにある。
「概念は、自己矛盾しなければ、きまって可能〔möglich〕だ。これは可能性なるものの論理的メルクマールであり、それによって当の概念の対象は nihil negativum〔ネガティヴな無〕と区別される。ただし、それにもかかわらず、それは空虚な概念であり得る。当の概念がそれによって生み出される総合のオブジェクティヴ・リアリティが別に明らかにされない場合には、だ。それは、しかし、上に示された通り、可能な経験の原理につねにもとづくのであって、分析原則(矛盾律)にではない。これは概念の可能性(論理的可能性)からものの可能性(リアルな可能性)を直ちに推論してはならないという戒めだ。」(B624)
今度は「総合のオブジェクティヴ・リアリティ」と来たが、ともあれ、「概念のオブジェクティヴ・リアリティ」は当の概念のオブジェクトの可能性を意味するものと思われる。理性が絶対必然的存在者という概念を必要としているからといって、それだけでは、そのオブジェクトの現実性はおろか、可能性すら保証され得ない、とカントは云っている訳だろう。(なお、はじめに引いたくだりからも窺えるように、カントはいわゆる事象様相(ものの性質としての様相)を認めないから、様相述語もまたリアルな述語ではないことになる。カントにおいては可能なオブジェクトは可能世界に存在するようなものではない。)
ところで、「Realität」という語は、『純粋理性批判』の本文においては、カテゴリー表(B106)に登場する以前に、まずは次のような文脈に現われる。
「我々の論究は、故に、外的に対象として我々へと現われ得るすべてのものを顧慮するに、空間のリアリティ(つまりオブジェクティヴな有効性)〔die Realität (d. i. objektive Gültigkeit)〕を示しているが、それと同時に、ものが理性によってそれ自体において、つまり我々の感性の性質をかえりみることなく検討される場合を顧慮するに、空間のアイディアリティ〔die Idealität〕をも示している。我々は、したがって、(あらゆる可能な外的経験を顧慮するに)空間のエンピリカル・リアリティ〔die empirische Realität〕を主張する。いかにも、我々は空間のトランセンデンタル・アイディアリティ〔die transzendentale Idealität〕を、つまり、我々があらゆる経験の可能性の条件を落とし、空間をものそのものの根底に横たわる何かと考えるや否や、それは無となることを主張するのではあるが。」(B44)
これに対応して、時間については、次のように述べられている。
「我々の主張は、故に、やがて我々の感覚へと齎されるであろうあらゆる対象を顧慮するに、時間のエンピリカル・リアリティ(つまりオブジェクティヴな有効性)を示している。・・・一方、我々は時間に対して、我々の感覚的直観のフォルムをかえりみることなく只管ものに条件ないしは属性としてまとわりつくような、絶対的リアリティへの一切の権利を認めない。」(B52)
そして、そうした時間のトランセンデンタル・アイディアリティとの関連で、感覚内容の述語について、
「ひとは、この場合、そうした述語が内属する現象そのものについて、それがオブジェクティヴ・リアリティをもつことを前提としている」(B53)
と云われている。また、時間についてはさらに次のように述べられている。
「時間は、たしかに、現実的な何か〔etwas Wirkliches〕、さらに云えば、内的直観の現実的フォルムである。それは、したがって、内的経験を顧慮するに、サブジェクティヴ・リアリティをもつ、つまり私は現実に時間の表象および時間における自らの規定をもつ。」(B53-54)
そして、少しあとのほうで、単なる見かけと現象の違いについて論じつつ、カントは次のように云っている。
「もし、それら〔空間と時間〕の表象フォルムにオブジェクティヴ・リアリティを付与するならば、すべてが単なる見かけに一転されることをひとは免れ得ない。」(B70)
こうした文脈に現われる「Realität」はカテゴリー表に登場するものとは別の意味で用いられていると考えるべきだろう。
憶えば、「リアルな述語」は「論理的述語」と対で登場していた。そして、上に見られる通り、「リアルな可能性」もまた「論理的可能性」と対で現われている。論理的とは、この場合、形ばかり、名ばかりということだとも云えるから、「real」は、それに対して、内容のある、実のあるというようなことを意味するものと考えられる。(なお、ハイデガーはリアルな述語に関して「sachhaltig」という表現を用いていた。それを俺はどうも意味がつかめないままに「事象内容を含む」などと訳して体裁をつくろっておいたのだが、この形容詞はものとかことがらとかを意味する名詞「Sache」に何々を含むというような意味の接尾辞「haltig」が附いたかたちなのだから、ざっくばらんに「実のある」とでも訳すべきだったかも知れない。)ラテン語の形容詞「realis」はものにかかわるというような意味をもつらしいが、どうやら、カントの「real」は、一般に、その名残をとどめつつ、内容のある、実のある、実質的というような意味で用いられているようだ。とすれば、上のような文脈に現われる「Realität」は実のあること、実質性というような意味をもつと解すことができるだろう。例えば、空間のリアリティとは空間という表象の実質性のことであり、では、その実質とは何かと云えば、それは外的対象にかかわる有効性のことである。概念のオブジェクティヴ・リアリティとはそのオブジェクトにかかわる実質性のことであり、では、その実質とは何かと云えば、そのオブジェクトの可能性のことである。そんなふうに考えてみれば、いかにも腑に落ちるではないか。
ところで、こうした「Realität」の二通りの意味は抽象名詞「Reale」を介して繋がるかに見えて、擦れ違う。まず、カントが「Reale」の名で呼んでいるのは現象において感覚内容に対応するマター(Materie)のことらしい。上の意味での形容詞「real」を抽象名詞化すれば、それは内容とか実質というような意味になるだろうから、この呼び名は一見もっともらしいものではある。そして、そうした現象のマターに対応する概念こそ「Realität」の名で呼ばれるもの、つまり――カントはこのような云い回しを敢えて避けているようだが――リアリティというカテゴリーに属す概念らしいのだ。(上に見られる感覚内容述語の現象への内属というのはこのあたりのことを云っているのだろう。)だが、このカテゴリーとしてのリアリティはカントの認識論における理論的概念である一方、もうひとつのリアリティは表象一般にかかわるものであり、謂わばメタ概念だ。同じく「Realität」によって表わされながらも、これらは論理的ステータスを異にしているのだった。(この論理的差異を見逃したために、ハイデガーは的外れな註釈をするはめになったと云えるだろう。)
さて、そんな訳で、たしかに、『純粋理性批判』においては、「real」は現実的というようなことを意味しないし、「Realität」は現実性を意味しない。そして、これらの語は、きっと、当時のドイツ語圏の学問の世界の慣用に倣うかたちで用いられているのだろう。一方、ヒュームやディドロらのテクストをちょっと覘いてみた限りでは、英語の「real」もフランス語の「réel」も現実的というような意味で、そして、「reality」と「réalité」は現実性というような意味で、それぞれ用いられているようだ。カントの同時代の英語やフランス語では、これらは既に今日におけるのとほぼ同様の一連の意味をもっていたのかも知れない。
それにしても、ラテン語の「res」に由来するこれらの語の意味の変容と拡張はいったいどういういきさつで生じたのか? それはいわゆる普遍論争にかかわりがあるのではないかという気がするのだが、スコラ哲学には近づきたくないので、この話題はもうこれで終えるとしよう。
「Da sie aber gleichwohl doch immer synthetisch sind, so sind sie es nur subjektiv, d. i. sie fügen zu dem Begriffe eines Dinges, (Realen,) von dem sie sonst nichts sagen, die Erkenntniskraft hinzu...」(Kritik der reinen Vernunft, B286)
これを「(Realen,) 」を無視して訳出してみれば次の通り。
「とはいえ、それら〔可能、現実、必然といういわゆる様相についての原則〕はやはりつねに総合的である訳で、してみれば、それらはただサブジェクティヴに総合的であるに過ぎない、つまり、ものの概念に認識力を付け加えるばかりで、当の概念については何も語らない・・・」
ハイデガーは形容詞「real」が名詞化されたかたちの「Realen」を「Dinges」の云い換えと解している訳だが、コンマに注意してみれば、むしろそれは「realen Begriffe」の略なのではないかと思われる。(ちなみに、第一版では括弧に括られているのは「realen」だ。)つまり、様相の原則はリアルな概念に認識力を付け加えるだけだ、とカントは云っているのではないか。
それはさておき、前回に引いたあたりのあとで、ハイデガーは今度は次のように云っている。
「カントのオブジェクティヴ・リアリティという概念は、リアリティという概念とは区別されねばならず、現実性と同義だ。オブジェクティヴ・リアリティは、それによって考えられている対象に、それのオブジェクトに実現している当の事物性、つまり、現実的なものとして、現に存在するものとして経験されている存在者に顕現している事物性を意味する〔Objektive Realität heißt diejenige Sachheit, die an dem in ihr gedachten Gegenstand, ihrem Objekt, sich erfüllt, d. h. diejenige Sachheit, die sich an erfahrenen Seienden als wirklichem, als daseiendem, ausweist〕。」(Die Gruntprobleme der phänomenologie, S. 49)
これは、だが、的を逸している。カントは、絶対必然的存在者という概念のオブジェクティヴ・リアリティは理性が当の概念を必要としているということによって証明されるようなものではない、と云っていた。また、sein はリアルな述語ではないというテーゼが出て来る少し前の脚註には次のようにある。
「概念は、自己矛盾しなければ、きまって可能〔möglich〕だ。これは可能性なるものの論理的メルクマールであり、それによって当の概念の対象は nihil negativum〔ネガティヴな無〕と区別される。ただし、それにもかかわらず、それは空虚な概念であり得る。当の概念がそれによって生み出される総合のオブジェクティヴ・リアリティが別に明らかにされない場合には、だ。それは、しかし、上に示された通り、可能な経験の原理につねにもとづくのであって、分析原則(矛盾律)にではない。これは概念の可能性(論理的可能性)からものの可能性(リアルな可能性)を直ちに推論してはならないという戒めだ。」(B624)
今度は「総合のオブジェクティヴ・リアリティ」と来たが、ともあれ、「概念のオブジェクティヴ・リアリティ」は当の概念のオブジェクトの可能性を意味するものと思われる。理性が絶対必然的存在者という概念を必要としているからといって、それだけでは、そのオブジェクトの現実性はおろか、可能性すら保証され得ない、とカントは云っている訳だろう。(なお、はじめに引いたくだりからも窺えるように、カントはいわゆる事象様相(ものの性質としての様相)を認めないから、様相述語もまたリアルな述語ではないことになる。カントにおいては可能なオブジェクトは可能世界に存在するようなものではない。)
ところで、「Realität」という語は、『純粋理性批判』の本文においては、カテゴリー表(B106)に登場する以前に、まずは次のような文脈に現われる。
「我々の論究は、故に、外的に対象として我々へと現われ得るすべてのものを顧慮するに、空間のリアリティ(つまりオブジェクティヴな有効性)〔die Realität (d. i. objektive Gültigkeit)〕を示しているが、それと同時に、ものが理性によってそれ自体において、つまり我々の感性の性質をかえりみることなく検討される場合を顧慮するに、空間のアイディアリティ〔die Idealität〕をも示している。我々は、したがって、(あらゆる可能な外的経験を顧慮するに)空間のエンピリカル・リアリティ〔die empirische Realität〕を主張する。いかにも、我々は空間のトランセンデンタル・アイディアリティ〔die transzendentale Idealität〕を、つまり、我々があらゆる経験の可能性の条件を落とし、空間をものそのものの根底に横たわる何かと考えるや否や、それは無となることを主張するのではあるが。」(B44)
これに対応して、時間については、次のように述べられている。
「我々の主張は、故に、やがて我々の感覚へと齎されるであろうあらゆる対象を顧慮するに、時間のエンピリカル・リアリティ(つまりオブジェクティヴな有効性)を示している。・・・一方、我々は時間に対して、我々の感覚的直観のフォルムをかえりみることなく只管ものに条件ないしは属性としてまとわりつくような、絶対的リアリティへの一切の権利を認めない。」(B52)
そして、そうした時間のトランセンデンタル・アイディアリティとの関連で、感覚内容の述語について、
「ひとは、この場合、そうした述語が内属する現象そのものについて、それがオブジェクティヴ・リアリティをもつことを前提としている」(B53)
と云われている。また、時間についてはさらに次のように述べられている。
「時間は、たしかに、現実的な何か〔etwas Wirkliches〕、さらに云えば、内的直観の現実的フォルムである。それは、したがって、内的経験を顧慮するに、サブジェクティヴ・リアリティをもつ、つまり私は現実に時間の表象および時間における自らの規定をもつ。」(B53-54)
そして、少しあとのほうで、単なる見かけと現象の違いについて論じつつ、カントは次のように云っている。
「もし、それら〔空間と時間〕の表象フォルムにオブジェクティヴ・リアリティを付与するならば、すべてが単なる見かけに一転されることをひとは免れ得ない。」(B70)
こうした文脈に現われる「Realität」はカテゴリー表に登場するものとは別の意味で用いられていると考えるべきだろう。
憶えば、「リアルな述語」は「論理的述語」と対で登場していた。そして、上に見られる通り、「リアルな可能性」もまた「論理的可能性」と対で現われている。論理的とは、この場合、形ばかり、名ばかりということだとも云えるから、「real」は、それに対して、内容のある、実のあるというようなことを意味するものと考えられる。(なお、ハイデガーはリアルな述語に関して「sachhaltig」という表現を用いていた。それを俺はどうも意味がつかめないままに「事象内容を含む」などと訳して体裁をつくろっておいたのだが、この形容詞はものとかことがらとかを意味する名詞「Sache」に何々を含むというような意味の接尾辞「haltig」が附いたかたちなのだから、ざっくばらんに「実のある」とでも訳すべきだったかも知れない。)ラテン語の形容詞「realis」はものにかかわるというような意味をもつらしいが、どうやら、カントの「real」は、一般に、その名残をとどめつつ、内容のある、実のある、実質的というような意味で用いられているようだ。とすれば、上のような文脈に現われる「Realität」は実のあること、実質性というような意味をもつと解すことができるだろう。例えば、空間のリアリティとは空間という表象の実質性のことであり、では、その実質とは何かと云えば、それは外的対象にかかわる有効性のことである。概念のオブジェクティヴ・リアリティとはそのオブジェクトにかかわる実質性のことであり、では、その実質とは何かと云えば、そのオブジェクトの可能性のことである。そんなふうに考えてみれば、いかにも腑に落ちるではないか。
ところで、こうした「Realität」の二通りの意味は抽象名詞「Reale」を介して繋がるかに見えて、擦れ違う。まず、カントが「Reale」の名で呼んでいるのは現象において感覚内容に対応するマター(Materie)のことらしい。上の意味での形容詞「real」を抽象名詞化すれば、それは内容とか実質というような意味になるだろうから、この呼び名は一見もっともらしいものではある。そして、そうした現象のマターに対応する概念こそ「Realität」の名で呼ばれるもの、つまり――カントはこのような云い回しを敢えて避けているようだが――リアリティというカテゴリーに属す概念らしいのだ。(上に見られる感覚内容述語の現象への内属というのはこのあたりのことを云っているのだろう。)だが、このカテゴリーとしてのリアリティはカントの認識論における理論的概念である一方、もうひとつのリアリティは表象一般にかかわるものであり、謂わばメタ概念だ。同じく「Realität」によって表わされながらも、これらは論理的ステータスを異にしているのだった。(この論理的差異を見逃したために、ハイデガーは的外れな註釈をするはめになったと云えるだろう。)
さて、そんな訳で、たしかに、『純粋理性批判』においては、「real」は現実的というようなことを意味しないし、「Realität」は現実性を意味しない。そして、これらの語は、きっと、当時のドイツ語圏の学問の世界の慣用に倣うかたちで用いられているのだろう。一方、ヒュームやディドロらのテクストをちょっと覘いてみた限りでは、英語の「real」もフランス語の「réel」も現実的というような意味で、そして、「reality」と「réalité」は現実性というような意味で、それぞれ用いられているようだ。カントの同時代の英語やフランス語では、これらは既に今日におけるのとほぼ同様の一連の意味をもっていたのかも知れない。
それにしても、ラテン語の「res」に由来するこれらの語の意味の変容と拡張はいったいどういういきさつで生じたのか? それはいわゆる普遍論争にかかわりがあるのではないかという気がするのだが、スコラ哲学には近づきたくないので、この話題はもうこれで終えるとしよう。
2013-01-19 12:17
コメント(0)
追って追って追って以下同様 [ノート]
ふとしたきっかけでゼノンのパラドクスのことが気になりだした。近頃の数学史ではそれはどう位置づけられているのか、というのがはじまりだったのだが、そのうちすぐに、いわゆるアキレスとカメのパラドクスの定式化へと興味がそれていって、そもそもアリストテレスはそれをどういうかたちで伝えているのか、という訳で、Hardie & Gaye による英訳を覘いてみることとあいなった。
それは、だが、次のような要約でしかないのだった。
「The second is the so-called 'Achilles', and it amounts to this, that in a race the quickest runner can never overtake the slowest, since the pursuer must first reach the point whence the pursued started, so that the slower must always hold a lead.」(Physics VI.9)
これでは簡略に過ぎて論証の体をなしていないではないか。問題は
「追うものはまずは追われるものがスタートした地点に達しなければならず、したがって遅い方がつねにリードを保つことになる」
というくだりだ。そこで、これをまっとうな推論に仕上げるにはどうしたらいいか、と考えてみて、アリストテレスになりかわって――モダンな理論に頼ることなく――それを為そうとする限り、どうにも仕様がなさそうだと気づいた。そして、そこにこのパラドクスのからくりがあるらしい、と。
まず、コンテクストをある程度はっきりさせることからはじめよう。走者は例によってアキレスとカメで、レースは百メートルの直線コースでおこなわれるものとする。ただし、カメはゴールまで十メートルの地点からスタートするものとしよう。もちろん、アキレスにはしっかり百メートルを走ってもらう訳だが、それでも彼は易々とカメを追い抜いてゴールに入ることだろう。途中で休んだりしない限りは。そこで、両者は合図とともに一斉にスタートし、ゴールめがけてひたすら駆け続けるものとする。以上を前提として、問題のくだりを次のように敷衍してみよう。
「まず、カメのスタート地点を第一地点と呼ぶことにすれば、アキレスが第一地点に達するまでの間に、カメもまた、アキレスに較べれば僅かにせよ、先へ進む。そこで、アキレスが第一地点に達する丁度その時にカメが達する地点を第二地点と呼ぶことにすれば、アキレスがさらに進んで第二地点に達するまでの間に、カメもまた、アキレスに較べれば僅かにせよ、さらに先へ進む。そこで、アキレスが第二地点に達する丁度その時にカメが達する地点を第三地点と呼ぶことにすれば、アキレスがさらに進んで第三地点に達するまでの間に、カメもまた、アキレスに較べれば僅かにせよ、さらに先へ進む。以下同様。したがって、それらの地点の何れについても、アキレスは、カメにリードを許したまま、そこに達することになる。」
我々は、上のようにしてコース上の地点をひとつづつ次々に規定していく作業には、その続行可能性において、原理的に際限が無いことを確信している。だが、そのことをこうして「以下同様」に託してみても、それだけでは第三地点に続くどんな地点も規定されはしない。「以下同様」やそれに代わるフレーズ、クローズは、このレースの記述――あくまで仮想的なものな訳だが――の一部なのではなく、記述に係るものであり、それによって当の記述がさらに進捗することはない。記述内容が増すことはない。そうすると、だが、「それらの地点の何れについても」は何を意味するのか? 古代ギリシャには、この穴を埋める手立ては無かっただろう。
ところで、この穴あきの推論は、次のような記述と、えてして混同されがちだ。
「まず、カメのスタート地点を第一地点と呼ぶことにすれば、アキレスが第一地点に達するまでの間に、カメもまた、アキレスに較べれば僅かにせよ、先へ進む。そこで、アキレスが第一地点に達する丁度その時にカメが達する地点を第二地点と呼ぶことにすれば、アキレスがさらに進んで第二地点に達するまでの間に、カメもまた、アキレスに較べれば僅かにせよ、さらに先へ進む。そこで、アキレスが第二地点に達する丁度その時にカメが達する地点を第三地点と呼ぶことにすれば、アキレスがさらに進んで第三地点に達するまでの間に、カメもまた、アキレスに較べれば僅かにせよ、さらに先へ進む。以上のようにしてコース上の地点を逐次規定していく作業は際限無く続行可能であり、そして、それが続けられる限りにおいて、各段階で規定されるのは、アキレスがカメにリードを許したままそこへと達することになる地点である。」
件の穴あき推論が、レースの記述にそれに係る表現が割り込むかたちをしているのに対して、こちらは、謂わば二階建ての記述であり、レースの記述にはじまり、それに係る記述で終わっている。それらが交錯する処に、このパラドクスは巣くっていると云える。そのからくりはこうだ: まずレースの断片的記述を呈示し、それが際限無く延長可能であることを覚らせ、そして、その記述にまつわる際限無さを、アキレスの走りにおけるものと取り違えさせる。
なお、今日の我々は、古典力学とスタンダードな数学に依拠して、上のような第一、第二、第三地点にはじまる無限列を、謂わば一挙に規定することができる。(アキレスとカメの運動をそれぞれに表わす関数を考え、それらを用いて、いわゆる再帰的定義にうったえればいい。)それによって問題のくだりを定式化しなおすとすれば、どういうことになるか? それを考えるのはまたの機会としよう。
それは、だが、次のような要約でしかないのだった。
「The second is the so-called 'Achilles', and it amounts to this, that in a race the quickest runner can never overtake the slowest, since the pursuer must first reach the point whence the pursued started, so that the slower must always hold a lead.」(Physics VI.9)
これでは簡略に過ぎて論証の体をなしていないではないか。問題は
「追うものはまずは追われるものがスタートした地点に達しなければならず、したがって遅い方がつねにリードを保つことになる」
というくだりだ。そこで、これをまっとうな推論に仕上げるにはどうしたらいいか、と考えてみて、アリストテレスになりかわって――モダンな理論に頼ることなく――それを為そうとする限り、どうにも仕様がなさそうだと気づいた。そして、そこにこのパラドクスのからくりがあるらしい、と。
まず、コンテクストをある程度はっきりさせることからはじめよう。走者は例によってアキレスとカメで、レースは百メートルの直線コースでおこなわれるものとする。ただし、カメはゴールまで十メートルの地点からスタートするものとしよう。もちろん、アキレスにはしっかり百メートルを走ってもらう訳だが、それでも彼は易々とカメを追い抜いてゴールに入ることだろう。途中で休んだりしない限りは。そこで、両者は合図とともに一斉にスタートし、ゴールめがけてひたすら駆け続けるものとする。以上を前提として、問題のくだりを次のように敷衍してみよう。
「まず、カメのスタート地点を第一地点と呼ぶことにすれば、アキレスが第一地点に達するまでの間に、カメもまた、アキレスに較べれば僅かにせよ、先へ進む。そこで、アキレスが第一地点に達する丁度その時にカメが達する地点を第二地点と呼ぶことにすれば、アキレスがさらに進んで第二地点に達するまでの間に、カメもまた、アキレスに較べれば僅かにせよ、さらに先へ進む。そこで、アキレスが第二地点に達する丁度その時にカメが達する地点を第三地点と呼ぶことにすれば、アキレスがさらに進んで第三地点に達するまでの間に、カメもまた、アキレスに較べれば僅かにせよ、さらに先へ進む。以下同様。したがって、それらの地点の何れについても、アキレスは、カメにリードを許したまま、そこに達することになる。」
我々は、上のようにしてコース上の地点をひとつづつ次々に規定していく作業には、その続行可能性において、原理的に際限が無いことを確信している。だが、そのことをこうして「以下同様」に託してみても、それだけでは第三地点に続くどんな地点も規定されはしない。「以下同様」やそれに代わるフレーズ、クローズは、このレースの記述――あくまで仮想的なものな訳だが――の一部なのではなく、記述に係るものであり、それによって当の記述がさらに進捗することはない。記述内容が増すことはない。そうすると、だが、「それらの地点の何れについても」は何を意味するのか? 古代ギリシャには、この穴を埋める手立ては無かっただろう。
ところで、この穴あきの推論は、次のような記述と、えてして混同されがちだ。
「まず、カメのスタート地点を第一地点と呼ぶことにすれば、アキレスが第一地点に達するまでの間に、カメもまた、アキレスに較べれば僅かにせよ、先へ進む。そこで、アキレスが第一地点に達する丁度その時にカメが達する地点を第二地点と呼ぶことにすれば、アキレスがさらに進んで第二地点に達するまでの間に、カメもまた、アキレスに較べれば僅かにせよ、さらに先へ進む。そこで、アキレスが第二地点に達する丁度その時にカメが達する地点を第三地点と呼ぶことにすれば、アキレスがさらに進んで第三地点に達するまでの間に、カメもまた、アキレスに較べれば僅かにせよ、さらに先へ進む。以上のようにしてコース上の地点を逐次規定していく作業は際限無く続行可能であり、そして、それが続けられる限りにおいて、各段階で規定されるのは、アキレスがカメにリードを許したままそこへと達することになる地点である。」
件の穴あき推論が、レースの記述にそれに係る表現が割り込むかたちをしているのに対して、こちらは、謂わば二階建ての記述であり、レースの記述にはじまり、それに係る記述で終わっている。それらが交錯する処に、このパラドクスは巣くっていると云える。そのからくりはこうだ: まずレースの断片的記述を呈示し、それが際限無く延長可能であることを覚らせ、そして、その記述にまつわる際限無さを、アキレスの走りにおけるものと取り違えさせる。
なお、今日の我々は、古典力学とスタンダードな数学に依拠して、上のような第一、第二、第三地点にはじまる無限列を、謂わば一挙に規定することができる。(アキレスとカメの運動をそれぞれに表わす関数を考え、それらを用いて、いわゆる再帰的定義にうったえればいい。)それによって問題のくだりを定式化しなおすとすれば、どういうことになるか? それを考えるのはまたの機会としよう。
2013-06-23 11:22
コメント(0)
続追って追って追って以下同様 [ノート]
前回の最後に触れた地点列について、ちょっと解説しておこう。
まず、アキレスとカメのレースは前と同じ設定でおこなわれるものとして、直交座標系 O-XYZ を原点 O がアキレスのスタート地点に一致し X-軸がゴール向きにコースに添うようにとるとしよう。単位はメートル。時間の単位は秒としておく。これでコース上の地点を X-軸上の点によって表わすことができ、また、アキレスの百メートルの走りは時間を表わす数直線上の或る閉区間から X-、Y-、Z-軸それぞれへの関数の組によって表わされる訳だが、いまの場合、X-軸への関数だけを考えれば済むことになる。カメの十メートルの走りについても同様だ。そこで、F をアキレスについてのそうした関数、G をカメについてのそれとしよう。ただし、どちらの値域も X-軸上の区間 [0, 100] とする。ふたたび前と同じく、アキレスとカメは合図とともに一斉にスタートし淀みなく前進してゴールに入るものとすれば、F も G も狭義単調増加と考えられる。ここでさらに数学的に必要なのは連続性だけなのだが、一応どちらも二階導関数をもつとしておく。加えて、アキレスの方がカメより先にゴールに入るものとする。
そこで、仮定から F は逆関数 invF をもつことになるから、それと G を用いて、正整数全体から X-軸上の区間 [0, 100] への写像 B を、B(1)=90、B(n+1)=G(invF(B(n))) として再帰的に定義すれば、次が成り立つ: どんな正整数 n についてもそれに応じて時点 t がひとつだけ在って、B(n)=F(t)、B(n+1)=G(t)、B(n)<B(n+1)<100。
これで問題の地点列 {B(n) | n は正整数} が得られたことになる。(以下ではこれを「{B(n)}」と略記する。)
写像 B に関しては次のようなことが云える。
「どんな正整数 n についても、アキレスの x-座標が B(n) である時点におけるカメの x-座標は B(n+1) であり、B(n)<B(n+1)。したがって、どんな正整数 n についても次が成り立つ: 区間 [0, B(n)] に属すどんな点 a についても、アキレスの x-座標が a である時点におけるカメの x-座標は a より大きい。」
これを次のようにパラフレーズしてみよう。
「地点列 {B(n)} に属す何れの地点についても、アキレスがそこに達する丁度その時に、カメは、列 {B(n)} におけるその地点の直後の項である地点へと、アキレスに先んじて達する。したがって、{B(n)} に属す何れの地点についても、アキレスは、カメにリードを許したまま、そこに達することになる。」
ここで、アキレスが {B(n)} に属す地点に達することをその運動におけるひとつのプロセスとかイヴェントとかと考えることができるとすれば、{B(n)} は狭義単調増加の無限列なのだから、アキレスがカメを追い抜いたあかつきには無限のプロセスなり何なりが完了していることになるが如何に? という訳で、ようやくパラドクスめいた雰囲気がでてきたところで、この話題はもう終えることにして、最後に、写像の再帰的定義について付け加えておこう。
その裏には次のような定理(いわゆる再帰定理あるいは帰納定理)がある:
S を何らかの集合、a をその要素、f を S から S への写像とすれば、次のような正整数全体から S への写像 g がひとつだけ存在する: g(1)=a、どんな正整数 n について も g(n+1)=f(g(n))。
証明は省くが、g は或る条件を充たすあらゆる集合の共通部分として特定される。(構成されるのではない。そもそも集合は対象を集めることによって構成されるようなものではない。)このユニークに存在する g を、g(1)=a、g(n+1)=f(g(n)) という条件を示して指定するのが再帰的定義である、という構図になっている訳で、上の写像 B がこれに当てはまるのは明らかだろう。古典数学(いわゆる古典論理にもとづく今日のスタンダードな数学)は謂わば超越的なかまえをしていて、その点がどうも胡散臭く感じられないでもないものの、ともあれ、再帰的定義が無限のステップを一挙に完了するマジカルな手続きなどでないことはたしかだ。
まず、アキレスとカメのレースは前と同じ設定でおこなわれるものとして、直交座標系 O-XYZ を原点 O がアキレスのスタート地点に一致し X-軸がゴール向きにコースに添うようにとるとしよう。単位はメートル。時間の単位は秒としておく。これでコース上の地点を X-軸上の点によって表わすことができ、また、アキレスの百メートルの走りは時間を表わす数直線上の或る閉区間から X-、Y-、Z-軸それぞれへの関数の組によって表わされる訳だが、いまの場合、X-軸への関数だけを考えれば済むことになる。カメの十メートルの走りについても同様だ。そこで、F をアキレスについてのそうした関数、G をカメについてのそれとしよう。ただし、どちらの値域も X-軸上の区間 [0, 100] とする。ふたたび前と同じく、アキレスとカメは合図とともに一斉にスタートし淀みなく前進してゴールに入るものとすれば、F も G も狭義単調増加と考えられる。ここでさらに数学的に必要なのは連続性だけなのだが、一応どちらも二階導関数をもつとしておく。加えて、アキレスの方がカメより先にゴールに入るものとする。
そこで、仮定から F は逆関数 invF をもつことになるから、それと G を用いて、正整数全体から X-軸上の区間 [0, 100] への写像 B を、B(1)=90、B(n+1)=G(invF(B(n))) として再帰的に定義すれば、次が成り立つ: どんな正整数 n についてもそれに応じて時点 t がひとつだけ在って、B(n)=F(t)、B(n+1)=G(t)、B(n)<B(n+1)<100。
これで問題の地点列 {B(n) | n は正整数} が得られたことになる。(以下ではこれを「{B(n)}」と略記する。)
写像 B に関しては次のようなことが云える。
「どんな正整数 n についても、アキレスの x-座標が B(n) である時点におけるカメの x-座標は B(n+1) であり、B(n)<B(n+1)。したがって、どんな正整数 n についても次が成り立つ: 区間 [0, B(n)] に属すどんな点 a についても、アキレスの x-座標が a である時点におけるカメの x-座標は a より大きい。」
これを次のようにパラフレーズしてみよう。
「地点列 {B(n)} に属す何れの地点についても、アキレスがそこに達する丁度その時に、カメは、列 {B(n)} におけるその地点の直後の項である地点へと、アキレスに先んじて達する。したがって、{B(n)} に属す何れの地点についても、アキレスは、カメにリードを許したまま、そこに達することになる。」
ここで、アキレスが {B(n)} に属す地点に達することをその運動におけるひとつのプロセスとかイヴェントとかと考えることができるとすれば、{B(n)} は狭義単調増加の無限列なのだから、アキレスがカメを追い抜いたあかつきには無限のプロセスなり何なりが完了していることになるが如何に? という訳で、ようやくパラドクスめいた雰囲気がでてきたところで、この話題はもう終えることにして、最後に、写像の再帰的定義について付け加えておこう。
その裏には次のような定理(いわゆる再帰定理あるいは帰納定理)がある:
S を何らかの集合、a をその要素、f を S から S への写像とすれば、次のような正整数全体から S への写像 g がひとつだけ存在する: g(1)=a、どんな正整数 n について も g(n+1)=f(g(n))。
証明は省くが、g は或る条件を充たすあらゆる集合の共通部分として特定される。(構成されるのではない。そもそも集合は対象を集めることによって構成されるようなものではない。)このユニークに存在する g を、g(1)=a、g(n+1)=f(g(n)) という条件を示して指定するのが再帰的定義である、という構図になっている訳で、上の写像 B がこれに当てはまるのは明らかだろう。古典数学(いわゆる古典論理にもとづく今日のスタンダードな数学)は謂わば超越的なかまえをしていて、その点がどうも胡散臭く感じられないでもないものの、ともあれ、再帰的定義が無限のステップを一挙に完了するマジカルな手続きなどでないことはたしかだ。
2013-11-03 14:33
コメント(0)
アキレスがカメに云ったこと [ノート]
前にアキレスとカメのパラドクスについてちょっと書いたが、その後ルイス・キャロルのアキレスとカメのことが気になりだして、初めてその What the Tortoise Said to Achilles (1895) に眼を通してみたところ、これがどうもいまひとつ腑に落ちないのだった。ドジソンではなくキャロルの名で書かれているだけあって、何やらワンダーランドめいているとでも云おうか。そこで、以下にその核心部を余計なおしゃべりを適宜省略しつつ引いて、少しばかりコメントを付しておこうと思う――あいかわらず他に書きたいことも無いので。
ACHILLES had overtaken the Tortoise, and had seated himself comfortably on its back.
"So you've got to the end of our race-course?" said the Tortoise. "Even though it does consist of an infinite series of distances? I thought some wiseacre or other had proved that the thing couldn't be done?"
"It can be done," said Achilles. "It has been done! Solvitur ambulando. You see the distances were constantly diminishing; and so—"
"But if they had been constantly increasing?" the Tortoise interrupted...
"... Well now, would you like to hear of a race-course, that most people fancy they can get to the end of in two or three steps, while it really consists of an infinite number of distances, each one longer than the previous one?"
"Very much indeed!" said the Grecian warrior, as he drew from his helmet ... an enormous note-book and a pencil. "Proceed! And speak slowly, please! Short-hand isn't invented yet!"
... "Well, now, let's take a little bit of the argument in that First Proposition [of Euclid]—just two steps, and the conclusion drawn from them. Kindly enter them in your note-book. And in order to refer to them conveniently, let's call them A, B, and Z:—
(A) Things that are equal to the same are equal to each other.
(B) The two sides of this Triangle are things that are equal to the same.
(Z) The two sides of this Triangle are equal to each other.
Readers of Euclid will grant, I suppose, that Z follows logically from A and B, so that any one who accepts A and B as true, must accept Z as true?"
"Undoubtedly! The youngest child in a High School ... will grant that."
"And if some reader had not yet accepted A and B as true, he might still accept the sequence as a valid one, I suppose?"
"No doubt such a reader might exist. He might say 'I accept as true the Hypothetical Proposition that, if A and B be true, Z must be true; but, I don't accept A and B as true.' Such a reader would do wisely in abandoning Euclid, and taking to football."
"And might there not also be some reader who would say 'I accept A and B as true, but I don't accept the Hypothetical'?"
"Certainly there might. He, also, had better take to football."
"And neither of these readers," the Tortoise continued, "is as yet under any logical necessity to accept Z as true?"
"Quite so," Achilles assented.
"Well, now, I want you to consider me as a reader of the second kind, and to force me, logically, to accept Z as true."
... "I'm to force you to accept Z, am I?" Achilles said musingly. "And your present position is that you accept A and B, but you don't accept the Hypothetical—"
"Let's call it C," said the Tortoise.
"—but you don't accept
(C) If A and B are true, Z must be true."
"That is my present position," said the Tortoise.
"Then I must ask you to accept C."
"I'll do so," said the Tortoise, "as soon as you've entered it in that note-book of yours. What else have you got in it?"
"Only a few memoranda," said Achilles, nervously fluttering the leaves: "a few memoranda of—of the battles in which I have distinguished myself!"
"Plenty of blank leaves, I see!" the Tortoise cheerily remarked. "We shall need them all!" (Achilles shuddered.) "Now write as I dictate:—
(A) Things that are equal to the same are equal to each other.
(B) The two sides of this Triangle are things that are equal to the same.
(C) If A and B are true, Z must be true.
(Z) The two sides of this Triangle are equal to each other."
"You should call it D, not Z," said Achilles. "It comes next to the other three. If you accept A and B and C, you must accept Z."
"And why must I?"
"Because it follows logically from them. If A and B and C are true, Z must be true. You don't dispute that, I imagine?"
"If A and B and C are true, Z must be true," the Tortoise thoughtfully repeated. "That's another Hypothetical, isn't it? And, if I failed to see its truth, I might accept A and B and C, and still not accept Z, mightn't I?”
"You might," the candid hero admitted; "though such obtuseness would certainly be phenomenal. Still, the event is possible. So I must ask you to grant one more Hypothetical."
"Very good. I'm quite willing to grant it, as soon as you've written it down..."...
まず注意しておきたいのは、これが論理学と数学がモダナイズされようとしていた時代のさなかに書かれたもので、いわゆる伝統的論理学とユークリッド原論の初歩の知識を前提としている、ということだ。(問題の推論は、形はやや異なるものの、実際にユークリッド原論第一巻の第一命題の証明中に見出せる。その命題は、所与の直線をもとに等辺三角形を構成すること、というもので、その証明は下の図のように円の性質に依拠している。(the two sides of this Triangle というのは ΑΓ と ΒΓ のことだ。)なお、ユークリッドにおいては線はもっぱら有限だ。)仮令ユークリッドの読者の誰かが A と B を真だと認めなかったとしても、それでもやはり彼は A と B から Z に到るシークエンスを妥当なものと認めることだろう、というカメの言葉に同意したあとで、アキレスがさらに、そのような者は「私は、A と B が真ならば Z は真であるほかない、という仮言命題を真だと認めるが、A と B を真だとは認めない」と云うことだろう、とわざわざ付け加えるのは、それがこのような場合に論理学の心得があることを示すためにひとが口にすべき紋切型というやつだから、という訳なのだろう。アキレスは、どうやら、「do not accept as true」を、理解できなくて真だと受け容れることができない、というほどの意味に解して、論理学の初歩を一応は知っているもののユークリッド入門に躓いた少年を想い描いているようだ。(ユークリッドの初歩を理解できないような少年でも問題の推論は妥当だとちゃんと判断できる、という想定はさほど不自然なものではないかも知れない。件の推論はいわゆる定言三段論法の第一格 AAA(通称 Barbara)という妥当な推論の典型中の典型に収まるものと看做し得るからだ。なお、定言三段論法の妥当性は、前提が何れも真ならば結論は真であるほかない、ということによって規定される。)ここまではまあいいとしよう。ところが、その紋切型を待ってましたとばかりに、カメが、それなら「私は A と B を真だと認めるが、件の仮言を認めない」と云う者だっているのではないか、とたたみかけ、アキレスがそれをあっさりと肯定してしまうところから話がおかしくなる。
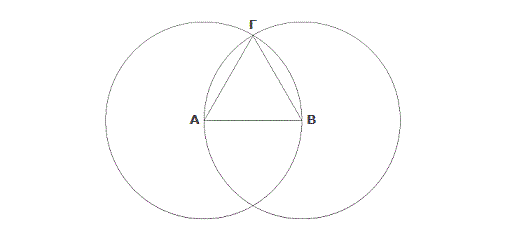 ここでまず気になるのはそのような者は何を根拠に B を真だと認めるのか――A はユークリッドの第一公理だからそのまま真だと認めていいにしても――ということだ。B を云うには直線 ΑΓ と ΒΓ がそれぞれに ΑΒ に等しいことを示せば足りる訳だが、第一命題の証明には、簡略に、点 Α は左側の円の中心だから ΑΓ は ΑΒ に等しい、というような意味のことしか述べられていないので、それを敷衍してみれば、以下のようになるだろう。
ここでまず気になるのはそのような者は何を根拠に B を真だと認めるのか――A はユークリッドの第一公理だからそのまま真だと認めていいにしても――ということだ。B を云うには直線 ΑΓ と ΒΓ がそれぞれに ΑΒ に等しいことを示せば足りる訳だが、第一命題の証明には、簡略に、点 Α は左側の円の中心だから ΑΓ は ΑΒ に等しい、というような意味のことしか述べられていないので、それを敷衍してみれば、以下のようになるだろう。
まず、Heath による英訳から円とその中心の定義(第十五および第十六定義)を引けば次の通り:
15. A circle is a plane figure contained by one line such that all the straight lines falling upon it from one point among those lying within the figure are equal to one another;
16. And the point is called the centre of the circle.
ここから次のような命題が得られるだろう:
All the straight lines falling upon the circumscribing line of a circle from its centre are equal to one another.
一方、ΑΒ と ΑΓ については次が得られる:
ΑΒ and ΑΓ are straight lines that are falling upon the circumscribing line of a circle from its centre.
これらから次が帰結する:
ΑΒ and ΑΓ are equal to one another.
これは、だが、問題の推論と同型の三段論法だ。件の仮言命題を認めないという彼奴はこれに係わる同様の仮言を認めるのか認めないのか? アキレスはそう問うてみてもよかったかも知れない。
もっとも、俺が解せないのはこの点ではない。問題はこれからだ。アキレスは「私を第二の類の読者だと想定して、Z を真だと論理的に認めざるを得ないようにしてみてほしい」というカメの誘いにこれまたあっさりと乗って、カメの仮想上の立場を確認したうえで「そこで俺はお前に C を認めて貰わねばならない訳だ」とこれまたわざわざ付け加え、そしてこれまたそれを待ってましたとばかりにカメが返した「そうしよう。それをそのノートに書込んでくれさえすれば」という言葉にまたまたあっさりと応じてしまう。そもそもカメが成り代わっている人物は C を認めないはずだったのに、しかもアキレスとカメはそれを確認したばかりなのに、いったいこれはどうしたことなのか? アキレスはカメと一丸となってもっぱら C の類の仮言命題を再帰的に弾き出し続けるマシーンと化すことをひたすら望んでいるかの如くだ。やはり彼らは追いかけっこするうちにいつのまにかワンダーランドに迷い込んでしまったものに相違ない。
ところで、この理不尽な展開を補うべく、アキレスは C を受け容れさせることでカメの論理学的無知を埋めようとし、カメはそれを甘受する、といった脚色がなされたりすることがあるが、もちろん、そうしたストーリーは他にも色々と考えてみることができる。そして、それにつれて例えば次のような一聯の問いが浮かびあがって来る: A と B が真ならば Z は真であるほかないという命題を真だと認めることと A と B が真ならば Z は真であるほかないということを認めることは同じではないだろうが、ならばそれらはどう違うのか? そもそも A と B が真ならば Z は真であるほかないという命題を真だと認めるとはどういうことなのか? ひとがそれをそう認めているということのクリテリオンは何なのか? A と B が真ならば Z は真であるほかないということを認めるとはどういうことなのか? ひとがそれを認めているということのクリテリオンは何なのか?・・・ ひょっとして、キャロルはこうした効果を狙って、敢えて無造作な語り方を選んだのでもあろうか。ちなみに、カメは最後の方で「what a lot of instruction this colloquy of ours will provide for the Logicians of the Nineteenth Century」と云っているが、どうやらこの対話篇には、様々なインストラクションやインスピレーションを提供すべく、あれこれ仕掛けが施されているらしい。やはりキャロルの名義は伊達ではないようだ。(ついでに、このあとの展開を書いておけば、透明だった語り手が見物していた第三者として顕われて、彼は銀行に急用があったのでその場を離れねばならず、数箇月後にふたたび通りかかってみると、一千一箇目の仮言命題をアキレスが書き終えたところだった、ということになっている。だが、そう語っているのは最初の語り手なのか、それとも第二の透明な語り手なのか?)
それはそうと、カメが成り代わっている人物は A と B を真だと認めるが C を認めない者としかされていないのだから、彼に代わって云い得ることは実は何も無い。可能なのは、ただ、何か妥当な推論が呈示されるたびに、それに係わる C と同様の仮言命題を彼はやはり認めないかも知れない、と指摘することだけだろう。そこで、彼が演繹的推論を悉く受けつけない推論盲とでも呼び得るような者だったとしたら、と考えてみたくなるのは俺ばかりではあるまい。ヴィトゲンシュタインは『哲学探求』第二部で、例えばウサギ‐アヒルの図を兎として見たり家鴨として見たりすることができないような者を想定し、アスペクト盲と呼んで「概念的診察」をおこなっているが、それに倣って、推論盲の概念的診察を試みればどういうことになるか。とっくに誰かがやっているだろうか?
最後に問題の推論を量化理論に拠ってパラフレーズしておく。
(A') ∀x∀y(∃z((x is equal to z)∧(y is equal to z))⊃(x and y are equal to each other))
これから普遍例化によって次が得られる:
(A'') ∃z((ΑΓ is equal to z)∧(ΒΓ is equal to z))⊃(ΑΓ and ΒΓ are equal to each other)
これと
(B') ∃z((ΑΓ is equal to z)∧(ΒΓ is equal to z))
から、モドゥス・ポネンスによって次が得られる:
(Z') (ΑΓ and ΒΓ are equal to each other)
A' が真ならば当然 A'' も真だが、さらに B' が真だとすれば Z' が真であるほかないことは A'' の形から一目瞭然だ。もちろん、C を認めない彼奴はこれもまた認めないかも知れないが。
ACHILLES had overtaken the Tortoise, and had seated himself comfortably on its back.
"So you've got to the end of our race-course?" said the Tortoise. "Even though it does consist of an infinite series of distances? I thought some wiseacre or other had proved that the thing couldn't be done?"
"It can be done," said Achilles. "It has been done! Solvitur ambulando. You see the distances were constantly diminishing; and so—"
"But if they had been constantly increasing?" the Tortoise interrupted...
"... Well now, would you like to hear of a race-course, that most people fancy they can get to the end of in two or three steps, while it really consists of an infinite number of distances, each one longer than the previous one?"
"Very much indeed!" said the Grecian warrior, as he drew from his helmet ... an enormous note-book and a pencil. "Proceed! And speak slowly, please! Short-hand isn't invented yet!"
... "Well, now, let's take a little bit of the argument in that First Proposition [of Euclid]—just two steps, and the conclusion drawn from them. Kindly enter them in your note-book. And in order to refer to them conveniently, let's call them A, B, and Z:—
(A) Things that are equal to the same are equal to each other.
(B) The two sides of this Triangle are things that are equal to the same.
(Z) The two sides of this Triangle are equal to each other.
Readers of Euclid will grant, I suppose, that Z follows logically from A and B, so that any one who accepts A and B as true, must accept Z as true?"
"Undoubtedly! The youngest child in a High School ... will grant that."
"And if some reader had not yet accepted A and B as true, he might still accept the sequence as a valid one, I suppose?"
"No doubt such a reader might exist. He might say 'I accept as true the Hypothetical Proposition that, if A and B be true, Z must be true; but, I don't accept A and B as true.' Such a reader would do wisely in abandoning Euclid, and taking to football."
"And might there not also be some reader who would say 'I accept A and B as true, but I don't accept the Hypothetical'?"
"Certainly there might. He, also, had better take to football."
"And neither of these readers," the Tortoise continued, "is as yet under any logical necessity to accept Z as true?"
"Quite so," Achilles assented.
"Well, now, I want you to consider me as a reader of the second kind, and to force me, logically, to accept Z as true."
... "I'm to force you to accept Z, am I?" Achilles said musingly. "And your present position is that you accept A and B, but you don't accept the Hypothetical—"
"Let's call it C," said the Tortoise.
"—but you don't accept
(C) If A and B are true, Z must be true."
"That is my present position," said the Tortoise.
"Then I must ask you to accept C."
"I'll do so," said the Tortoise, "as soon as you've entered it in that note-book of yours. What else have you got in it?"
"Only a few memoranda," said Achilles, nervously fluttering the leaves: "a few memoranda of—of the battles in which I have distinguished myself!"
"Plenty of blank leaves, I see!" the Tortoise cheerily remarked. "We shall need them all!" (Achilles shuddered.) "Now write as I dictate:—
(A) Things that are equal to the same are equal to each other.
(B) The two sides of this Triangle are things that are equal to the same.
(C) If A and B are true, Z must be true.
(Z) The two sides of this Triangle are equal to each other."
"You should call it D, not Z," said Achilles. "It comes next to the other three. If you accept A and B and C, you must accept Z."
"And why must I?"
"Because it follows logically from them. If A and B and C are true, Z must be true. You don't dispute that, I imagine?"
"If A and B and C are true, Z must be true," the Tortoise thoughtfully repeated. "That's another Hypothetical, isn't it? And, if I failed to see its truth, I might accept A and B and C, and still not accept Z, mightn't I?”
"You might," the candid hero admitted; "though such obtuseness would certainly be phenomenal. Still, the event is possible. So I must ask you to grant one more Hypothetical."
"Very good. I'm quite willing to grant it, as soon as you've written it down..."...
まず注意しておきたいのは、これが論理学と数学がモダナイズされようとしていた時代のさなかに書かれたもので、いわゆる伝統的論理学とユークリッド原論の初歩の知識を前提としている、ということだ。(問題の推論は、形はやや異なるものの、実際にユークリッド原論第一巻の第一命題の証明中に見出せる。その命題は、所与の直線をもとに等辺三角形を構成すること、というもので、その証明は下の図のように円の性質に依拠している。(the two sides of this Triangle というのは ΑΓ と ΒΓ のことだ。)なお、ユークリッドにおいては線はもっぱら有限だ。)仮令ユークリッドの読者の誰かが A と B を真だと認めなかったとしても、それでもやはり彼は A と B から Z に到るシークエンスを妥当なものと認めることだろう、というカメの言葉に同意したあとで、アキレスがさらに、そのような者は「私は、A と B が真ならば Z は真であるほかない、という仮言命題を真だと認めるが、A と B を真だとは認めない」と云うことだろう、とわざわざ付け加えるのは、それがこのような場合に論理学の心得があることを示すためにひとが口にすべき紋切型というやつだから、という訳なのだろう。アキレスは、どうやら、「do not accept as true」を、理解できなくて真だと受け容れることができない、というほどの意味に解して、論理学の初歩を一応は知っているもののユークリッド入門に躓いた少年を想い描いているようだ。(ユークリッドの初歩を理解できないような少年でも問題の推論は妥当だとちゃんと判断できる、という想定はさほど不自然なものではないかも知れない。件の推論はいわゆる定言三段論法の第一格 AAA(通称 Barbara)という妥当な推論の典型中の典型に収まるものと看做し得るからだ。なお、定言三段論法の妥当性は、前提が何れも真ならば結論は真であるほかない、ということによって規定される。)ここまではまあいいとしよう。ところが、その紋切型を待ってましたとばかりに、カメが、それなら「私は A と B を真だと認めるが、件の仮言を認めない」と云う者だっているのではないか、とたたみかけ、アキレスがそれをあっさりと肯定してしまうところから話がおかしくなる。
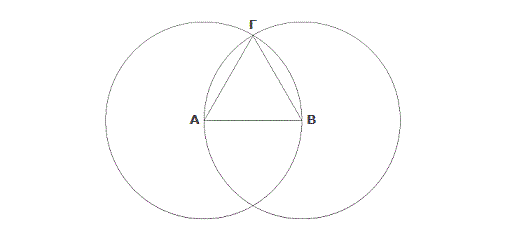
まず、Heath による英訳から円とその中心の定義(第十五および第十六定義)を引けば次の通り:
15. A circle is a plane figure contained by one line such that all the straight lines falling upon it from one point among those lying within the figure are equal to one another;
16. And the point is called the centre of the circle.
ここから次のような命題が得られるだろう:
All the straight lines falling upon the circumscribing line of a circle from its centre are equal to one another.
一方、ΑΒ と ΑΓ については次が得られる:
ΑΒ and ΑΓ are straight lines that are falling upon the circumscribing line of a circle from its centre.
これらから次が帰結する:
ΑΒ and ΑΓ are equal to one another.
これは、だが、問題の推論と同型の三段論法だ。件の仮言命題を認めないという彼奴はこれに係わる同様の仮言を認めるのか認めないのか? アキレスはそう問うてみてもよかったかも知れない。
もっとも、俺が解せないのはこの点ではない。問題はこれからだ。アキレスは「私を第二の類の読者だと想定して、Z を真だと論理的に認めざるを得ないようにしてみてほしい」というカメの誘いにこれまたあっさりと乗って、カメの仮想上の立場を確認したうえで「そこで俺はお前に C を認めて貰わねばならない訳だ」とこれまたわざわざ付け加え、そしてこれまたそれを待ってましたとばかりにカメが返した「そうしよう。それをそのノートに書込んでくれさえすれば」という言葉にまたまたあっさりと応じてしまう。そもそもカメが成り代わっている人物は C を認めないはずだったのに、しかもアキレスとカメはそれを確認したばかりなのに、いったいこれはどうしたことなのか? アキレスはカメと一丸となってもっぱら C の類の仮言命題を再帰的に弾き出し続けるマシーンと化すことをひたすら望んでいるかの如くだ。やはり彼らは追いかけっこするうちにいつのまにかワンダーランドに迷い込んでしまったものに相違ない。
ところで、この理不尽な展開を補うべく、アキレスは C を受け容れさせることでカメの論理学的無知を埋めようとし、カメはそれを甘受する、といった脚色がなされたりすることがあるが、もちろん、そうしたストーリーは他にも色々と考えてみることができる。そして、それにつれて例えば次のような一聯の問いが浮かびあがって来る: A と B が真ならば Z は真であるほかないという命題を真だと認めることと A と B が真ならば Z は真であるほかないということを認めることは同じではないだろうが、ならばそれらはどう違うのか? そもそも A と B が真ならば Z は真であるほかないという命題を真だと認めるとはどういうことなのか? ひとがそれをそう認めているということのクリテリオンは何なのか? A と B が真ならば Z は真であるほかないということを認めるとはどういうことなのか? ひとがそれを認めているということのクリテリオンは何なのか?・・・ ひょっとして、キャロルはこうした効果を狙って、敢えて無造作な語り方を選んだのでもあろうか。ちなみに、カメは最後の方で「what a lot of instruction this colloquy of ours will provide for the Logicians of the Nineteenth Century」と云っているが、どうやらこの対話篇には、様々なインストラクションやインスピレーションを提供すべく、あれこれ仕掛けが施されているらしい。やはりキャロルの名義は伊達ではないようだ。(ついでに、このあとの展開を書いておけば、透明だった語り手が見物していた第三者として顕われて、彼は銀行に急用があったのでその場を離れねばならず、数箇月後にふたたび通りかかってみると、一千一箇目の仮言命題をアキレスが書き終えたところだった、ということになっている。だが、そう語っているのは最初の語り手なのか、それとも第二の透明な語り手なのか?)
それはそうと、カメが成り代わっている人物は A と B を真だと認めるが C を認めない者としかされていないのだから、彼に代わって云い得ることは実は何も無い。可能なのは、ただ、何か妥当な推論が呈示されるたびに、それに係わる C と同様の仮言命題を彼はやはり認めないかも知れない、と指摘することだけだろう。そこで、彼が演繹的推論を悉く受けつけない推論盲とでも呼び得るような者だったとしたら、と考えてみたくなるのは俺ばかりではあるまい。ヴィトゲンシュタインは『哲学探求』第二部で、例えばウサギ‐アヒルの図を兎として見たり家鴨として見たりすることができないような者を想定し、アスペクト盲と呼んで「概念的診察」をおこなっているが、それに倣って、推論盲の概念的診察を試みればどういうことになるか。とっくに誰かがやっているだろうか?
最後に問題の推論を量化理論に拠ってパラフレーズしておく。
(A') ∀x∀y(∃z((x is equal to z)∧(y is equal to z))⊃(x and y are equal to each other))
これから普遍例化によって次が得られる:
(A'') ∃z((ΑΓ is equal to z)∧(ΒΓ is equal to z))⊃(ΑΓ and ΒΓ are equal to each other)
これと
(B') ∃z((ΑΓ is equal to z)∧(ΒΓ is equal to z))
から、モドゥス・ポネンスによって次が得られる:
(Z') (ΑΓ and ΒΓ are equal to each other)
A' が真ならば当然 A'' も真だが、さらに B' が真だとすれば Z' が真であるほかないことは A'' の形から一目瞭然だ。もちろん、C を認めない彼奴はこれもまた認めないかも知れないが。
2015-03-17 11:59
コメント(0)
続アキレスがカメに云ったこと [ノート]
その後、いわゆる伝統的論理学ではなしに元祖アリストテレスの論理学というのはそもそもどういうものなのか、興味を覚え、分析論前書の A. J. Jenkinson による英訳のはじめの方に当たってみたところ、キャロルはそのあたりの知識も前提としていたのではないかと気付いたので、それについてちょっと書き留めておこうと思う。なお、アリストテレスは「sullogismos」という語を単に妥当な推論というほどの意味で用いていたようだ。下の引用における「syllogism」は、だから、そのつもりで読み替えてもらいたい。また、ここで扱うのはいわゆる定言三段論法の形の推論だけであり、そこに現われる命題は二つのタームを含む次のような形のものに限られる。
● B はみな A である。
● B は一切 A でない。
● B の一部は A である。
● B の一部は A でない。
アリストテレスはまず次のように述べている。
「Whenever three terms are so related to one another that the last is contained in the middle as in a whole, and the middle is either contained in, or excluded from, the first as in or from a whole, the extremes must be related by a perfect syllogism... If A is predicated of all B, and B of all C, A must be predicated of all C: we have already explained what we mean by ‘predicated of all’. Similarly also, if A is predicated of no B, and B of all C, it is necessary that no C will be A.」(Prior Analytics I.4)
この「predicated of all」の意味とは次の通り。
「That one term should be included in another as in a whole is the same as for the other to be predicated of all of the first. And we say that one term is predicated of all of another, whenever no instance of the subject can be found of which the other term cannot be asserted.」(I.1)
どうもいまひとつ要領を得ないが、ここはこれを勝手に今日流に解釈し、そうして先のくだりを敷衍してみることにしたい。
まず、タームの外延(つまりそのタームを具現している個物の総体)を「ext(A)」のように表わすことにして、次のような形の命題を考えよう。
● B がみな A であるのは ext(B) が ext(A) にすっかり含まれる場合であり、その場合に限る。
● B が一切 A でないのは ext(B) が ext(A) に全然含まれない場合であり、その場合に限る。
● B の一部が A であるのは ext(B) が ext(A) に全然含まれないわけではない場合であり、その場合に限る。
● B の一部が A でないのは ext(B) が ext(A) にすっかり含まれるわけではない場合であり、その場合に限る。
ここでは外延が空のタームは考えに入れないものとし、これらの形の命題をひとからげに量の原理とでも呼ぶことにして、さらに次のような形の命題を考えよう。
(1) ext(C) が ext(B) にすっかり含まれ ext(B) が ext(A) にすっかり含まれるならば、ext(C) は ext(A) にすっかり含まれる。
(2) ext(C) が ext(B) にすっかり含まれ ext(B) が ext(A) に全然含まれないならば、ext(C) は ext(A) に全然含まれない。
量の原理を認め、さらに (1) や (2) の形の命題を悉く認めるならば、次のような形の命題はそこに含まれるタームの如何にかかわらず悉く真であることが了解されるだろう。
(1') C がみな B であり B がみな A であるならば、C はみな A である。
(2') C がみな B であり B が一切 A でないならば、C は一切 A でない。
もちろん、以上は (1') や (2') の形の命題が今日流に云えば論理的に真(あるいは妥当あるいは恒真)であることを証明しようとするものではない。ただ、タームの外延のあいだの関係の直観的把握にうったえることによって、これらの形の命題が謂わば原理的に真であることを浮かびあがらせようと試みているまでだ。さて、それが納得されたとして、これらの形の命題を前提に含む次のような形の推論を考えてみよう。
(inf1) C はみな B であり、B はみな A である。ところが、C がみな B であり B がみな A であるならば、C はみな A である。したがって、C はみな A である。
(inf2) C はみな B であり、B は一切 A でない。ところが、C がみな B であり B が一切 A でないならば、C は一切 A でない。したがって、C は一切 A でない。
これらの形の推論が妥当であることは自明だろう――カメには暫し口を噤んでいてもらうとして。ところが、(1') や (2') の形の命題はそこに含まれるタームの如何にかかわらず悉く真なのだから、これらの形の前提を (inf1) や (inf2) の形の推論から云うまでもないものとして省いてしまうことにしても別に不都合はないだろう。かくて伝統的論理学における定言三段論法第一格の通称 Barbara および Celarent の推論規則が得られることになる。
ここでさらに次のような形の命題を考えよう。
● ext(B) が ext(A) に全然含まれないならば、ext(A) は ext(B) に全然含まれない。
● ext(B) が ext(A) にすっかり含まれるならば、ext(A) は ext(B) に全然含まれないわけではない。
● ext(B) が ext(A) に全然含まれないわけではないならば、ext(A) は ext(B) に全然含まれないわけではない。
量の原理を認め、さらにこれらの形の命題を悉く認めるならば、次のような形の命題は悉く真であることが了解されるだろう。
● B が一切 A でないならば、A は一切 B でない。
● B がみな A であるならば、A の一部は B である。
● B の一部が A であるならば、A の一部は B である。
かくて、(inf1) および (inf2) の場合と同様に、いわゆる換位(conversion)の三つの推論規則が得られる。
アリストテレスが分析論前書のはじめのあたりでおこなっているのは、以上のようにして得られる五つの推論規則を駆使して、伝統的論理学における通称 Darii、Ferio、Cesare、Camestres、Festino、Baroco、Darapti、Felapton、Disamis、 Datisi、Bocardo、Ferison の十二の規則を導く作業なのだと解釈し得る。せっかくだから、第二格の四つについて、それを見ておこう。
まずは Cesare と Camestres から。
「Let M be predicated of no N, but of all O. Since, then, the negative relation is convertible, N will belong to no M: but M was assumed to belong to all O: consequently N will belong to no O. This has already been proved. Again if M belongs to all N, but to no O, then N will belong to no O. For if M belongs to no O, O belongs to no M: but M (as was said) belongs to all N: O then will belong to no N: for the first figure has again been formed. But since the negative relation is convertible, N will belong to no O. 」(I.5)
これは次のように云い替えることができるだろう。
「まず、N は一切 M でないと仮定すれば、換位によって、M は一切 N でない。そこで、さらに、O はみな M であると仮定すれば、第一格の第二の推論規則[Celarent]によって、O は一切 N でない。つまり、N が一切 M でなく O がみな M であるならば、O は一切 N でない。
次に、N はみな M であると仮定する。そのうえで、O は一切 M でないと仮定すれば、換位によって、M は一切 O でないから、ふたたび第一格の第二の推論規則によって、N は一切 O でない。したがって、換位によって、O は一切 N でない。つまり、N がみな M で O が一切 M でないならば、O は一切 N でない。」
次に Festino と Baroco。
「...if M belongs to no N, but to some O, it is necessary that N does not belong to some O. For since the negative statement is convertible, N will belong to no M: but M was admitted to belong to some O: therefore N will not belong to some O: for the result is reached by means of the first figure. Again if M belongs to all N, but not to some O, it is necessary that N does not belong to some O: for if N belongs to all O, and M is predicated also of all N, M must belong to all O: but we assumed that M does not belong to some O. And if M belongs to all N but not to all O, we shall conclude that N does not belong to all O... 」(I.5)
これは次のように云い替えることができるだろう。
「まず、N は一切 M でないと仮定すれば、換位によって、M は一切 N でない。そこで、さらに、O の一部は M であると仮定すれば、第一格の第四の推論規則[Ferio]によって[つまり、N が一切 M でなく O の一部が M であるならば、O の一部は N でないから]、O の一部は N でない。つまり、N が一切 M でなく O の一部が M であるならば、O の一部は N でない。[なお、Ferio は Cesare にもとづいて導かれる。Cesare は既に見た通り Celarent にもとづいて導かれるから、結局、Festino は Celarent に還元される。]
次に、N はみな M であると仮定し、また、O の一部は M でないと仮定する。そのうえで、O はみな N であると仮定すれば、第一の仮定から、第一格の第一の推論規則[Barbara]によって、O はみな M である。しかし、これは第二の仮定と両立し得ないから、O の一部は N でない。つまり、N がみな M であり O の一部が M でないならば、O の一部は N でない。」
かくて、(inf1) および (inf2) の場合と同様に、四つの推論規則が得られることは明らかだろう。
さて、ここでカメに口を開いてもらうとすればどうなるか? もちろんアキレスにも加わってもらって。聞けば彼は、特大ノートのページ切れのせいでカメとの共同作業が頓挫したのち、ケンブリッジに遊学して新進の哲学徒バートランド・ラッセルと近付きになり、イェーナのゴットロープ・フレーゲの概念記法なるものを一緒に研究していたのだとか――息抜きにはフットボールをしたりしつつ。しかも、彼はラッセルの未来の弟子ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインがやがて書き遺すことになる数学の基礎をめぐる一聯のノートのコピーまで早々と手に入れて来たらしい。――と書いておいて、あとはうっかりここまで読んでしまったあなたに委ねるとしよう。別に急用があるわけではないのだが。
なお、Stanford Encyclopedia of Philosophy の Aristotle's Logic のページ
http://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/aristotle-logic/
をおおいに参考にしたことを付け加えておく。
● B はみな A である。
● B は一切 A でない。
● B の一部は A である。
● B の一部は A でない。
アリストテレスはまず次のように述べている。
「Whenever three terms are so related to one another that the last is contained in the middle as in a whole, and the middle is either contained in, or excluded from, the first as in or from a whole, the extremes must be related by a perfect syllogism... If A is predicated of all B, and B of all C, A must be predicated of all C: we have already explained what we mean by ‘predicated of all’. Similarly also, if A is predicated of no B, and B of all C, it is necessary that no C will be A.」(Prior Analytics I.4)
この「predicated of all」の意味とは次の通り。
「That one term should be included in another as in a whole is the same as for the other to be predicated of all of the first. And we say that one term is predicated of all of another, whenever no instance of the subject can be found of which the other term cannot be asserted.」(I.1)
どうもいまひとつ要領を得ないが、ここはこれを勝手に今日流に解釈し、そうして先のくだりを敷衍してみることにしたい。
まず、タームの外延(つまりそのタームを具現している個物の総体)を「ext(A)」のように表わすことにして、次のような形の命題を考えよう。
● B がみな A であるのは ext(B) が ext(A) にすっかり含まれる場合であり、その場合に限る。
● B が一切 A でないのは ext(B) が ext(A) に全然含まれない場合であり、その場合に限る。
● B の一部が A であるのは ext(B) が ext(A) に全然含まれないわけではない場合であり、その場合に限る。
● B の一部が A でないのは ext(B) が ext(A) にすっかり含まれるわけではない場合であり、その場合に限る。
ここでは外延が空のタームは考えに入れないものとし、これらの形の命題をひとからげに量の原理とでも呼ぶことにして、さらに次のような形の命題を考えよう。
(1) ext(C) が ext(B) にすっかり含まれ ext(B) が ext(A) にすっかり含まれるならば、ext(C) は ext(A) にすっかり含まれる。
(2) ext(C) が ext(B) にすっかり含まれ ext(B) が ext(A) に全然含まれないならば、ext(C) は ext(A) に全然含まれない。
量の原理を認め、さらに (1) や (2) の形の命題を悉く認めるならば、次のような形の命題はそこに含まれるタームの如何にかかわらず悉く真であることが了解されるだろう。
(1') C がみな B であり B がみな A であるならば、C はみな A である。
(2') C がみな B であり B が一切 A でないならば、C は一切 A でない。
もちろん、以上は (1') や (2') の形の命題が今日流に云えば論理的に真(あるいは妥当あるいは恒真)であることを証明しようとするものではない。ただ、タームの外延のあいだの関係の直観的把握にうったえることによって、これらの形の命題が謂わば原理的に真であることを浮かびあがらせようと試みているまでだ。さて、それが納得されたとして、これらの形の命題を前提に含む次のような形の推論を考えてみよう。
(inf1) C はみな B であり、B はみな A である。ところが、C がみな B であり B がみな A であるならば、C はみな A である。したがって、C はみな A である。
(inf2) C はみな B であり、B は一切 A でない。ところが、C がみな B であり B が一切 A でないならば、C は一切 A でない。したがって、C は一切 A でない。
これらの形の推論が妥当であることは自明だろう――カメには暫し口を噤んでいてもらうとして。ところが、(1') や (2') の形の命題はそこに含まれるタームの如何にかかわらず悉く真なのだから、これらの形の前提を (inf1) や (inf2) の形の推論から云うまでもないものとして省いてしまうことにしても別に不都合はないだろう。かくて伝統的論理学における定言三段論法第一格の通称 Barbara および Celarent の推論規則が得られることになる。
ここでさらに次のような形の命題を考えよう。
● ext(B) が ext(A) に全然含まれないならば、ext(A) は ext(B) に全然含まれない。
● ext(B) が ext(A) にすっかり含まれるならば、ext(A) は ext(B) に全然含まれないわけではない。
● ext(B) が ext(A) に全然含まれないわけではないならば、ext(A) は ext(B) に全然含まれないわけではない。
量の原理を認め、さらにこれらの形の命題を悉く認めるならば、次のような形の命題は悉く真であることが了解されるだろう。
● B が一切 A でないならば、A は一切 B でない。
● B がみな A であるならば、A の一部は B である。
● B の一部が A であるならば、A の一部は B である。
かくて、(inf1) および (inf2) の場合と同様に、いわゆる換位(conversion)の三つの推論規則が得られる。
アリストテレスが分析論前書のはじめのあたりでおこなっているのは、以上のようにして得られる五つの推論規則を駆使して、伝統的論理学における通称 Darii、Ferio、Cesare、Camestres、Festino、Baroco、Darapti、Felapton、Disamis、 Datisi、Bocardo、Ferison の十二の規則を導く作業なのだと解釈し得る。せっかくだから、第二格の四つについて、それを見ておこう。
まずは Cesare と Camestres から。
「Let M be predicated of no N, but of all O. Since, then, the negative relation is convertible, N will belong to no M: but M was assumed to belong to all O: consequently N will belong to no O. This has already been proved. Again if M belongs to all N, but to no O, then N will belong to no O. For if M belongs to no O, O belongs to no M: but M (as was said) belongs to all N: O then will belong to no N: for the first figure has again been formed. But since the negative relation is convertible, N will belong to no O. 」(I.5)
これは次のように云い替えることができるだろう。
「まず、N は一切 M でないと仮定すれば、換位によって、M は一切 N でない。そこで、さらに、O はみな M であると仮定すれば、第一格の第二の推論規則[Celarent]によって、O は一切 N でない。つまり、N が一切 M でなく O がみな M であるならば、O は一切 N でない。
次に、N はみな M であると仮定する。そのうえで、O は一切 M でないと仮定すれば、換位によって、M は一切 O でないから、ふたたび第一格の第二の推論規則によって、N は一切 O でない。したがって、換位によって、O は一切 N でない。つまり、N がみな M で O が一切 M でないならば、O は一切 N でない。」
次に Festino と Baroco。
「...if M belongs to no N, but to some O, it is necessary that N does not belong to some O. For since the negative statement is convertible, N will belong to no M: but M was admitted to belong to some O: therefore N will not belong to some O: for the result is reached by means of the first figure. Again if M belongs to all N, but not to some O, it is necessary that N does not belong to some O: for if N belongs to all O, and M is predicated also of all N, M must belong to all O: but we assumed that M does not belong to some O. And if M belongs to all N but not to all O, we shall conclude that N does not belong to all O... 」(I.5)
これは次のように云い替えることができるだろう。
「まず、N は一切 M でないと仮定すれば、換位によって、M は一切 N でない。そこで、さらに、O の一部は M であると仮定すれば、第一格の第四の推論規則[Ferio]によって[つまり、N が一切 M でなく O の一部が M であるならば、O の一部は N でないから]、O の一部は N でない。つまり、N が一切 M でなく O の一部が M であるならば、O の一部は N でない。[なお、Ferio は Cesare にもとづいて導かれる。Cesare は既に見た通り Celarent にもとづいて導かれるから、結局、Festino は Celarent に還元される。]
次に、N はみな M であると仮定し、また、O の一部は M でないと仮定する。そのうえで、O はみな N であると仮定すれば、第一の仮定から、第一格の第一の推論規則[Barbara]によって、O はみな M である。しかし、これは第二の仮定と両立し得ないから、O の一部は N でない。つまり、N がみな M であり O の一部が M でないならば、O の一部は N でない。」
かくて、(inf1) および (inf2) の場合と同様に、四つの推論規則が得られることは明らかだろう。
さて、ここでカメに口を開いてもらうとすればどうなるか? もちろんアキレスにも加わってもらって。聞けば彼は、特大ノートのページ切れのせいでカメとの共同作業が頓挫したのち、ケンブリッジに遊学して新進の哲学徒バートランド・ラッセルと近付きになり、イェーナのゴットロープ・フレーゲの概念記法なるものを一緒に研究していたのだとか――息抜きにはフットボールをしたりしつつ。しかも、彼はラッセルの未来の弟子ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインがやがて書き遺すことになる数学の基礎をめぐる一聯のノートのコピーまで早々と手に入れて来たらしい。――と書いておいて、あとはうっかりここまで読んでしまったあなたに委ねるとしよう。別に急用があるわけではないのだが。
なお、Stanford Encyclopedia of Philosophy の Aristotle's Logic のページ
http://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/aristotle-logic/
をおおいに参考にしたことを付け加えておく。
2015-11-01 21:21
コメント(0)
規則が振舞い方を規定することなどあり得ないとさ。どんな振舞い方も当の規則に合致させ得るのだからと。 [ノート]
前回の最後にヴィトゲンシュタインの名をだしたが、その後、『哲学探究』第一部を読みなおしていたところ、というか、原文をはじめてまともに読んでいたら、どうもひっかかるところがあって、あれこれ考えてみたあげく、そのあたりがはじめて理解できた気になったので、ちょっと書留めておきたい。
まずは、そのあたり、§198 から§202 にかけてを適宜省略しつつ引いておこう。
198. »Aber wie kann mich eine Regel lehren, was ich an dieser Stelle zu tun habe[それにしても規則がこの場合に何を為すべきかを私に教えるというようなことがどうしてあり得るのか]? Was immer ich tue, ist doch durch irgendeine Deutung mit der Regel zu vereinbaren[私が何を為そうが、それは何らかの解釈によって当の規則に適合させ得るのに].« ― Nein, so sollte es nicht heißen[いや、そう云うべきではなかろう]. Sondern so[寧ろこうだ]: Jede Deutung hängt, mitsamt dem Gedeuteten, in der Luft[何れの解釈も解釈されたものともども宙に浮いている]; sie kann ihm nicht als Stütze dienen[その支えにはならない]. Die Deutungen allein bestimmen die Bedeutung nicht[解釈が単独で意義を規定することはない].
»Also ist, was immer ich tue, mit der Regel vereinbar[それでも私が何を為そうが、それは当の規則に適合し得るだろう]?« ― Laß mich so fragen[こう問わせてもらおう]: Was hat der Ausdruck der Regel ― sagen wir, der Wegweiser ― mit meinen Handlungen zu tun[規則の表現――例えば道標――は私の振舞とどんな係りをもつのか]? Was für eine Verbindung besteht da[どんな類の結びつきがそこになりたっているのか]? ― Nun, etwa diese[そう、例えばこれだ]: ich bin zu einem bestimmten Reagieren auf dieses Zeichen abgerichtet worden, und so reagiere ich nun[私はこの記号に特定の反応をするよう仕込まれたのであり、それでいまそう反応する].
Aber damit hast du nur einen kausalen Zusammenhang angegeben[だが、君は因果関係を挙げているだけだ], nur erklärt, wie es dazu kam, daß wir uns jetzt nach dem Wegweiser richt[どうやって我々が道標に導かれるようになったかを説明しているだけだ]; nicht, worin dieses Dem-Zeichen-Folgen eigentlich besteht[この記号随遵がそもそも何処になりたっているのかを説明してはいない]. Nein; ich habe auch noch angedeutet[いや、私はさらに次の点をも示唆している], daß sich Einer nur insofern nach einem Wegweiser richtet, als es einen ständigen Gebrauch, eine Gepflogenheit, gibt[安定した使用、慣習がある限りにおいて、ひとは道標に導かれる].
199. Ist, was wir »einer Regel folgen« nennen, etwas, was nur ein Mensch, nur einmal im Leben, tun könnte[我々が「規則にしたがう」と呼ぶものは、ただ一人の者だけが生涯にただ一度だけ為し得るようなことがらだろうか]? ― Und das ist natürlich eine Anmerkung zur Grammatik des Ausdrucks »der Regel folgen«[ところで、これはもちろん「規則にしたがう」という表現の文法についての註だ。].
... Einer Regel folgen, eine Mitteilung machen, einen Befehl geben, eine Schachpartie spielen sind Gepflogenheiten (Gebräuche, Institutionen)[《規則にしたがう》、《報告をする》、《命令をあたえる》、《チェスの勝負をする》は慣習(しきたり、制度)だ。]...
200. Es ist natürlich denkbar, daß in einem Volke, das Spiele nicht kennt, zwei Leute sich an ein Schachbrett setzen und die Züge einer Schachpartie ausführen[盤上ゲームのようなものを知らない民族において二人の者がチェス盤にむかってチェスの一勝負に相当する仕方で駒を動かす、ということはもちろん考え得る]; ja auch mit allen seelischen Begleiterscheinungen[しかもそれらしい心的見かけをも伴って]. Und sähen wir dies, so würden wir sagen, sie spielten Schach[そしてそれを見たら我々は云うことだろう。彼らはチェスをしている、と]...
201. Unser Paradox war dies[我々のパラドクスとやらはこれなのだった]: eine Regel könnte keine Handlungsweise bestimmen[規則が振舞い方を規定することはあり得ない], da jede Handlungsweise mit der Regel in Übereinstimmung zu bringen sei[どんな振舞い方も当の規則に合致させ得るのだから]. Die Antwort war[答はこうなのだった]: Ist jede mit der Regel in Übereinstimmung zu bringen, dann auch zum Widerspruch[合致させ得るからには、矛盾させることだってできる]. Daher gäbe es hier weder Übereinstimmung noch Widerspruch[よって、ここには合致も矛盾も無かろう].
Daß da ein Mißverständnis ist, zeigt sich schon darin[ここに誤解が存在することは次の点から既に明らかだ], daß wir in diesem Gedankengang Deutung hinter Deutung setzen[我々はこの思考過程において解釈に解釈を重ねている]; als beruhige uns eine jede wenigstens für einen Augenblick, bis wir an eine Deutung denken, die wieder hinter dieser liegt[それぞれの解釈が、ともあれ次に控えている解釈を考えるまでの束の間は、我々を落着かせでもするかのごとく]. Dadurch zeigen wir nämlich[それによって我々は次のことを示している訳だ], daß es eine Auffassung einer Regel gibt, die nicht eine Deutung ist[解釈ではない規則把握が在る]; sondern sich, von Fall zu Fall der Anwendung, in dem äußert, was wir »der Regel folgen«, und was wir »ihr entgegenhandeln« nennen[適用事例から適用事例へと、我々が何を「規則にしたがっている」と呼び何を「規則に反して振舞っている」と呼ぶかに表われる規則把握が].
Darum besteht eine Neigung, zu sagen: jedes Handeln nach der Regel sei ein Deuten[そういう訳で、規則にのっとった振舞は何れも解釈である、とする傾向は根強い]. »Deuten« aber sollte man nur nennen: einen Ausdruck der Regel durch einen anderen ersetzen[だが、規則の一表現を別の表現に置き換えることをもっぱら「解釈」と呼ぶべきだろう。].
202. Darum ist ›der Regel folgen‹ eine Praxis[そういう訳で、「規則にしたがう」はプラクシスだ]. Und der Regel zu folgen glauben ist nicht: der Regel folgen[そして《規則にしたがっていると思っている》は《規則にしたがっている》ではない]. Und darum kann man nicht der Regel ›privatim‹ folgen[それ故、規則に「私的に」したがうことは叶わない], weil sonst der Regel zu folgen glauben dasselbe wäre, wie der Regel folgen[さもなければ、《規則にしたがっていると思っている》が《規則にしたがっている》と同じことになってしまうから].
§201 は「Unser Paradox war dies」と過去時制ではじまり、「eine Regel könnte keine Handlungsweise bestimmen, da jede Handlungsweise mit der Regel in Übereinstimmung zu bringen sei」と接続法(第二に第一)で続けられている。つまり、そのパラドクスなるものは念入りに距離を置くようにして呈示されている訳で、さっさと片付けるためにもちだされているようにも受けとれる。(それを酌んで、上ではその出だしを「我々のパラドクスとやらはこれなのだった」と訳してみた。はじめはそれに続く方を今回のこの文章のタイトルのように訳そうかと考えたのだったが。)そして、実際それは、次のような意味で、その場で片付けられていると云い得る。
件のパラドクスとやらは、§198 に現われる「規則がこの場合に何を為すべきかを私に教えるというようなことがどうしてあり得るのか? 私が何を為そうが、それは何らかの解釈によって当の規則に適合させ得るのに」という引用符にくくられた主張ともども、解釈なるものに惑わされた錯誤の見本なのであり、《規則にしたがう》が那辺に存するのかをはっきりさせるための手だてとしてひきあいにだされている。そして、《規則にしたがう》はプラクシスであり、規則に私的にしたがうことは叶わない、ということが見さだめられたところで、用済みとなっている。
なお、俺がひっかかったのは別に原文の叙法や時制ではなくて、「規則が振舞い方を規定することはあり得ない。どんな振舞い方も当の規則に合致させ得るのだから」というようなことがどうして云い得るのか、という点なのだった。そして、あれこれ考えているうちに、これは接続法で述べられているのだから問題としてまともに提起されている訳ではないのではないか、と思いあたったのだった。
もちろん、《規則にしたがう》をめぐる話はこれでは終わらない。ヴィトゲンシュタインがしつこく考え続けたのは§185 に登場する +2 の数列を 1000、1004、1008、1012 と続ける生徒に象徴されることがらだったようなのだが、しかし、それについてはまたの機会としよう。
まずは、そのあたり、§198 から§202 にかけてを適宜省略しつつ引いておこう。
198. »Aber wie kann mich eine Regel lehren, was ich an dieser Stelle zu tun habe[それにしても規則がこの場合に何を為すべきかを私に教えるというようなことがどうしてあり得るのか]? Was immer ich tue, ist doch durch irgendeine Deutung mit der Regel zu vereinbaren[私が何を為そうが、それは何らかの解釈によって当の規則に適合させ得るのに].« ― Nein, so sollte es nicht heißen[いや、そう云うべきではなかろう]. Sondern so[寧ろこうだ]: Jede Deutung hängt, mitsamt dem Gedeuteten, in der Luft[何れの解釈も解釈されたものともども宙に浮いている]; sie kann ihm nicht als Stütze dienen[その支えにはならない]. Die Deutungen allein bestimmen die Bedeutung nicht[解釈が単独で意義を規定することはない].
»Also ist, was immer ich tue, mit der Regel vereinbar[それでも私が何を為そうが、それは当の規則に適合し得るだろう]?« ― Laß mich so fragen[こう問わせてもらおう]: Was hat der Ausdruck der Regel ― sagen wir, der Wegweiser ― mit meinen Handlungen zu tun[規則の表現――例えば道標――は私の振舞とどんな係りをもつのか]? Was für eine Verbindung besteht da[どんな類の結びつきがそこになりたっているのか]? ― Nun, etwa diese[そう、例えばこれだ]: ich bin zu einem bestimmten Reagieren auf dieses Zeichen abgerichtet worden, und so reagiere ich nun[私はこの記号に特定の反応をするよう仕込まれたのであり、それでいまそう反応する].
Aber damit hast du nur einen kausalen Zusammenhang angegeben[だが、君は因果関係を挙げているだけだ], nur erklärt, wie es dazu kam, daß wir uns jetzt nach dem Wegweiser richt[どうやって我々が道標に導かれるようになったかを説明しているだけだ]; nicht, worin dieses Dem-Zeichen-Folgen eigentlich besteht[この記号随遵がそもそも何処になりたっているのかを説明してはいない]. Nein; ich habe auch noch angedeutet[いや、私はさらに次の点をも示唆している], daß sich Einer nur insofern nach einem Wegweiser richtet, als es einen ständigen Gebrauch, eine Gepflogenheit, gibt[安定した使用、慣習がある限りにおいて、ひとは道標に導かれる].
199. Ist, was wir »einer Regel folgen« nennen, etwas, was nur ein Mensch, nur einmal im Leben, tun könnte[我々が「規則にしたがう」と呼ぶものは、ただ一人の者だけが生涯にただ一度だけ為し得るようなことがらだろうか]? ― Und das ist natürlich eine Anmerkung zur Grammatik des Ausdrucks »der Regel folgen«[ところで、これはもちろん「規則にしたがう」という表現の文法についての註だ。].
... Einer Regel folgen, eine Mitteilung machen, einen Befehl geben, eine Schachpartie spielen sind Gepflogenheiten (Gebräuche, Institutionen)[《規則にしたがう》、《報告をする》、《命令をあたえる》、《チェスの勝負をする》は慣習(しきたり、制度)だ。]...
200. Es ist natürlich denkbar, daß in einem Volke, das Spiele nicht kennt, zwei Leute sich an ein Schachbrett setzen und die Züge einer Schachpartie ausführen[盤上ゲームのようなものを知らない民族において二人の者がチェス盤にむかってチェスの一勝負に相当する仕方で駒を動かす、ということはもちろん考え得る]; ja auch mit allen seelischen Begleiterscheinungen[しかもそれらしい心的見かけをも伴って]. Und sähen wir dies, so würden wir sagen, sie spielten Schach[そしてそれを見たら我々は云うことだろう。彼らはチェスをしている、と]...
201. Unser Paradox war dies[我々のパラドクスとやらはこれなのだった]: eine Regel könnte keine Handlungsweise bestimmen[規則が振舞い方を規定することはあり得ない], da jede Handlungsweise mit der Regel in Übereinstimmung zu bringen sei[どんな振舞い方も当の規則に合致させ得るのだから]. Die Antwort war[答はこうなのだった]: Ist jede mit der Regel in Übereinstimmung zu bringen, dann auch zum Widerspruch[合致させ得るからには、矛盾させることだってできる]. Daher gäbe es hier weder Übereinstimmung noch Widerspruch[よって、ここには合致も矛盾も無かろう].
Daß da ein Mißverständnis ist, zeigt sich schon darin[ここに誤解が存在することは次の点から既に明らかだ], daß wir in diesem Gedankengang Deutung hinter Deutung setzen[我々はこの思考過程において解釈に解釈を重ねている]; als beruhige uns eine jede wenigstens für einen Augenblick, bis wir an eine Deutung denken, die wieder hinter dieser liegt[それぞれの解釈が、ともあれ次に控えている解釈を考えるまでの束の間は、我々を落着かせでもするかのごとく]. Dadurch zeigen wir nämlich[それによって我々は次のことを示している訳だ], daß es eine Auffassung einer Regel gibt, die nicht eine Deutung ist[解釈ではない規則把握が在る]; sondern sich, von Fall zu Fall der Anwendung, in dem äußert, was wir »der Regel folgen«, und was wir »ihr entgegenhandeln« nennen[適用事例から適用事例へと、我々が何を「規則にしたがっている」と呼び何を「規則に反して振舞っている」と呼ぶかに表われる規則把握が].
Darum besteht eine Neigung, zu sagen: jedes Handeln nach der Regel sei ein Deuten[そういう訳で、規則にのっとった振舞は何れも解釈である、とする傾向は根強い]. »Deuten« aber sollte man nur nennen: einen Ausdruck der Regel durch einen anderen ersetzen[だが、規則の一表現を別の表現に置き換えることをもっぱら「解釈」と呼ぶべきだろう。].
202. Darum ist ›der Regel folgen‹ eine Praxis[そういう訳で、「規則にしたがう」はプラクシスだ]. Und der Regel zu folgen glauben ist nicht: der Regel folgen[そして《規則にしたがっていると思っている》は《規則にしたがっている》ではない]. Und darum kann man nicht der Regel ›privatim‹ folgen[それ故、規則に「私的に」したがうことは叶わない], weil sonst der Regel zu folgen glauben dasselbe wäre, wie der Regel folgen[さもなければ、《規則にしたがっていると思っている》が《規則にしたがっている》と同じことになってしまうから].
§201 は「Unser Paradox war dies」と過去時制ではじまり、「eine Regel könnte keine Handlungsweise bestimmen, da jede Handlungsweise mit der Regel in Übereinstimmung zu bringen sei」と接続法(第二に第一)で続けられている。つまり、そのパラドクスなるものは念入りに距離を置くようにして呈示されている訳で、さっさと片付けるためにもちだされているようにも受けとれる。(それを酌んで、上ではその出だしを「我々のパラドクスとやらはこれなのだった」と訳してみた。はじめはそれに続く方を今回のこの文章のタイトルのように訳そうかと考えたのだったが。)そして、実際それは、次のような意味で、その場で片付けられていると云い得る。
件のパラドクスとやらは、§198 に現われる「規則がこの場合に何を為すべきかを私に教えるというようなことがどうしてあり得るのか? 私が何を為そうが、それは何らかの解釈によって当の規則に適合させ得るのに」という引用符にくくられた主張ともども、解釈なるものに惑わされた錯誤の見本なのであり、《規則にしたがう》が那辺に存するのかをはっきりさせるための手だてとしてひきあいにだされている。そして、《規則にしたがう》はプラクシスであり、規則に私的にしたがうことは叶わない、ということが見さだめられたところで、用済みとなっている。
なお、俺がひっかかったのは別に原文の叙法や時制ではなくて、「規則が振舞い方を規定することはあり得ない。どんな振舞い方も当の規則に合致させ得るのだから」というようなことがどうして云い得るのか、という点なのだった。そして、あれこれ考えているうちに、これは接続法で述べられているのだから問題としてまともに提起されている訳ではないのではないか、と思いあたったのだった。
もちろん、《規則にしたがう》をめぐる話はこれでは終わらない。ヴィトゲンシュタインがしつこく考え続けたのは§185 に登場する +2 の数列を 1000、1004、1008、1012 と続ける生徒に象徴されることがらだったようなのだが、しかし、それについてはまたの機会としよう。
2016-11-23 11:23
コメント(0)
続続アキレスがカメに云ったこと [ノート]
ヴィトゲンシュタインはキャロルのアキレスとカメについては何も書き遺していないようだ。知ってはいたものの特に云うべきことは無なかった、といったところだろうか。ともあれ、『哲学探究』の頃のヴィトゲンシュタイン流にそれを眺めてみるとどうなるか?
やはり気になるのはカメのこの言葉だ。
And might there not also be some reader who would say 'I accept A and B as true, but I don't accept the Hypothetical'?
ここでユークリッドの第一命題の証明を Heath による英訳から引いておこう。
On a given finite straight line to construct an equilateral triangle.
Let ΑΒ be the given finite straight line.
Thus it is required to construct an equilateral triangle on the straight line ΑΒ.
With centre Α and distance ΑΒ let the circle ΒΓΔ be described; again, with centre Β and distance ΒΑ let the circle ΑΓΕ be described; and from the point Γ, in which the circles cut one another, to the points Α, Β let the straight lines ΓΑ, ΓΒ be joined.
Now, since the point A is the centre of the circle ΓΔΒ, ΑΓ is equal to ΑΒ.
Again, since the point Β is the centre of the circle ΓΑΕ, ΒΓ is equal to ΒΑ.
But ΓΑ was also proved equal to ΑΒ; therefore each of the straight lines ΓΑ, ΓΒ is equal to ΑΒ.
And things which are equal to the same thing are also equal to one another; therefore ΓΑ is also equal to ΓΒ.
Therefore the three straight lines ΓΑ, ΑΒ, ΒΓ are equal to one another.
Therefore the triangle ΑΒΓ is equilateral; and it has been constructed on the given finite straight line ΑΒ.
さて、『哲学探究』のヴィトゲンシュタイン流観点からすれば、カメは次のような問を投げかけているものと解釈し得る。
各ステップの妥当性を丁寧に確かめながらこの証明を辿って来た者が、ΓΑ と ΓΒ はそれぞれ ΑΒ に等しく同一のものに等しいものどもは互いに等しいのだから ΓΑ は ΓΒ に等しい、というステップで立往生して、これは妥当ではない、と断言したとしたらどうか?
件の言葉をこう解した我らがアキレスはカメの背に腰を据えたまま黙って考え込んで彫像のように身じろぎもしなくなってしまった。カメはカメでアキレスが口を開くのをじっと待って石のように動かず・・・。
やはり気になるのはカメのこの言葉だ。
And might there not also be some reader who would say 'I accept A and B as true, but I don't accept the Hypothetical'?
ここでユークリッドの第一命題の証明を Heath による英訳から引いておこう。
On a given finite straight line to construct an equilateral triangle.
Let ΑΒ be the given finite straight line.
Thus it is required to construct an equilateral triangle on the straight line ΑΒ.
With centre Α and distance ΑΒ let the circle ΒΓΔ be described; again, with centre Β and distance ΒΑ let the circle ΑΓΕ be described; and from the point Γ, in which the circles cut one another, to the points Α, Β let the straight lines ΓΑ, ΓΒ be joined.
Now, since the point A is the centre of the circle ΓΔΒ, ΑΓ is equal to ΑΒ.
Again, since the point Β is the centre of the circle ΓΑΕ, ΒΓ is equal to ΒΑ.
But ΓΑ was also proved equal to ΑΒ; therefore each of the straight lines ΓΑ, ΓΒ is equal to ΑΒ.
And things which are equal to the same thing are also equal to one another; therefore ΓΑ is also equal to ΓΒ.
Therefore the three straight lines ΓΑ, ΑΒ, ΒΓ are equal to one another.
Therefore the triangle ΑΒΓ is equilateral; and it has been constructed on the given finite straight line ΑΒ.
さて、『哲学探究』のヴィトゲンシュタイン流観点からすれば、カメは次のような問を投げかけているものと解釈し得る。
各ステップの妥当性を丁寧に確かめながらこの証明を辿って来た者が、ΓΑ と ΓΒ はそれぞれ ΑΒ に等しく同一のものに等しいものどもは互いに等しいのだから ΓΑ は ΓΒ に等しい、というステップで立往生して、これは妥当ではない、と断言したとしたらどうか?
件の言葉をこう解した我らがアキレスはカメの背に腰を据えたまま黙って考え込んで彫像のように身じろぎもしなくなってしまった。カメはカメでアキレスが口を開くのをじっと待って石のように動かず・・・。
2017-11-07 17:13
コメント(0)
番外駄目押し sein はリアルな述語ではない [ノート]
YouTube でジル・ドゥルーズの1980年頃の講義を聴いていたら、ノミナル・デフィニション(définition nominale)とリアル・デフィニション(définition réelle)というのが出て来た。(なお、このコンテクストでは「définition」を「定義」と訳しては不都合なので、敢えて片仮名英語にしておく。)伝統的論理学でおこなわれていた区別で、ディファインされるものの可能性については何も述べないのがノミナル、その可能性を一緒に示すのがリアル・デフィニションなのだそうな。
ドゥルーズはそれを幾何図形の例などを挙げて簡単に説明し、そしてその二通りのデフィニションという観点から資本なるものを論じていくのだが、それはさておき、俺がそこで思ったのは、こういうことを心得ている者はカントの「reales Prädikat」(「prédicat réel」、「real predicate」)に特にひっかかったりはしないだろう、ということなのだった。(ちなみに、リアル・デフィニションをもつ概念はカント流に云えばオブジェクティヴ・リアリティをもつことになる。)だが、あらためて考えてみれば、仮令それを知らなくとも、ドイツ語の「real」もフランス語の「réel」も英語の「real」も現実的というような意味のほかに実際のとか本当のというような意味をもつのだから、厳めしい哲学書に現われているという点に惑わされたりしなければ、別にひっかかるようなこともないのかも知れない。(ところが、「実在的述語」となると、困ったことに、そうはいかないわけだ。上のような「nominal」と対をなす「real」の用法は今日でも経済学に残っているようだが、日本語ではその場合の「real」の訳語は「実質」なわけで、「実在的述語」の「実在」を咄嗟に「実質」と読み換えるのは誰にでもできるようなわざではない。実際、経済学に全然興味の無い俺はながいことそれに気付かずにいたのだった。)
ところで、ハイデガーは、Sein はリアルな述語ではないというカントのテーゼの理解はカント流のリアリティという概念の理解にかかっている(Heidegger, Die Gruntprobleme der phänomenologie, Vittorio Klostermann, S. 37)、としながら、そのくせリアルという形容概念については何も語っていない。それはひとつには、前にも触れたように、メタ概念としてのリアリティが彼には見えていなかったからだろう。リアルもまたメタ概念だから盲点に入っていたわけだろう。それでも、かろうじて次のようなくだりがある。
Sein ist kein reales Prädikat bedeutet, es ist kein Prädikat von einer res〔Sein はリアルな述語でないとはそれが res にかかわる述語でないことを意味する〕(S. 44).
イタリックに注目すれば、「real」はもののとかものにかかわるというようなことを意味すると示唆されているように見えるが、一方、前にも引いたが、次のようなくだりもある。
Realität ist demnach die rechtmäßige, zur Sache, res, selbst, zu ihrem Begriffe gehörige sachhaltige, reale Bestimmung, determinatio〔リアリティは、だから、正当な、当の事物、res そのものに、その概念に適った、実のある、リアルな規定、determinatio だ〕(S. 47).
ここで形容詞、形容句はただ並べられているのではなく、二組に分けられている。そのひとつは「Bestimmung」に直接かかる「sachhaltig」と「real」の組で、これらは共に内容のあるとか実のあるというような意味で用いられているように思われる。(ちなみに、これは単なる臆測だが、元々「sachhaltig」という語は実のあるというような意味での「real」の代替としてひねりだされたものだったのではなかろうか。)結局、「real」がこのような文脈に現われるのは特に奇異なことではないため、ハイデガーとしても、やはり、その意味について格別の注意をはらう必要を覚えなかったということなのだろう。(なお、「définition réelle」の「réel」は、「nominal」を名前のというような意味に解すか名目上のというような意味に解すかに応じて、ものにかかわるというような意味なり実質的というような意味なりに自ずと解されるが、「reales Prädikat」の「real」も、俺はこの点を見逃していたのだが、それと対をなす「logisch」に「Logos」を看て取るか「Logik」を看て取るかに応じて、ものにかかわるというような意味なり実のあるというような意味なりに自ずと解される。ところが、この二系統の意味はすんなりとつながるものではないわけで、そのつながりを明らかにしておこうと試みていたならば、ハイデガーの眼にもきっとメタ概念としてのリアリティが見えて来たことだろうに。かく云う俺にも、だが、それを探る気はない。あいかわらずスコラ哲学には近付きたくないので。)
それはそうと、ハイデガーは、これも前に引いたが、「Kant spricht von der Bestimmung, die zum Was eines Dinges, zur res, hinzukommt〔カントはものの何に、res に加わる規定について語っている〕」(S. 46)と述べている。そこで、これに随って上の第一の文の「res」を「Was eines Dinges」に置き換えて、Sein はリアルな述語でないとはそれがものの何にかかわる述語でないことを意味する、と云うこともできるだろう。さて、ここからが駄目押しだが、ひょっとして、木田元はこのような路をたどり、そして第一の文の示唆どおり「real」をものの何にかかわるというようなことを意味するものと解し、さらに第二の文の「real」と並べられた「sachhaltig」に惑わされたあげく、「real」は事象内容を示すということを意味すると考えるに到ったのではなかろうか?
ともあれ、リアルな述語とはものの何にかかわる述語であるというのは別に間違いではないし、ものの何にかかわるということを事象内容を示すというように解釈するのも、胡乱ではあるものの、間違いではなかろうが、しかし、リアルな述語とは事象内容を示す述語であると云い得るからといって、それで、「real」は事象内容を示すということを意味する、とするのは牽強付会というものだ。
「牽強付会ですよ、先生。」
木田は達者で長生きしたようだが、そう突っ込んで来る者はついに現われなかったのだろうか。
最後に付け加えておけば、「現在」が現に在ることを意味しないように、「実在」も、もしかしたら、元々哲学用語としては実際に在るというようなことを意味するものとして使われだしたわけではなかったのではないか? ひょっとして、それは「real」のスコラ哲学に由来する意味をねらって造語されたものだったのではないか? そんな気がしないでもないのだが、どうだろうか。
ドゥルーズはそれを幾何図形の例などを挙げて簡単に説明し、そしてその二通りのデフィニションという観点から資本なるものを論じていくのだが、それはさておき、俺がそこで思ったのは、こういうことを心得ている者はカントの「reales Prädikat」(「prédicat réel」、「real predicate」)に特にひっかかったりはしないだろう、ということなのだった。(ちなみに、リアル・デフィニションをもつ概念はカント流に云えばオブジェクティヴ・リアリティをもつことになる。)だが、あらためて考えてみれば、仮令それを知らなくとも、ドイツ語の「real」もフランス語の「réel」も英語の「real」も現実的というような意味のほかに実際のとか本当のというような意味をもつのだから、厳めしい哲学書に現われているという点に惑わされたりしなければ、別にひっかかるようなこともないのかも知れない。(ところが、「実在的述語」となると、困ったことに、そうはいかないわけだ。上のような「nominal」と対をなす「real」の用法は今日でも経済学に残っているようだが、日本語ではその場合の「real」の訳語は「実質」なわけで、「実在的述語」の「実在」を咄嗟に「実質」と読み換えるのは誰にでもできるようなわざではない。実際、経済学に全然興味の無い俺はながいことそれに気付かずにいたのだった。)
ところで、ハイデガーは、Sein はリアルな述語ではないというカントのテーゼの理解はカント流のリアリティという概念の理解にかかっている(Heidegger, Die Gruntprobleme der phänomenologie, Vittorio Klostermann, S. 37)、としながら、そのくせリアルという形容概念については何も語っていない。それはひとつには、前にも触れたように、メタ概念としてのリアリティが彼には見えていなかったからだろう。リアルもまたメタ概念だから盲点に入っていたわけだろう。それでも、かろうじて次のようなくだりがある。
Sein ist kein reales Prädikat bedeutet, es ist kein Prädikat von einer res〔Sein はリアルな述語でないとはそれが res にかかわる述語でないことを意味する〕(S. 44).
イタリックに注目すれば、「real」はもののとかものにかかわるというようなことを意味すると示唆されているように見えるが、一方、前にも引いたが、次のようなくだりもある。
Realität ist demnach die rechtmäßige, zur Sache, res, selbst, zu ihrem Begriffe gehörige sachhaltige, reale Bestimmung, determinatio〔リアリティは、だから、正当な、当の事物、res そのものに、その概念に適った、実のある、リアルな規定、determinatio だ〕(S. 47).
ここで形容詞、形容句はただ並べられているのではなく、二組に分けられている。そのひとつは「Bestimmung」に直接かかる「sachhaltig」と「real」の組で、これらは共に内容のあるとか実のあるというような意味で用いられているように思われる。(ちなみに、これは単なる臆測だが、元々「sachhaltig」という語は実のあるというような意味での「real」の代替としてひねりだされたものだったのではなかろうか。)結局、「real」がこのような文脈に現われるのは特に奇異なことではないため、ハイデガーとしても、やはり、その意味について格別の注意をはらう必要を覚えなかったということなのだろう。(なお、「définition réelle」の「réel」は、「nominal」を名前のというような意味に解すか名目上のというような意味に解すかに応じて、ものにかかわるというような意味なり実質的というような意味なりに自ずと解されるが、「reales Prädikat」の「real」も、俺はこの点を見逃していたのだが、それと対をなす「logisch」に「Logos」を看て取るか「Logik」を看て取るかに応じて、ものにかかわるというような意味なり実のあるというような意味なりに自ずと解される。ところが、この二系統の意味はすんなりとつながるものではないわけで、そのつながりを明らかにしておこうと試みていたならば、ハイデガーの眼にもきっとメタ概念としてのリアリティが見えて来たことだろうに。かく云う俺にも、だが、それを探る気はない。あいかわらずスコラ哲学には近付きたくないので。)
それはそうと、ハイデガーは、これも前に引いたが、「Kant spricht von der Bestimmung, die zum Was eines Dinges, zur res, hinzukommt〔カントはものの何に、res に加わる規定について語っている〕」(S. 46)と述べている。そこで、これに随って上の第一の文の「res」を「Was eines Dinges」に置き換えて、Sein はリアルな述語でないとはそれがものの何にかかわる述語でないことを意味する、と云うこともできるだろう。さて、ここからが駄目押しだが、ひょっとして、木田元はこのような路をたどり、そして第一の文の示唆どおり「real」をものの何にかかわるというようなことを意味するものと解し、さらに第二の文の「real」と並べられた「sachhaltig」に惑わされたあげく、「real」は事象内容を示すということを意味すると考えるに到ったのではなかろうか?
ともあれ、リアルな述語とはものの何にかかわる述語であるというのは別に間違いではないし、ものの何にかかわるということを事象内容を示すというように解釈するのも、胡乱ではあるものの、間違いではなかろうが、しかし、リアルな述語とは事象内容を示す述語であると云い得るからといって、それで、「real」は事象内容を示すということを意味する、とするのは牽強付会というものだ。
「牽強付会ですよ、先生。」
木田は達者で長生きしたようだが、そう突っ込んで来る者はついに現われなかったのだろうか。
最後に付け加えておけば、「現在」が現に在ることを意味しないように、「実在」も、もしかしたら、元々哲学用語としては実際に在るというようなことを意味するものとして使われだしたわけではなかったのではないか? ひょっとして、それは「real」のスコラ哲学に由来する意味をねらって造語されたものだったのではないか? そんな気がしないでもないのだが、どうだろうか。
2018-01-07 11:31
コメント(0)
続続続アキレスがカメに云ったこと [ノート]
ずいぶん間があいてしまった。書きたいことが無いわけではないのだが、どうにも機が熟さない。で、ここはひとまずキャロルの What the Tortoise said to Achilles をまるごと引いて、あらためて少しばかりコメントを付すことでお茶をにごしておきたい。
Achilles had overtaken the Tortoise, and had seated himself comfortably on its back.
"So you've got to the end of our race-course?" said the Tortoise. "Even though it does consist of an infinite series of distances? I thought some wiseacre or another had proved that the thing couldn't be done?"
"It can be done," said Achilles; "It has been done! Solvitur ambulando. You see, the distances were constantly diminishing; and so—"
"But if they had been constantly increasing?" the Tortoise interrupted. "How then?"
"Then I shouldn't be here," Achilles modestly replied; "and you would have got several times round the world, by this time!"
"You flatter me—flatten, I mean," said the Tortoise; "for you are a heavy weight, and no mistake! Well now, would you like to hear of a race-course, that most people fancy they can get to the end of in two or three steps, while it really consists of an infinite number of distances, each one longer than the previous one?"
"Very much indeed!" said the Grecian warrior, as he drew from his helmet (few Grecian warriors possessed pockets in those days) an enormous note-book and a pencil. "Proceed! And speak slowly, please. Short-hand isn't invented yet!"
"That beautiful First Proposition of Euclid!" the Tortoise murmured dreamily. "You admire Euclid?"
"Passionately! So far, at least, as one can admire a treatise that wo'n't be published for some centuries to come!"
"Well, now, let's take a little bit of the argument in that First Proposition—just two steps, and the conclusion drawn from them. Kindly enter them in your note-book. And in order to refer to them conveniently, let's call them A, B, and Z:—
(A) Things that are equal to the same are equal to each other.
(B) The two sides of this Triangle are things that are equal to the same.
(Z) The two sides of this Triangle are equal to each other.
Readers of Euclid will grant, I suppose, that Z follows logically from A and B, so that any one who accepts A and B as true, must accept Z as true?"
"Undoubtedly! The youngest child in High School—as soon as High Schools are invented, which wlil not be till some two thousand years later—will grant that."
"And if some reader had not yet accepted A and B as true, he might still accept the sequence as a valid one, I suppose?"
"No doubt such a reader might exist. He might say, 'I accept as true the Hypothetical Proposition that, if A and B be true, Z must be true; but, I don't accept A and B as true.' Such a reader would do wisely in abandoning Euclid, and taking to football."
"And might there not also be some reader who would say, 'I accept A and B as true, but I don't accept the Hypothetical'?"
"Certainly there might. He, also, had better take to football."
"And neither of these readers," the Tortoise continued, "is as yet under any logical necessity to accept Z as true?"
"Quite so," Achilles assented.
"Well, now, I want you to consider me as a reader of the second kind, and to force me, logically, to accept Z as true."
"A tortoise playing football would be—" Achilles was beginning
"—an anomaly, of course," the Tortoise hastily interrupted. "Don't wander from the point. Let's have Z first, and football afterwards!"
"I'm to force you to accept Z, am I?" Achilles said musingly. "And your present position is that you accept A and B, but you don't accept the Hypothetical—"
"Let's call it C," said the Tortoise.
"—but you don't accept
(C) If A and B are true, Z must be true."
"That is my present position," said the Tortoise.
"Then I must ask you to accept C."
"I'll do so," said the Tortoise, "as soon as you've entered it in that note-book of yours. What else have you got in it?"
"Only a few memoranda," said Achilles, nervously fluttering the leaves: "a few memoranda of—of the battles in which I have distinguished myself!"
"Plenty of blank leaves, I see!" the Tortoise cheerily remarked. "We shall need them all!" (Achilles shuddered.) "Now write as I dictate:—
(A) Things that are equal to the same are equal to each other.
(B) The two sides of this Triangle are things that are equal to the same.
(C) If A and B are true, Z must be true.
(Z) The two sides of this Triangle are equal to each other."
"You should call it D, not Z," said Achilles. "It comes next to the other three. If you accept A and B and C, you must accept Z."
"And why must I?"
"Because it follows logically from them. If A and B and C are true, Z must be true. You don't dispute that, I imagine?"
"If A and B and C are true, Z must be true," the Tortoise thoughtfully repeated. "That's another Hypothetical, isn't it? And, if I failed to see its truth, I might accept A and B and C, and still not accept Z, mightn't I?"
"You might," the candid hero admitted; "though such obtuseness would certainly be phenomenal. Still, the event is possible. So I must ask you to grant one more Hypothetical."
"Very good. I'm quite willing to grant it, as soon as you've written it down. We will call it
(D) If A and B and C are true, Z must be true.
Have you entered that in your note-book?"
"I have!" Achilles joyfully exclaimed, as he ran the pencil into its sheath. "And at last we've got to the end of this ideal race-course! Now that you accept A and B and C and D, of course you accept Z."
"Do I?" said the Tortoise innocently. "Let's make that quite clear. I accept A and B and C and D. Suppose I still refused to accept Z?"
"Then Logic would take you by the throat, and force you to do it!" Achilles triumphantly replied. "Logic would tell you, 'You ca'n't help yourself. Now that you've accepted A and B and C and D, you must accept Z!' So you've no choice, you see. "
"Whatever Logic is good enough to tell me is worth writing down," said the Tortoise. "So enter it in your book, please. We will call it
(E) If A and B and C and D are true, Z must be true. Until I've granted that, of course I needn't grant Z. So it's quite a necessary step, you see?"
"I see," said Achilles; and there was a touch of sadness in his tone.
Here the narrator, having pressing business at the Bank, was obliged to leave the happy pair, and did not again pass the spot until some months afterwards. When he did so, Achilles was still seated on the back of the much-enduring Tortoise, and was writing in his note-book, which appeared to be nearly full. The Tortoise was saying, "Have you got that last step written down? Unless I've lost count, that makes a thousand and one. There are several millions more to come. And would you mind, as a personal favour, considering what a lot of instruction this colloquy of ours will provide for the Logicians of the Nineteenth Century—would you mind adopting a pun that my cousin the Mock-Turtle will then make, and allowing yourself to be re-named Taught-Us?"
"As you please!" replied the weary warrior, in the hollow tones of despair, as he buried his face in his hands. "Provided that you, for your part, will adopt a pun the Mock-Turtle never made, and allow yourself to be re-named A Kill-Ease!"
このアキレスとカメの C の類の仮言命題を逐次書きつらねる共同作業を彼等のレースと対比してみたい。まずは、そのレースについて前に見たところを補足を加えつつまとめておこう。
● 我々は、アキレスがカメのスタート地点に達するまでの間にカメもまた先へ進む、ということからコース上の地点を逐次規定するためのひとつの再帰的アルゴリズムを感得するとともに、その規定の作業が原理的には際限無く続行可能であることをさとる。ただし、そのアルゴリズムはそれに適う地点の無限列(あるいは上でカメが云っているような両者の間の隔たりの無限列(an infinite series of distances))の存在を保証するものではない。
● 「以下同様」の類の表現はレースの記述の一部なのではなくて記述に係るものであり、それによって当の記述がさらに進捗することはない。ところが、「以下同様」の闖入はそれで記述が一挙に進んだかのごとき錯覚を惹き起こすとともに、件のコース上の地点を逐次規定する作業の際限無さをあらためて照らし出す効果をもつ。
● それやこれやでレースの記述にまつわる際限無さがアキレスの走りに投影されるところに、パラドクスの幻影が現われる。
さて、アキレスとカメの共同作業だが、我々はカメの「それ[A と B と C が真ならば、Z は真であるほかない、という命題]もやっぱり仮言ではないか。そしてその真理を看て取るのをしくじったならば、私は A と B と C を認めつつもなお Z を認めないことだろう」という言葉から C の類の仮言を逐次書きつらねるための再帰的アルゴリズムを感得するとともに、その書きつらねの作業が原理的には際限無く続行可能であることをさとる。
ここでは C、D、E と仮言が並べられて行くくだりがレースの記述に相当すると云っていいだろう。そして、「以下同様」の役目を果たしているのは透明だった語り手が見物人として顕われて以降のくだりだ。面白いのは彼のだしぬけの登場とともに語りのレヴェルがあざやかに遷移し、そして、レースの場合とは違って、そのままもとに還ることなくはなしが進行する点だ。つまり、ここにはパラドクスの幻影の現出を援けるような仕掛けは無い。もっとも、ここでのアキレスは、際限無さをあらためて投影されるまでもなく、既に際限無く続行可能な作業の一端を担っているわけだが、しかし、その仕事にパラドクシカルなところは無い。(あるいは、これには異議が呈されるかもしれない。アキレスは無限のタスクを遂行しようとしているのだからパラドクシカルではないか、と。たしかに、彼等の共同作業が無限のプロセスから成るものであれば、そう云い得るだろう。そのような作業もやはりひとつの作業であるには違いないから。だが、彼等がたずさわっているのは際限無く続行可能な作業だ。それはもっぱら続行される限りにおいてひとつの作業なのであり、その限りにおいてつねに有限のプロセスから成る。際限無さはその続行可能性にあり、そこに遂行やら完遂やらの出る幕は無い。そして、アキレスがその共同作業の一端を担うことによって遂行しようとしているのはカメに Z が真であると認めさせることであり、それは無限の果てにおいて達成されるようなものではない。)
こうしてみると、いわゆる無限背進の演出はここでは飾りに過ぎないとも云い得る。パラドクシカルなのは、前にも指摘したとおり、その共同作業をはじめるに至るカメとアキレスの遣り取りであり、その核には次のような課題がある。
A と B を真だと認めるが C を認めない者をして Z を真だと論理的に認めざるを得なくせしめよ。
いったいこれにどう応じればいいのか? そのような者を前にしてはそもそも論理的ということが宙に浮いてしまうわけで、しかも、まさに問題の推論こそが、通常は、A と B を真だと認める者をして Z を真だと認めせしめるものなのだから。
ついでに、いかにもキャロルらしいくどさが殺伐としたおかしみをそこはかとなく醸しているところを挙げて終えるとしよう。「The two sides of this Triangle are things that are equal to the same」という命題 B のフォーミュレーションがそれだ。ここには「things that are」など無くていいし無い方がすっきりするのにわざわざ付け加えてあるのは、もちろん、A に揃えるためだろう――そうしないことには A の主語と B の述語が正確には一致せず三段論法の型に微妙に合わなくなってしまうから。
☆ ☆ ☆
WHAT THE TORTOISE SAID TO ACHILLES
Lewis Carroll
Achilles had overtaken the Tortoise, and had seated himself comfortably on its back.
"So you've got to the end of our race-course?" said the Tortoise. "Even though it does consist of an infinite series of distances? I thought some wiseacre or another had proved that the thing couldn't be done?"
"It can be done," said Achilles; "It has been done! Solvitur ambulando. You see, the distances were constantly diminishing; and so—"
"But if they had been constantly increasing?" the Tortoise interrupted. "How then?"
"Then I shouldn't be here," Achilles modestly replied; "and you would have got several times round the world, by this time!"
"You flatter me—flatten, I mean," said the Tortoise; "for you are a heavy weight, and no mistake! Well now, would you like to hear of a race-course, that most people fancy they can get to the end of in two or three steps, while it really consists of an infinite number of distances, each one longer than the previous one?"
"Very much indeed!" said the Grecian warrior, as he drew from his helmet (few Grecian warriors possessed pockets in those days) an enormous note-book and a pencil. "Proceed! And speak slowly, please. Short-hand isn't invented yet!"
"That beautiful First Proposition of Euclid!" the Tortoise murmured dreamily. "You admire Euclid?"
"Passionately! So far, at least, as one can admire a treatise that wo'n't be published for some centuries to come!"
"Well, now, let's take a little bit of the argument in that First Proposition—just two steps, and the conclusion drawn from them. Kindly enter them in your note-book. And in order to refer to them conveniently, let's call them A, B, and Z:—
(A) Things that are equal to the same are equal to each other.
(B) The two sides of this Triangle are things that are equal to the same.
(Z) The two sides of this Triangle are equal to each other.
Readers of Euclid will grant, I suppose, that Z follows logically from A and B, so that any one who accepts A and B as true, must accept Z as true?"
"Undoubtedly! The youngest child in High School—as soon as High Schools are invented, which wlil not be till some two thousand years later—will grant that."
"And if some reader had not yet accepted A and B as true, he might still accept the sequence as a valid one, I suppose?"
"No doubt such a reader might exist. He might say, 'I accept as true the Hypothetical Proposition that, if A and B be true, Z must be true; but, I don't accept A and B as true.' Such a reader would do wisely in abandoning Euclid, and taking to football."
"And might there not also be some reader who would say, 'I accept A and B as true, but I don't accept the Hypothetical'?"
"Certainly there might. He, also, had better take to football."
"And neither of these readers," the Tortoise continued, "is as yet under any logical necessity to accept Z as true?"
"Quite so," Achilles assented.
"Well, now, I want you to consider me as a reader of the second kind, and to force me, logically, to accept Z as true."
"A tortoise playing football would be—" Achilles was beginning
"—an anomaly, of course," the Tortoise hastily interrupted. "Don't wander from the point. Let's have Z first, and football afterwards!"
"I'm to force you to accept Z, am I?" Achilles said musingly. "And your present position is that you accept A and B, but you don't accept the Hypothetical—"
"Let's call it C," said the Tortoise.
"—but you don't accept
(C) If A and B are true, Z must be true."
"That is my present position," said the Tortoise.
"Then I must ask you to accept C."
"I'll do so," said the Tortoise, "as soon as you've entered it in that note-book of yours. What else have you got in it?"
"Only a few memoranda," said Achilles, nervously fluttering the leaves: "a few memoranda of—of the battles in which I have distinguished myself!"
"Plenty of blank leaves, I see!" the Tortoise cheerily remarked. "We shall need them all!" (Achilles shuddered.) "Now write as I dictate:—
(A) Things that are equal to the same are equal to each other.
(B) The two sides of this Triangle are things that are equal to the same.
(C) If A and B are true, Z must be true.
(Z) The two sides of this Triangle are equal to each other."
"You should call it D, not Z," said Achilles. "It comes next to the other three. If you accept A and B and C, you must accept Z."
"And why must I?"
"Because it follows logically from them. If A and B and C are true, Z must be true. You don't dispute that, I imagine?"
"If A and B and C are true, Z must be true," the Tortoise thoughtfully repeated. "That's another Hypothetical, isn't it? And, if I failed to see its truth, I might accept A and B and C, and still not accept Z, mightn't I?"
"You might," the candid hero admitted; "though such obtuseness would certainly be phenomenal. Still, the event is possible. So I must ask you to grant one more Hypothetical."
"Very good. I'm quite willing to grant it, as soon as you've written it down. We will call it
(D) If A and B and C are true, Z must be true.
Have you entered that in your note-book?"
"I have!" Achilles joyfully exclaimed, as he ran the pencil into its sheath. "And at last we've got to the end of this ideal race-course! Now that you accept A and B and C and D, of course you accept Z."
"Do I?" said the Tortoise innocently. "Let's make that quite clear. I accept A and B and C and D. Suppose I still refused to accept Z?"
"Then Logic would take you by the throat, and force you to do it!" Achilles triumphantly replied. "Logic would tell you, 'You ca'n't help yourself. Now that you've accepted A and B and C and D, you must accept Z!' So you've no choice, you see. "
"Whatever Logic is good enough to tell me is worth writing down," said the Tortoise. "So enter it in your book, please. We will call it
(E) If A and B and C and D are true, Z must be true. Until I've granted that, of course I needn't grant Z. So it's quite a necessary step, you see?"
"I see," said Achilles; and there was a touch of sadness in his tone.
Here the narrator, having pressing business at the Bank, was obliged to leave the happy pair, and did not again pass the spot until some months afterwards. When he did so, Achilles was still seated on the back of the much-enduring Tortoise, and was writing in his note-book, which appeared to be nearly full. The Tortoise was saying, "Have you got that last step written down? Unless I've lost count, that makes a thousand and one. There are several millions more to come. And would you mind, as a personal favour, considering what a lot of instruction this colloquy of ours will provide for the Logicians of the Nineteenth Century—would you mind adopting a pun that my cousin the Mock-Turtle will then make, and allowing yourself to be re-named Taught-Us?"
"As you please!" replied the weary warrior, in the hollow tones of despair, as he buried his face in his hands. "Provided that you, for your part, will adopt a pun the Mock-Turtle never made, and allow yourself to be re-named A Kill-Ease!"
☆ ☆ ☆
このアキレスとカメの C の類の仮言命題を逐次書きつらねる共同作業を彼等のレースと対比してみたい。まずは、そのレースについて前に見たところを補足を加えつつまとめておこう。
● 我々は、アキレスがカメのスタート地点に達するまでの間にカメもまた先へ進む、ということからコース上の地点を逐次規定するためのひとつの再帰的アルゴリズムを感得するとともに、その規定の作業が原理的には際限無く続行可能であることをさとる。ただし、そのアルゴリズムはそれに適う地点の無限列(あるいは上でカメが云っているような両者の間の隔たりの無限列(an infinite series of distances))の存在を保証するものではない。
● 「以下同様」の類の表現はレースの記述の一部なのではなくて記述に係るものであり、それによって当の記述がさらに進捗することはない。ところが、「以下同様」の闖入はそれで記述が一挙に進んだかのごとき錯覚を惹き起こすとともに、件のコース上の地点を逐次規定する作業の際限無さをあらためて照らし出す効果をもつ。
● それやこれやでレースの記述にまつわる際限無さがアキレスの走りに投影されるところに、パラドクスの幻影が現われる。
さて、アキレスとカメの共同作業だが、我々はカメの「それ[A と B と C が真ならば、Z は真であるほかない、という命題]もやっぱり仮言ではないか。そしてその真理を看て取るのをしくじったならば、私は A と B と C を認めつつもなお Z を認めないことだろう」という言葉から C の類の仮言を逐次書きつらねるための再帰的アルゴリズムを感得するとともに、その書きつらねの作業が原理的には際限無く続行可能であることをさとる。
ここでは C、D、E と仮言が並べられて行くくだりがレースの記述に相当すると云っていいだろう。そして、「以下同様」の役目を果たしているのは透明だった語り手が見物人として顕われて以降のくだりだ。面白いのは彼のだしぬけの登場とともに語りのレヴェルがあざやかに遷移し、そして、レースの場合とは違って、そのままもとに還ることなくはなしが進行する点だ。つまり、ここにはパラドクスの幻影の現出を援けるような仕掛けは無い。もっとも、ここでのアキレスは、際限無さをあらためて投影されるまでもなく、既に際限無く続行可能な作業の一端を担っているわけだが、しかし、その仕事にパラドクシカルなところは無い。(あるいは、これには異議が呈されるかもしれない。アキレスは無限のタスクを遂行しようとしているのだからパラドクシカルではないか、と。たしかに、彼等の共同作業が無限のプロセスから成るものであれば、そう云い得るだろう。そのような作業もやはりひとつの作業であるには違いないから。だが、彼等がたずさわっているのは際限無く続行可能な作業だ。それはもっぱら続行される限りにおいてひとつの作業なのであり、その限りにおいてつねに有限のプロセスから成る。際限無さはその続行可能性にあり、そこに遂行やら完遂やらの出る幕は無い。そして、アキレスがその共同作業の一端を担うことによって遂行しようとしているのはカメに Z が真であると認めさせることであり、それは無限の果てにおいて達成されるようなものではない。)
こうしてみると、いわゆる無限背進の演出はここでは飾りに過ぎないとも云い得る。パラドクシカルなのは、前にも指摘したとおり、その共同作業をはじめるに至るカメとアキレスの遣り取りであり、その核には次のような課題がある。
A と B を真だと認めるが C を認めない者をして Z を真だと論理的に認めざるを得なくせしめよ。
いったいこれにどう応じればいいのか? そのような者を前にしてはそもそも論理的ということが宙に浮いてしまうわけで、しかも、まさに問題の推論こそが、通常は、A と B を真だと認める者をして Z を真だと認めせしめるものなのだから。
ついでに、いかにもキャロルらしいくどさが殺伐としたおかしみをそこはかとなく醸しているところを挙げて終えるとしよう。「The two sides of this Triangle are things that are equal to the same」という命題 B のフォーミュレーションがそれだ。ここには「things that are」など無くていいし無い方がすっきりするのにわざわざ付け加えてあるのは、もちろん、A に揃えるためだろう――そうしないことには A の主語と B の述語が正確には一致せず三段論法の型に微妙に合わなくなってしまうから。
2019-05-11 19:37
コメント(0)


